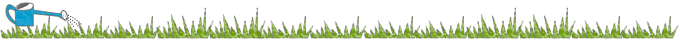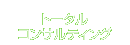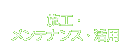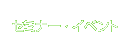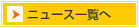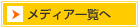屋上菜園物語(1)我が家
真澄は買物のついでにふと屋上に上がってみようという気になった。館内の案内板に屋上の利用案内のポスターが貼ってあったからだ。急いで家に帰ることもなかった。夫が朝出社してから夜迄、真澄は一人だった。「今日は荷物も軽いし」エレベータで10階に上がる。
エレベータホールのドアを開けて階段を降りると屋上は緑一色だった。
「ワーッ」
真澄は胸の内で小さく叫んだ。
「こんなふうになっているんだ。へ~、知らなかった。」
屋上の左側には菜園があり、その奥にブドウの棚。右側に芝生が広がっていて、島のような感じで花壇がポツン、ポツンとある。
「ビルの上がこんなふうになっているんだ。」巡回しているガードマンが会釈をして去っていく。
5月の空が大きく、高く頭上に広がっていた。思わず深呼吸をした。すぐ近くに東京スカイツリーが見える。屋上の鮮やかな緑が真澄の落ち込んでいる気持にも映り、少し元気が出てきた。
屋上には何人かの買物客が上がってきている。子供を乗せたバギーを前に置いて、ベンチで休息がてら会話を楽しんでいる母親たち。真澄は見るともなしに親子を見ていた。
「私にもあのような光景がやってくるかしら」
若いカップルが芝生の上を歩きながら囁き合っている。二人だけの世界。「私にもあんな時があったわ」
真澄は暫く自分が立ち止まっていたことに気がつき、歩き始めた。まず菜園の区画に向かった。
「どんなお野菜を栽培しているのかしら」
区画毎に栽培している野菜のプレートが立っている。
四季成りイチゴ、ミニトマト、ナス、シシトウ、フルーツピーマン、キューリ、スイカ、エダマメ、サツマイモ。
屋上でもこんなにいろいろできるんだ。真澄は区画毎に野菜を見て回った。野菜の苗たちがそれぞれ元気に生長している。思わず声をかけた。
「元気に育つのよ」
屋上菜園の案内板を読む。
「この屋上では15cmの深さの土で葉物、実物、根物野菜を有機栽培しています。一番美味しい旬の時に完熟の野菜を収穫します」
「そんな薄い土で野菜が育つのかしら」
しゃがんで、ミニトマトの株を見ると小さな黄色い花がいくつもついている。葉物野菜はともかく、実もの野菜、根もの野菜はもっと深い土ではないと良く育たないんじゃないかしら」
真澄は野菜栽培のことは良く知らないが、最近テレビで農業番組が増えてきているので、何気なく見ている。
真澄は福井の出身で、今の夫とは大阪で知り合い、夫の転勤で東京に来た。東京には友人が一人もいない。いつか大阪に帰ると思うと、友人を東京でつくることにあまり積極的になれない。夫からは友達をつくれ、と言われるけど。私は友達との別れがとても辛いタイプなの。
真澄はミニトマトの花にそっと声をかけた。
「私はひとりぽっちなのよ。トマトさんはお友達が沢山いていいわね」
トマトの区画にはトマトの株が10本以上植えられている。
ミツバチが飛んできて花から花へと動きまわっている。
「こんな屋上にもミツバチが来るんだわ。どこから来るのかしら」
ミツバチが去った後、微風に揺れながらミニトマトが真澄に話しかけた。
「私達は花を咲かせ、黄色い花を赤い実に変えていきます。最後はあなたの背丈ほどにもなりますよ。最初、この屋上菜園に来た時には思わず泣いてしまいました。こんな薄い土でしかも乾燥しやすいところで、生きるなんてとてもできない、と思ったからです。でも私達を世話してくださる方達のお陰で今では『大丈夫』という気持で毎日を生きています」
真澄は思わず答えるともなしに言った。
「トマトさんはミツバチさん、それに世話してくださる方達がいて幸せね」
トマトが言った。
「真澄さんにもきっとそのような方達がいるはずですよ。」
「そうね、そうだといいんだけど。・・・私、結婚したら早くお母さんになりたいと思ったの。でもなかなか子供に恵まれなくて、もう3年たったわ。年齢のこともあるし、焦ってもいるの」
トマトは言った。
「今はまだ5月で実は一番下の枝にしかついていませんが、2番目、3番目・・・6番目と枝に花が次々と付いて実が鈴なりのようにたくさんつくんですよ。楽しみにしていてください」
トマトの花をじっと見詰ていた真澄はふと我に返り、ゆっくりと立ち上がった。
ブドウの棚に近づいて行った。太い枝が2本伸び、そこから等間隔で細い枝が伸び、葉が繁っている。「今年の9月には枝たわわのブドウが稔ります」とブドウの区画の案内板に書いてある。「ブドウもできるんだ」
ブドウの向こう、フェンス越しに隅田川が銀色に光りながら流れているのが見える。
真澄はフェンスに近づき、眼下に拡がる町を見た。その中に自分の家が見えたような気がした。そこだけかすかに光っているように見える。
真澄はわが家を両手の手のひらで包むようにして言った。「私の家・・・」
フェンスを離れ、エレベータ乗り場に向かう時、屋上菜園の傍を通った。真澄は思わず
野菜たちに声をかけた。
「今日はありがとう。お蔭で元気が出たわ」
トマトが言った。「真澄さん、夫婦は向き合うことが大切です。相手を深く知ることです。
ある時は勇気を持って相手の真実に向き合いましょう。そして何気ない時も含めて夫婦一緒の時間をできるだけ取ってくださいね。真澄さんには分からないかもしれませんが、私たちもそのようにして生きています。・・・そして気が向いたらこの屋上菜園に時々でいいですから、足を運んでください。私たちも真澄さんと笑顔の時を一緒に持ちたいと願っているんですよ」
屋上菜園物語(2)ほんとうの人間になる
西堀啓介は72歳を過ぎたころから、今迄と違う自分を感じるようになっていた。電車に乗り、流れていく外の風景を見ながら、何か懐かしさと淋しさを感じるのだ。さらに言えばこの世にいる自分とあの世に行った自分、その二人が同じ風景を同時に見ている、という感じだろうか。そして淋しさがこみあげてくる。こんな経験は初めてだ。ひょっとするとお迎えが近いのだろうかとさえ思う。
啓介は思わずつぶやいた。「俺の人生って一体何だったんだろう」
啓介は先日、親友の森山に心の中の悩みを聞いてもらった。
啓介「最近淋しいんだ。何か具体的理由があるわけではないんだけど、とにかく淋しい」
森山「いつも元気そうにしているから、そんなふうに見えなかったけど、どうしたんだろうね」
啓介「高齢者のウツ病に俺もかかり始めているのかもしれない、と思ったりしている」
森山「最近、倉田百三の『出家とその弟子』を読んでいたら、こんな箇所があった。親鸞が弟子の唯円に、『私も淋しいのだよ。私は一生淋しいのだろうと思っている。もっとも今の私の淋しさはお前の淋しさとは違うがね』と答えている」
啓介「今迄の人生ではあれやこれやとやるべきことが山ほどあって、淋しいと思う時は殆ど無かった。自分と向き合う時間も敢えて持たなかったし・・・」
森山「その意味では今がその時なのかもしれないね」
啓介「来るべき時が来た、ということなのかな」
帰宅後、啓介はお茶を飲んで一服した後、今住んでいるマンションの屋上に上がった。夕暮れが始まっていた。遠くの空が夕焼けでオレンジ色に染まっている。階段を上がったすぐのところに菜園がある。啓介は気分転換を兼ねて時々屋上に上がる。菜園には季節毎にいろいろな野菜が育っている。オーナーの天海さんが、屋上菜園で野菜の有機栽培を専門にやっているガーデンマスターと一緒に野菜の世話をしている。ミニトマト、ナス、キュウリ、ピーマン、ジャガイモ、それに葉物野菜のフリルレタス、ハーブではルッコラ、ミント、カモミール、ローズマリー。もう一つの区画は芝生で緑化されていて、ブドウ、オリーブなどの果樹も植わっている。
啓介はウコンの前で立ち止まった。茎から大きな葉が何枚も出て、花が咲いている。蘭のような薄緑かかった白い花。こんなに可憐な花が咲くとは・・・啓介はしばらく見とれていた。それにしてもこんな15cmの薄い土で根物野菜がよくできるもんだ。ウコンの花に触ってみた。「野菜の花ってきれいなんだな」その時、夕べの風が吹いてきてウコンの葉を揺らした。啓介はウコンに思わず話しかけた。「俺に力をくれないか。自分の人生は、失敗と挫折の連続だったように感じている。最近つくづくそう思う。世間は俺には微笑んでくれなかった。俺みたいな人間はこれから生きていてもたいしたことはないように思うんだ」
また風が吹いてきた。その風の中で何か声が聞こえた。
「私は秋ウコンです。私はウコンとして生まれ、ウコンとして生長し、そして根茎をつけて一生を全うします。その間、遅霜にやられたり、害虫に葉を食べられたりしますが、それは生きていくためには仕方がないことだと思っています。私の願いは次の世代のために元気な、ほんとうの根茎を残すことです。西堀さんの人生もご自分だけの人生ではなく、次の世代の人達のための人生なのではありませんか」
啓介は慌ててあたりを見渡したが、誰もいない。確かにウコンが話しているのだ。啓介は目の前のウコンをもう一度見た。ウコンは言葉をつないだ。
「元気を出してくださいな。私は屋上で朝日を浴び、夜は星空を見ています。ただこんな都会では見える星は限られていますが、夜明け前の星が一番きれいに見えますよ」
夕焼けが最後の光を放った後、急に暗くなってきた。
マンションの部屋に戻ったら、妻の良枝が帰宅していた。夕食の準備で忙しい。啓介は良枝にウコンの話をしようかと喉まで出かかったが、飲み込んだ。「少し疲れているんじゃないの。だいじょうぶ?」と言われるのが関の山と思ったからだ。
あくる日、啓介は森山に電話をした。次の日、早速行きつけのカフェで会った。
啓介「実は昨日俺の住んでいるマンションの屋上菜園でウコンと話したんだ」
森山「農園を経営している人で野菜と話ができる人がいる、と聞いたことがあるけど、西堀くんもいよいよその域に達した、ということかな。・・・それでどんな話だった?」
啓介「ウコンが言うんだ。『私の願いは次の世代のために元気な、ほんとうの根茎を残すことです』って。」
森山「ほんとうの根茎か。俺も最近思うんだ。俺たちが生きているのはほんとうの人間になることではないか、と。ほんとうの人間になるためには成功よりも失敗、挫折、試練を経験することが大事なんじゃないかな。」
啓介「ほんとうの人間?・・・そんなこと、今迄考えたこともなかった。なんだか意味が深そうだな」
森山「ある人がこう言ったそうだ。『自分は成功のみを追求したからこそ、人生に失敗したのだ。たしかに仕事においては成功したかもしれない。しかし自分はほんとうの人間になることにおいて失敗した』、と」
啓介「俺たちが目指すべきはほんとうの人間、ということなんだね」
森山「能力、立場、環境に関係なく目指すことができる。そのためになくてはならないのは・・・なんだろう」
啓介「俺にもほんとうの人間を目指すことができるのかな。あのウコンがほんとうの根茎を残す、と言ったように」
啓介は森山と別れてマンションに戻った。すぐに屋上に行き、ウコンの前に立った。
「ありがとう。お蔭で気持ちが吹っ切れた、というより整理できた。これからの残りの
人生、ほんとうの人間を目指して、生きていくよ。そう思ったら全てが愛おしくなってきたような気がする」。
ウコンは微笑みながら言った。「西堀さんだったらできます。人には愛という神様が与えてくださった尊い宝があります。是非愛を見つけてください。そうすれば西堀さんの人生の失敗、挫折に新しい光が注がれるはずです。もう一度新しい気持ちで残りの人生を生きてくださいな。そのためには健康です。私には肝臓の機能を高める効果があります。そのままでは苦いのでハチミツ漬けにして食べてくださいね。」
屋上菜園物語(3)故郷の母
菜穂は芝生と花壇、そして菜園のある屋上に久しぶりに上がってきた。今日はなぜか休憩時間を緑と空のある屋上で過ごしたいと思った。大きな青空だ。芝生を踏みながら、菜園のところにきた。夏野菜の収穫も終わり、菜園に残っている野菜は少なかった。菜園の一角に刈り取ったばかりの稲が干してあった。支柱を合掌式に組み合わせ、その間を支柱が横に渡してある。「そうなんだ、今年屋上で稲を育てていたんだ、知らなかった」。稲束の上には赤い鳥除けネットが掛けられていた。「そうよ、スズメが群でくるから。田舎と同じだ」
菜穂はそうつぶやいた後、故郷の風景を思い出した。そして母の顔を。
菜穂の両親は代々続く農家だった。米作を中心にしながらもその時、その時でいろいろな野菜をつくっていた。昔はタバコも栽培していた。儲かるからということでシイタケ栽培に力を入れたこともあった。父は耕運機に乗って作業していた時、バランスを崩し、耕運機の下敷きになって命を落としてしまった。夕方になっても帰ってこないので、畑に行ってみたら息絶えている父がいた。高校1年生の時だった。
菜穂には兄弟がいなかった。一人っ子だった。母は田畑を守るために、父が亡くなった後、遮二無二働いた。家事は菜穂の担当となったが、忙しい時には田んぼに、畑にと駆り出された。「身を粉にして働かなくては食べていけない」それが母の口癖だった。
母は菜穂が地元の男性と結婚することを望んでいた。しかし菜穂は田舎で一生を過ごすとは考えていなかった。母と一緒に汗を流して働いたが家の暮らしは一向に楽にならず、「農業には将来性がない」と心の底からそう思った。
「私は東京に出て、東京で働き、東京に住みたい」
高校3年生になった時、将来の進路を決めなければならない。菜穂の夢は服飾デザイナーだった。母に負担はかけられない、との思いから昼、夜飲食店でアルバイトをしながら生活費と学費を稼いで、ある程度貯まったら専門学校に行く、と母親に話した。
母は「おまえがそう決めているなら、反対はしないけど、東京の生活は大変だよ。身体を壊さないか心配だ」
高校を卒業後、母の兄にあたる伯父さんに保証人になってもらってアパートを借りた。また飲食店に勤める際の保証人にもなってもらった。母が頼んでくれたのだ。
東京のアパートは家賃をできるだけ節約したかったので、板橋区を通る、私鉄の電車の線路近くの部屋を借りた。北西向きで殆ど陽があたらない部屋だった。早朝に家を出て、夜遅く帰ってくる。終電の通る音を聞きながら眠った。土曜日、日曜日も働いた。収入が多い月は母に仕送りをした。母からは毎月手紙が来た。
東京に来てから2年経った秋、菜穂は久振りで田舎に帰った。田畑の風景に耕作放棄地が目立った。「みんな歳をとって、はあ、農作業ができなくなってきたよ」「かあちゃんはまだ若い方だから頑張れるけど、正直しんどくなってきただよ」
「手伝ってくれる人もいるかもしれないが、多分みんな年寄りだろう。かあちゃんだけはいつまでも元気でいてほしい」菜穂は心の中で呟いた。
東京に出てきてから4年が経った。菜穂は服飾デザインの道を諦めてはいなかったが、専門学校に行くだけの資金を貯めることはできなかった。今はこの商業ビルの6階にあるオーガニックの雑貨店の店員として働いている。毎月の母への仕送りも続けている。
今日屋上に来て、干してある稲束を見て、思わず母の顔を思いだした。それだけでなく稲刈りの後、母と一緒に稲を干したことも思い出した。
屋上菜園で野菜の世話をしている人がいる。私が暫く干してある稲束を見ていたので、そっと声を掛けてくれた。「どうしました?」私は思わず「田舎の母を思い出していたんです」
「ご実家は田舎なんですね」「そうです。この時期はこんな田園風景が広がっています」
「そうなんですね。・・・東京の真ん中、ビルの屋上でもお米ができるんですよ」
菜穂はその人と別れ際に言った。「今晩母に電話します」。しかし菜穂はなぜか母に電話ができなかった。いつも忙しさにかまけて母に電話もかけず、手紙もかかない自分を責める気持ちがあったからかもしれない。「あの子は用事がある時だけしか連絡していこない」と思われているのではないか。
翌日また屋上菜園に行った。稲束は昨日と同じだ。少し風に揺れている。今日は屋上菜園を世話する人もいない。自分一人だ。稲束をじっと見つめていると声が聞こえてきた。
「菜穂さん、今日はお母さんに電話をしてくださいね。お母さんは菜穂さんの声を聞きたいんです。お母さんは田畑の仕事の後、毎晩たった独りで夕食をとっています。淋しさに耐えながら・・・、ある時は涙をこぼしながら、「菜穂・・・、お父ちゃん・・・」と、すぐ目の前にいるかのようにそっと声をかけて食事をしていますよ。
お母さんは言っていました。「菜穂が本当に幸せになる迄、お父ちゃん、私はそっちにいけないよ~。」
菜穂は思わず稲束に尋ねた。「あなたにどうして母のことが分かるんですか?私の実家は栃木です。こことは遠く離れているのに」
稲束は答えた。栃木のあなたのお母さんのところから昨晩、ここまで風が吹いてきて、そう伝えてくれたのです。」
菜穂は思わずそこにしゃがみこんで泣いた。
その晩、菜穂は母に電話をした。
「お母さん、菜穂。ごめんね、ずっと連絡していなくて」
「菜穂、元気にしているかい?」
「私は元気よ。お母さんは元気?」
「大丈夫だよ、それはそうと東京の生活はどうだい。仕事はうまくいってるかい。」
「生活も、仕事も順調よ」
「そうかい。そうかい。それは良かった、私は周りの皆に助けられて元気にしているからね。心配しなくていいよ。今日はもう遅いから早く寝なさい、明日も仕事があるんだろ」
屋上菜園物語(4)居酒屋
昭代は店先の灯を消し、暖簾を外して、店の中に入れた。終電車が通り過ぎていった。昭代の居酒屋は埼玉県N市の駅の近くにある。今日も一日が終わった。昭代は夫の信夫と一緒にこの居酒屋を切り盛りしてきたが、半年前、夫が脳溢血で倒れた。幸い軽かったが暫く病院で治療を受け、今は家で静養している。そんな訳で昭代が一人で酒の肴をつくり接客しているが、有難いことに客足は以前と変わりない。
「大将には早く良くなってまた店に立ってほしいな。暫く女将さんが大変だけど頑張って。直に戻ってくるよ。」そう励ましてくれるお客さんの気持ちに励まされて昭代は店に立っていた。
昭代はふと大事なことを思い出したかのように立ち上がって店の外に出た。
「そうそう、うっかりしてたわ。今晩は冷え込みそうだから店の中に入れておきましょう。」
昭代は外の台の上に置いてあったスナップエンドウのプランターを「よいしょ」と店の中に入れた。外の寒風に吹かれていたスナップエンドウをぼんやり見ながら屋上菜園の講習会で講師が「本葉が5枚ぐらいになれば氷点下の寒さでも大丈夫」と言っていたのを思い出した。昭代は市の社会福祉法人主催の有機野菜栽培教室に2年間通い続けた。
それで一通りの野菜栽培のやり方を知ることができた。その中でやはり手間がかからないものということで、店先で夏はウコンとえごまを育ててお客さんに喜んで頂いた。秋冬野菜ではスナップエンドウを栽培した。そして昭代はスナップエンドウになぜか惹かれた。
昭代はスナップエンドウに声を掛けた。
「スナップエンドウさん、頑張って! 私も頑張っているのよ。春になったらグングン伸びて花を一杯咲かせて美味しい実を沢山つけてね」
夫が待っている家は店から歩いて5分ぐらいのところにある。昭代は気持ちを切り替えるためもあって店を出る前に、好きな演歌を1つ唄った。今晩はちあきなおみが唄った「昭和えれじい」。3番の歌詞、死んだつもりでもう一度 待ってみようかねえお酒 いつか来る春 昭和川 を唄った後、ふいに涙がこぼれた。「もう一度・・・」とつぶやいた。
昭代は店の鍵を閉め、徒歩で深夜の街を歩き、帰宅した。アパートの扉を開けると部屋には電気がついていた。夫はテレビを見ていた。昭代は急いで遅い夕食を作った。夫は一時はすっかり気力をなくしてしまったが、今は早く店に出たいと口癖のように言う。手足に軽い麻痺があるが、何とか歩き、箸も使えるようになった。昭代は今日来たお客さんのことを信夫に話した。信夫は黙って聞いていた。
昭代が信夫と会ったのは今から45年前だった。故郷の岡山から大学入学のための東京に出てきた。実家は農家だった。私学だったので入学金、学費は高かったが、実家の両親は一人娘のために大枚をはたいてくれた。
昭代は両親に生活費と家賃はアルバイトで何とかするから、と伝えた。
当時学生ができるアルバイトは限られていた。入学後、大学の掲示板にアルバイト募集広告が掲載されていたので、昭代は毎日のように貼紙を見た。下宿は恵比寿駅近くの川傍の4畳半の部屋を借りた。いろいろとバイトをやったが、毎月の生活費と家賃を稼ぐことは簡単ではなかった。同じように地方から出てきて同じクラスの圭子と学食でランチを食べていた時、圭子がふいに聞いた。
「昭代、今どこでバイトをしているの?」
昭代は一呼吸置いて答えた。
「今はカステラをつくる工場で働いているわ。午後5時から11時迄」
圭子「それで家賃を払って食べていける?」
昭代は言い淀んだ。その表情を見て圭子は秘密を明かすかのように昭代の耳元に顔を寄せ囁いた。「私はアルバイトサロンでバイトしているの。時給もずっといいし・・・」
その日はそれで圭子と別れたがバイト先から下宿先に帰ってきて遅い夕食を食べた後、昭代は圭子に思い切って相談してみることにした。
日本は高度成長期に入っていた。もはや戦後は終わったとも言われた。働けば豊かになれる、そんな素朴な楽観的気分が時代を覆っていた。サラリーマンにとってアルバイトサロン(アルサロ)は気軽な気分転換のための場所だった。あちこちにアルサロがあった。
昭代がアルバイトサロンで働いていた時、ムード歌謡のグループが定期的にやってきた。バックコーラスの中に信夫は居た。ある晩、アルバイトサロンがある駅前のスナックで昭代は一息入れていた。大学の授業に出席するため、下宿は毎朝7時半には出ていた。そろそろ帰ろうかという時に信夫が店に入ってきた。
先に信夫が声を掛けてきた。「アレ、さっきのサロンで働いていたお姉さんじゃないかな」
それがキッカケになり、付き合いが始まった。信夫はムード歌謡の仕事がない時はカラオケスナックで店員として働いているとのことだった。
そしていつの間にか二人は同棲するようになった。二人の稼ぎを合わせても生活はカツカツだった。それがもとで喧嘩することも度々だった。何が面白くないのか、信夫が酔っ払って帰ってくることが多くなった。そんな日々が続いていたある日、信夫が山手線ガード下の居酒屋が後釜を探しているという話を聞きつけてきた。
それから45年、二人は居酒屋の主人と女将として生きてきた。結局昭代は大学には3年間通って中退した。ささやかな結婚式を東京で挙げた。せめてもの親孝行のつもりだったが、来てくれたのは母親だけだった。父親は「水商売の男と結婚させるために昭代を大学に入れたんじゃない」と昭代の結婚を認めようとはしなかった。
昭代が30歳になって居酒屋の経営も軌道に乗った頃、妊娠した。男の子だった。店の準備があるので、どこかに預けなければならかった。その苦労が尾を引き、結局子供は一人しかつくらなかった。今息子はサラリーマン生活をしている。水商売は夜が遅く、また家族の時間が持てないことを息子はいやというほど知っていた。結婚して子供が2人いる。
冬が終わり、3月。店先のスナップエンドウはグングン伸び、支柱に絡んでいる。花も増えてきた。2月に信夫が店に復帰してお客さんに元気な姿を見せていたが、脳溢血が再発し、信夫は店の中で倒れた。入院した病院の医師からは症状が重く、もう仕事は無理と宣告された。父親の病状を息子に伝えると、1週間後、息子から思いもよらない返事が来た。妻と相談した結果、息子が居酒屋を継ぐことにした、とのことだった。但し妻は居酒屋の女将にはならず、今の仕事を続けるという条件だった。
息子が店にやってきたので、昭代は聞いた。「お父さんの後を継いでくれるのは嬉しいけど、本当にいいの?水商売なのよ」
息子は言った。「どんな仕事であれ、僕はお父さんとお母さんの仕事を継ぎたいんだ」
昭代は言葉が無かった。
昭代は灯を消し、暖簾を外して、店の中に入れた。そして店の中に入れた背丈の大きくなったスナップエンドウを見つめた。スナップエンドウは暗がりの中で話しかけてきた。
「昭代さん、頑張られましたね。お店の外で私はいつも昭代さんの声を聞いていました。
私たちは冬に芽を出し、寒さに耐えながら少しづつ大きくなり、3月には花を咲かせ、沢山の実をつけていきます。私はスナップエンドウです。一番上の兄はグリーンピース、次の兄はきぬさやです。私はちょうど両方の特徴を持った新しい品種としてアメリカで開発されました。でもなかなか日の目を見ることがありませんでした。
私にも長い冬の時代がありました。これからは息子さんと一緒にお店に立つんですね。どうか息子さんが一人前の居酒屋のご主人になるまで、昭代さん・・・、身体に気をつけて息子さんと一緒に新しい店づくりをしてくださいな。居酒屋はひとりぽっちの人が多いこの時代、そんな皆さんのための暖かい、なくてはならない居場所なのですから。」
屋上菜園物語(5)こころの再起
仙台発の夜行バスが上野に着いた。一組の夫婦が人目を避けるようにして上野公園の中に消えていった。公衆便所の中で健二も美津子も用を済ませ、顔を洗った。昨晩は着の身着のまま仙台から夜行バスに乗って夜逃げしてきた倒産者夫婦だ。健二は1冊の本をボストンバックの中に入れていた。「倒産者を救う会」の野崎会長が書いた本だ。会の事務所が上野駅近くにある。事務所が開く迄時間がある。二人はぼんやり朝空を流れる雲を見ていた。
健二が言う。「どうしてこんなことになっちゃったんだろう・・・。もうだめだ」
美津子はそれには答えずここ2週間のことを思い出していた。
3週間前、健二の会社は債権者集会を開いた。厳しい質問が相次いだ。しかし、健二はまともに答えられなかった。代わりに弁護士が今後のこと、弁済率について説明した。その後暴力団関係者から毎日のように電話があった。
健二が社長になったのは突然だった。兄が社長で弟の健二は専務だったが、兄が突然脳出血で倒れ、昏睡状態が2日続いた後、亡くなった。
同族会社ということもあり、専務の健二が急遽兄の後を継いだ。会社は食料品卸で規模は小さかったが、経営は順調だった。長年の得意先にも恵まれ、健二は「会社経営は現状維持」を最優先で考えていた。そこに降って湧いたような不渡り事件が起きた。兄が商品相場に手を出し、会社の経理部に無断で、独断で手形を発行していたのだ。商品相場の大幅な下落で大損を被った。その損を埋めるためにまた手形を発行し、その結果現在の会社の力では手形が決済できず、不渡りという事態になった。倒産だ。
会社の社員は、本業は順調で、利益も出ているので、不渡り、倒産と聞かされた時は全員呆気に取られていた。一番呆気にとられていたのは社長の健二だった。不渡りの金額が大きかったのでどこからも助け船は出なかった。
健二は兄に裏切られた思い、倒産後のもろもろの処理、暴力団関係者の脅しで憔悴していた。発作的に手首を包丁で切って死のうとした。痛みで呻いている健二に気付いた美津子が風呂場に駆け込んできて、救急車で病院に運ばれた。健二はうわごとのように「死にたい、死なせてほしい」と言っていた。そんなこともあり、「倒産者を救う会」の野崎会長に会いに行きましょう、と言って夫を連れてきたのは美津子だった。夫は「会ってもどうにもならない」と乗り気ではなかったが。
野崎会長はにこやかな笑顔で二人を迎えてくれた。美津子の話を暫くじっと聞いた後で、「まだ朝食を食べていないんじゃありませんか」と言って、会長は2人を近くの食堂に連れていった。普通の定食だったが、昨日の朝から何も食べていなかったので、二人は黙って食べ続けていた。食べ終わってから美津子が言った。「ご飯がこんなに美味しいなんて」
朝食後会長から「ここ暫くは東京で落ち着いた静かな生活をしたらどうですか」ということで、住む場所と当面の仕事について話があった。住む場所は会長の友人が近くにマンションをもっているが古い建物なのでいずれ取り壊す予定にしている。空き部屋があるので、そこで暮らしたらどうか、ということだった。仕事の方は、健二は飲食店の皿洗い、美津子はビジネスホテルの清掃の仕事を紹介された。
2週間後の朝、健二がマンションの屋上に初めて上がってみるとオーナーの鈴木さんが屋上菜園で野菜の手入れをしていた。
「おはようございます。何をしているのですか」
「小松菜の間引きをしています。・・・元気になられましたか」
「ありがとうございます。御蔭様で」
菜園の一部が塔屋の日陰になっているが、そこに植わっている野菜がある。
「この野菜は何ですか」
「ルッコラです。ゴマの味がする野菜というかハーブですよ。日陰でも育つけど、若干苦味が強くなりますね」
健二と美津子にとっては慣れない仕事だったが、余計なことを考えずに一日を終えることができるというのが何よりの救いだった。身体を使うので疲れるがその分ぐっすり眠れる。健二が仕事を終えて夜遅く帰ってきて美津子と夕食を共にする時、美津子は必ず缶ビールを1本、健二の前に置いた。
「今日もお疲れ様」
健二の仕事柄、朝は時間があったので、鈴木さんの屋上菜園を手伝うようになった。屋上に木枠が置いてあり、その中に土が入っている。土の深さは15cmくらい、フカフカしている。
「こんな薄い土でよく野菜ができますね」
「屋上での野菜づくりを指導しているある団体のサポートを受けていろいろな野菜にチャレンジしているんですよ。ジャガイモもサツマイモも大根だってできる」
「すごいですね」
「大北さん。私が野菜を栽培していて一番うれしいのは土に播いた種が一斉に芽を出す時なんだ。いじらしいというか健気というか、なんとも言えない」
健二は今迄野菜を栽培したことなどなかった。野菜を栽培するようになってから、美味しい野菜を食べるだけでなく、いのちの力、野菜の一途な生き方に少しづつこころが惹かれていった。
あれから2年、倒産した会社の経済的・法的処理も野崎会長が紹介してくれた弁護士、公認会計士の力を借りて完了した。健二は自己破産の手続きをとった。東京での生活は平凡だが、軌道に乗りつつあった。健二は、現在旅行会社の営業マンとして、主に高齢者向けの旅行企画の販売で頑張っている。美津子は健康食品の会社で経理を担当している。今は鈴木さんのマンション近くのアパートを借りて2人は住んでいる。
ある晩、夕食の時、健二は美津子に言った。
「自分からこんなことを言うのは気が引けるけど、平凡だけどやっと幸せになれたと思う。
美津子には心配、苦労の掛け通しだったけど、今は本当にそう思う。だけど心の片隅で会社が倒産してあれだけ多くの人たちに迷惑をかけたから、自分たちは幸せになってはいけないんじゃないか、という後ろめたい気持ちもあるんだ」
美津子はそれに答えて、
「あなたの気持ちはよくわかります。私も今は幸せという気持ちです。私たち2人の間でそう思っていればいいんじゃないしら。私が今一番うれしいのはあなたが、『もうだめだ』と言わなくなったことよ」
「確かにそうだね。屋上菜園の野菜たちを見ているうちになぜか自分も頑張らなくちゃ、メソメソウジウジしていられない、という気持ちになれたんだ」
翌朝、健二は久しぶりに鈴木さんのマンションの屋上菜園に行った。小松菜が元気だ。
健二は小松菜に声を掛けた。「元気だね」
小松菜も健二に声を掛けた「大北さんも元気そうですね」
健二はある時鈴木さんから小松菜について話を聞いたことがある。鈴木さんはこう話してくれた。
「私は小松菜が好きなんです。平凡な野菜かもしれませんが、栄養価が高く、できるだけ毎日食べるようにしています。そして私が、小松菜が好きなもう一つの理由ですが、小松菜はほぼ一年中栽培して、収穫することができる。私も小松菜のように平凡な人間だが、繰り返し繰り返し、少しでも人様のお役に立てるような生き方をしたい」
健二は小松菜に伝えた。
「私も小松菜さんのように生きていきたいと思うようになりました」
屋上菜園物語(6)幸せづくり
明彦はアルバイトの仕事の後、カフェに立ち寄り、窓際の席に座った。自分の心の中で渦巻いている感情を落ち着かせたかったのだ。虚しさに対する苛立ちだったのかもしれない。
自分でも説明できない、初めて経験する感情だった。運ばれてきたアメリカンを飲みながら、ぼんやりと店の前を通りすぎる人々を見ていた。苛立ちは収まらない。
その時、窓を叩く者がいた。びっくりして見ると友人の野口だった。野口は店の中に入ってきて、明彦の前に立った。
「安田君、久しぶり。こんなところで会えるとは思わなかったよ。座ってもいいかな」
野口は明るい声でそう言った。
明彦は「どうぞ」と答えた。
明彦と野口は定年退職後、あるNPOの活動で出会った。都市と地方の交流を促進する活動をしている団体だった。ウマがあったのだろう、二人は一緒に活動することが多かった。しかし明彦は月1回山梨県の奥迄泊りがけでいくのが段々難しくなり、事情を説明して途中から身を引いた。
「安田君は今何をしているの?」
明彦は近況をかいつまんで話した。今2つの会社で顧問のような仕事をしている、それぞれ週1回の出勤で、残りの日は自分なりに小さな会社を起したいと思っているのでその準備をしている、できれば生涯現役で仕事を続けていきたい、などなど。
野口は黙って話を聞いていた。そして明彦が話し終わった後、
「やっぱりこれからは自分が納得できる、打ち込める仕事がしたいね。人生の最終章を飾る価値ある仕事ということかな。小さくていい、自分が生きた証になるような仕事だ。自分もそれを探している」
明彦は野口の顔を見た。微笑んでいる。
「安田君、今自分は屋上で野菜を育てる仕事をしている。一度気分転換を兼ねて見にこないか。その時は連絡してほしい」そう言ってメモを残して店を出て行った。
明彦はその後もぼんやりと窓の外の風景を眺めていた。、店の中の他の客にはどう見えていただろうか。明彦が何か思い詰めているように見えたかもしれない。
安田明彦は大学卒業後、ある中堅商事会社に入社した。
最初に配属されたのは総務部広報課だった。そこで3年間仕事をした後、貿易部に異動になった。鉄鋼製品の輸出が主な業務だった。海外出張もあった。しかし仕事上の失敗が原因でうつ病になり、会社を半年間休職した。半年後仕事に復帰した時、配属されたのは会社が保有している倉庫の入出庫管理をする資材管理課だった。以前の仕事とは全く違い、戸惑うことが多かったが、やっと慣れた頃にまた異動となった。今度は子会社で、親会社では扱わないような小規模な商談の担当となった。明彦にもそれなりのプライドもあり、また挽回したいという気持ちもあったが、今回の子会社への異動で覚悟を決めざるを得なかった。妻の利絵は元気になればもう一度本社の営業部で活躍できるかもしれないという淡い期待を持っていたようだが、子会社への異動を伝えた時、ありありと落胆の色を見せた。それでも気を取り直して「私も働くわ」と言った後、
「お父さん。これからも身体に気をつけて頑張ってください。いよいよお父さんにとって正念場になるわ。マンションのローンもまだ残っているし」
明彦はこの正念場という言葉を聞いて目が覚めたような気がした。今まで俺は何のために仕事をしてきたのか。自問自答を繰り返した。その結果辿り着いた結論は「これからは事に仕える」ということだった。今迄は出世競争に加わりたいために、人の目を気にし、また自分には到底無理な目標をたてて自分を駆り立ててきた。その挙句うつ病になってしまった。これからは余計なことは考えずに、自分なりに納得できる良い仕事をしよう。自己意識の固まりのようなプライドも捨てよう。
そのように思い定めた夜、明彦は行きつけの飯田橋の居酒屋で独りで痛飲した。帰宅したのは真夜中だった。利絵は寝ずに明彦の帰宅を待っていた。
子会社で明彦はどんな商談にも喜んで取り組んだ。お客様の話をしっかり、深く聞くので仕事の成約率は高かった。しかしそれだけ時間をかけることになるので、成約件数は余り伸びなかった。ノルマは達成していたが、もっと売上げを伸ばしたい子会社の社長は満足せず、明彦にプレッシャーをかけてきた。「効率とスピードだよ」子会社の社長は実績を上げて親会社復帰を目指していた。
40歳後半になっていたので役職は課長代理だったが、明彦には部下はいなかった。そういえば自分には育てるべき直属の部下は与えられなかった。
3年後親会社でリストラが始まった。業績の悪化を人員整理で乗り切ろうというわけだ。当然子会社にもリストラの波が押し寄せてきた。明彦も肩を叩かれた。抵抗はできなかった。自分のサラリーマン人生とは一体何だったのか。
最後の出社日、子会社の社長から「長い間お疲れ様でした。またいつかどこかで会うかもしれませんが、お元気で」と声を掛けられた。子会社の社長もリストラされるという話を聞いた。
明彦は子会社時代に親しくなった2社の社長から声をかけられた。どちらも小さな会社だ。
社長からは「相談相手になっていただきたい」ということで週1回の出社で毎月5万円の顧問料だった。マンションのローンは既に返済しているが、まだ年金の受給開始年齢まで10年以上あるので、合計10万円では苦しかった。妻の梨絵はパートに出ていたが、年間収入は100万円ほどだった。したくはなかったが足りない時は退職金に手をつけることもあった。
明彦、梨絵の夫婦には子供がいなかった。
明彦はこのままでは終われない、人生の最終段階で自分が納得できる仕事を起こそうと考えていたが、自分が本当に打ち込める仕事はなかなか見つからなかった。セールスレップなど新しい仕事もやってみたが、長続きしなかった。ある時自分が小さな筏に乗って暗い海を漂流し続けているような気分になったことがある。
そんな時、カフェで偶然野口にあった。というより野口が自分を見つけてくれた。明彦は野口から渡されたメモを見た。
1週間後、明彦は足立区の商業ビルの屋上にいた。野口は屋上菜園の様子を丁寧に説明してくれた。明彦は初めて屋上菜園というものを見た。野口が屋上菜園の他の区画で野菜の手入れをしている間、明彦はピーマンの区画にいた。緑の実がいくつもついている。そして花もたくさん咲いている。太陽の光を受けてピーマンの実は輝いていた。野口が寄ってきて言う。「ピーマンもよくできる。土の深さは15cmなんだ。この土なら根も十分呼吸できるから茎葉も元気に生長し、実もたくさんとれる」
野口が去った後も明彦はピーマンの区画にとどまっていた。何か声が聞こえたような気がしたからだ。明彦はピーマンの木に耳を寄せた。
「安田さん。初めまして。今日初めて屋上菜園に来られて、私たちのところで足をとめてくださりありがとうございます。私たちピーマンは初夏から冬近く迄花を咲かせ実をつけます。夏野菜の中ではナスさんと同じように息の長い野菜なんです。安田さんと同じように初夏から真夏迄の暑い時期と空気が冷たくなってくる秋の時期と環境の変化に対応しながら花を咲かせ実をつけていきます。もっとも秋には花も少なくなり、出来る実も小さ目ですが、頑張っていますよ。」
明彦は思わずピーマンに聞いた。
「なぜ私のことを知っているんですか」
「野口さんが先日あなたのことを私たちに話してくれたんです。安田さん、これからの仕事は人々を幸せにすることです。私たちは太陽の光を受け「幸せ」という気持ちになり花を咲かせます。安田さんも是非「幸せの花」を咲かせてください。安田さんの今迄のサラリーマン人生は順風満帆ではなかったでしょうが、だからこそ幸せの姿がきっと見えるはずです。そして幸せはつくることができます。安田さんの今迄の人生経験を糧にしてこれからは幸せづくりに励んでください。」
ピーマンは暖かい風にゆっくりと揺れている。
屋上菜園物語(7)微笑み
今日は屋上でイベントが開催されている。初夏の暖かい日差しの中、緑の芝生の上で遊んだり、シートを拡げて食事をしている家族もいる。屋上の一部が菜園になっていて、今日は野菜の苗の定植イベントが開催されている。整理券を持った地元の人たちが順番に並び、屋上菜園に、屋上菜園の栽培スタッフに手伝ってもらいながら、野菜の苗をそれぞれの場所に植え付けて、土を寄せていく。用意された野菜の苗はミニトマト、ナス、キュウリ、ピーマン、シシトウ。家族で植える時は子供が主役だ。毎日の生活で土に触れる機会の少ない子供たちは、ちょっと興奮気味。植え終わった後、「ぼくがこのトマトを植えたんだよ。」誇らしそうに言う。「これからどんどん大きくなるから時々見にこようね」と母親。
そこに車椅子に女の子を乗せた夫婦がやってきた。車椅子の女の子は7,8歳ぐらいだろうか。車椅子に座っているというより寝ている状態だ。
母親が車椅子を押している父親に声をかけた。
「野菜の苗を植え付けるイベントをやってる。ホラ、あそこで。できたら千恵ちゃんにもさせてあげたいわ。」
家族は菜園の区画のところまで来た。父親の紀夫は屋上菜園の栽培スタッフに声をかけた。「うちの子にもトマトの苗の植え付けをさせてもらえませんか」
栽培スタッフは車椅子の家族を見て、「いいですよ。まだトマト、ナス、シシトウの苗がありますから、お嬢さんも定植できますよ」
紀夫が娘の両足を持ち、栽培スタッフのYさんが肩の後に両手を入れて、菜園の横の芝生の上に千恵さんを置いた。それからYさんは千恵さんの右手にミニトマトの苗を握らせ、掘った穴の中に手を沿えて誘導、千恵さんはミニトマトの苗を植えた。それを見ていた紀夫は「ナスの定植は私が手伝います」と言って、千恵さんにナスの苗を定植させた。シシトウは紀夫とYさんが一緒に手伝って植え付けた。その間、千恵さんは全く表情を変えず、言葉も口にしなかった。お人形さんのようだった。
母親のゆかりが千恵さんに声を掛けた。
「千恵ちゃん。お野菜の苗を植えたのよ。良かったね。また来ようね」そう言った後、Yさんに「ありがとうございました。来月また来ます。よろしくお願いします」。頭を下げた。車椅子の家族はブドウ園の方に向かっていった。
鈴木夫妻に子供が与えられたのは10年前だった。結婚して5年が経っていた。ところが生まれてきた赤ちゃんに異常が見つかった。1年経っても、2年経っても声も出さず、表情もなく、まるでお人形さんのような状態だった。娘は難病に侵されていた。それでもお乳を飲むことはできた。ゆかりは千恵の難病は自分のせいだと思い、自分を責め、塞ぎこむ日々を送っていた。紀夫は前途を悲観し、一家心中を考えた。
心配したゆかりの友人が度々、鈴木家を訪れ、ゆかりに寄り添っていた。その友人も障害を抱えた子供の母親だった。子供は「お母さんのせいでぼくはこんなになったんだ」繰り返し母親を責めたそうだ。母親は「ごめんね、ごめんね」と謝るしかなかった。そんな日々を送っているうちにある時、<人は生かされている>ということに気付かされたと友人は話してくれた。
紀夫が一家心中のことを持ち出した時、ゆかりは言った。「この子は私に授かった子です。私はこの子と生きていきます」
紀夫はゆかりの覚悟を知って、一家心中を思い留まった。
ゆかりはいつも千恵と一緒にいた。そしてつきっきりですべての世話をしていた。
紀夫は食品機械を販売する商社で営業を担当していた。優秀な営業マンだったが、家庭の事情もあるので、接待の機会はなるべく減らしてもらって、定時過ぎには帰宅するようにしていた。
千恵さんは5歳になっても変わらなかった。身体は少しづつ大きくなってきたが、食事は流動食に限られていた。顔の表情の変化はなく、言葉も発しなかった。
紀夫は自分に言い聞かせた。<今日一日だけを生きよう 先のことは考えない 今日のことだけを考える。今、ここを大切にして、心を込めて一日を生きていく>。そしてこうも思った。<私たち、この子がいなかったら別れていたかもしれない>
梅雨に入る前、6月下旬の土曜日、鈴木家の皆さんが屋上菜園に来た。鈴木さんご夫妻はまっすぐ千恵さんが定植した区画に向かった。
ゆかりが千恵さんに嬉しそうに声を掛けた。
「千恵ちゃんが植えたミニトマト、実がついているわよ。良かったね~。それからナスもシシトウにも花が咲いて、実ができている」
栽培スタッフのYさんが笑顔で近づいてきて、「どうぞ収穫してください」と言って、紀夫にハサミを渡した。紀夫は丁寧に収穫して、千恵ちゃんの掌に乗せ、握らせた。
「千恵ちゃんのミニトマトだよ。ナスとシシトウは次にしようね」
車椅子の千恵さんを菜園の傍に置いて、紀夫とゆかりが栽培スタッフのところに来た。「お世話してくださり、ありがとうございます。屋上のこんな薄い土でも野菜が出来るんですね。びっくりするやらうれしいやらです」
栽培スタッフのYさんが説明している。
「屋上はとにかく陽あたり良いので、野菜づくりには最高の自然環境です。それにこの高さまで飛んでくる害虫も少ないので、無農薬で野菜を栽培することができます。難しかったのは土の量です。何しろ建物の屋上なので、沢山の土は乗せられません・・・」
菜園の傍に一人でいる千恵さんの顔に微かだが、笑みが浮かんでいる。千恵さんは心の中で野菜たちと言葉を交わしていた。それは人間が使う言葉ではなく、言葉を超えたいのちの対話のようだった。
千恵さん「野菜の皆さん。私は千恵です。今日皆さんのところに来れてとても幸せです。私の心はこれからミツバチになって皆さんのところに飛んでいきますよ。」
野菜たち「千恵さん。私たち植物はこの地球にずっとずっと昔に生まれ、生き続けてきました。私たちには最近地上に生まれた人間には分からないコミュニケーションの方法があります。いのちのコミュニケーションです。千恵さんは特別な人です。なぜなら千恵さんは私たちとコミュニケーションができるのですから」
千恵さんは真っ青な空から目を移し、菜園の野菜の方に微かに首を動かした。
「今日はお野菜さんたちとコミュニケーションができてとてもうれしかったです。また来ますね」
鈴木さんご夫妻はYさんと話をしていた。「また来月きますので、よろしくお願いします」挨拶して、千恵さんのところに戻ってきた。
ゆかりが千恵さんに語り掛ける。「9月にはブドウも採れるんだって。すごいね~」
車椅子を押して菜園からエレベータホールに行こうした時、紀夫は少し右に傾いている千恵さんの頭を元に戻しながら、千恵さんの顔に微かな笑みが浮かんでいることに気がついた。「ママ、千恵ちゃんが微笑んでいるみたい」
「アラ、ホント。千恵ちゃんの笑った顔、初めてみた。今日は最高にいい日になったわ」
屋上菜園物語(8)夜空に流れる歌声
東海道新幹線新大阪駅の近く、10階建てのマンションの屋上から歌声が流れてくる。ファド歌手、月森夕湖が歌っている。ポルトガルの民族歌謡のファド、「サウダーデの風」。・・・夕べの鐘が 潮風に乗り 通りすがりの 旅人の胸に よぎっていく 亡き友の顔 ああ サウダーデ 君をしのぶよ 悲しみの涙を 喜びに変えて 人は祈り 人は生きる ああ サウダーデ 君を思うよ」
このマンションの屋上は柔らかな芝生で緑化されている。ブドウ、オリーブの果樹も植わっている。晩夏の夕方の風が屋上を気持ちよく吹き抜けていく。今夕は月森夕湖のライブだ。30名ほどの聴衆が芝生の上に座って夕湖の歌に耳を傾けている。夕湖は歌と歌の間で短く歌詞にまつわる物語を語った。全部で10曲歌い終わった後、夕湖は最後にあいさつをした。
「私は千葉県のいすみ市というところに住んでいます。家は竹林の多い里山の中にあります。私はファドに私の人生をささげてきました。ファドを愛しています。これからの人生、ファドを唄い続けていきたいと思っています。
私の家の前には畑がありますので、ちょっとおかしい言葉かもしれませんが、「半農半歌」の生活をしています。半分農作業、あとの半分は歌手活動です。農作業を通じて私は自然と交流し、またその土地で亡くなった人々の魂と対話しています。ですから私の歌声はそこから出てくるのではないかと思っています。民謡はその土地の霊、地霊が一緒に歌っているのかもしれません。
私が最初にそのことに気がついたのは若い時、自分のこれからの生き方を考えたくて、一人、ハンガリーに旅行した時です。小さなレストランでジプシー音楽に出会いました。ジプシーが歌った「キッシュ・ラーニュ」(小さな娘)という歌ですが、私の歌の原点になりました。そしてブダペストの食堂ではよくボルシチを食べました。ロシア料理ですね。ボルシチはビーツ、パプリカ、馬肉が入った煮込みスープです。私はビーツが大好きで自分の畑でも栽培しています。今日これから開かれる夕食会のために私の畑からビーツを持ってきました。
それからポルトガル料理。
私はファドの歌手になりたくてリスボンに行きました。小さなホテルに泊まって、毎日のようにファドが歌われているレストランに通いました。そして最後はポルトガル語をきちんと学びたいと思ってリスボン大学の聴講生になりました。若いからできたんですね。大学の傍に小さなレストランがあって、そこでポルトガルの代表的な野菜スープ、カルド・ヴェルデをよく食べました。ということで、私の畑からジャガイモも持ってきました。山下さんご夫妻にお願いして、これから開かれる夕食会にはボルシチとカルド・ヴェルデを出して頂く予定です。
お話が長くなりごめんなさい。
今夕は皆さん、ファドに耳を傾けてくださり、ありがとうございました。ポルトガルギターを弾いてくださった松雪さん、ありがとうございました。そして今日この会場に呼んでくださり、多くの方に声をかけてくださった、ビルオーナーの山下さんご夫妻にこころからお礼を申し上げます。また機会がありましたら是非お呼びください。
月森夕湖は屋上の出入口のところに立って聴衆の一人一人に声をかけながら、握手をしていた。
ライブの後は夕食会がビルの1階にあるカフェで開催される。月森夕湖は山下さんご夫妻と一緒のテーブルについた。ある若い女性が月森のところに来た。
若い女性「月森さん、今日は本当に素晴らしい歌を聞かせてくださり、ありがとうございました。その中で特に私のこころに迫ってきたのは「感謝の歌」でした。“あなたが私にくださったもの 不安、心配(少しのやさしさもあったかしら)”。私、最近離婚しました。
いろいろな思いがありますが、「感謝の歌」の最後、「でもね。私の愛する人よ 決して皮肉ではないわ 心からありがとう あなたが下さったすべてにありがとう」を聞いて救われたような気持ちになりました。」
月森はじっと聞いていた。そして言った。「そう言って頂くとうれしいわ。私も60歳になりました。今迄の人生、愛する人との出会いと別れが私にもありました。若い時に出会った愛する人、そして中年になってから出会った愛する人。その時は傷つけられたり、傷つけたりして別れたけど、今では私も「あなたが下さったすべてにありがとう」という気持ちよ。」
若い女性「月森さんは、すべてにありがとう、という気持ちになれたんですね。どうしたらそうなれるんでしょうか」
月森は若い女性を励ますように女性の手を握って言った。「過去を振り返ってはいけないの」
若い女性は答えた。「私もそのようにしています。未来を見ています。今度こそ幸せになりたい。過去を忘れ、前だけ向いて生きていこう、と」
月森は答えた。「私が過去を振り返ってはいけない、というのは過去を部分的に思い出すということじゃなくて、過去全体に向き合う、ということなの。過去と向き合うというのは勇気がいるわ。過去は失敗ではないの。いろいろな経験を通して成長したあなたがいるわ。人は傷つきながら成長していくものよ」
若い女性は涙を浮かべ、今度は自分から手を出して月森の手を握った。
若い女性の次に並んでいたのは白髪の男性だった。
男性「私は「私の中のファド」が心に沁みました。私は今年で75歳になりました。いつ死んでもおかしくない年齢です。最近は今日が私の人生最後の日という気持ちで一日一日を過ごしています。夜寝るときは「今晩寝ている時の身体と魂をお守りください。そして明日の朝を元気に迎えられますように」って祈るんです。寝ている間に向こうの世界に行くのは避けたいですから。やはりこの世で家族に最後の感謝の言葉を伝えて旅立ちたいものです。私の中にもいつのまにか棲みついている心の歌があります、ちょっと秘密ですが、いつも口ずさんでいますよ」
月森は答える。「ご自分の中に心の歌を持っている人は幸せです。歌は私たちを、人生の深みに連れていってくれます。そして私は最近思うんですけれども、私が歌う時、目の前にいる生きている人も、既に亡くなった私の親しい人も一緒に聞いていてくれるような気がしています。歌は生きている人と亡くなった人をつなぐ何か特別のものかもしれませんね。生き物の中で歌を歌うのは人間だけじゃないかしら」
男性の後は中年の女性だった。10人ほどの列ができている。
夕食会の準備ができた。最初はワインで乾杯。マスカットベリーAの赤ワイン。各テーブルの上に小さなバーベキューセットが置かれ、肉、野菜が焼かれる。野菜のほとんどはこのビルの屋上で収穫されたものだ。玉ねぎ、ピーマン、ニンジン、パプリカそしてビーツ。
そしてボルシチもカルド・ヴェルデも運ばれてきた。楽しい夕食会だった。山下さんご夫妻が夕湖と一緒にテーブルを回り、歓談の花を咲かせた。
夕食会は10時迄続いた。
ホテルに戻ってきた月森夕湖は着替えをする前に持ちかえったワインを飲みながら今日一日のことを振り返り、習慣にしている日記を書いていた。頬杖をつき、ちょっとぼんやりした時、ハンドバックに一つ残しておいた小さなビーツが話しかけてきた。
「夕湖さん。今日のライブは良かったですね。夕湖さんが祈るような気持ちで歌っているのが伝わってきました。夕湖さんと私は40年近くの付き合いになるんですね。ところで私は夕湖さんがいろいろな病気を抱えながら、半農半歌の生き方をしていることを知っています。私は「食べる輸血」を言われるように栄養豊富な野菜です。収穫して私を皆さんに差し上げるのはいいのですが、夕湖さんご自身ももっと私を食べてくださいね。私は「奇跡の野菜」とも言われています。夕湖さんのために是非奇跡を起こしたいと思っているんですよ。一日でも長く元気でいて、多くの人に生きる力を、幸せをプレゼントしてください。私からのお願いです。」
屋上菜園物語(9)楽農オジサン
オジサンの草間岳生は埼玉県のN市に住んでいる。定年退職してから2年が経っていた。「いよいよ自由になった。これからはやりたいことをやる」とゴルフ、旅行そして読書に明け暮れる日々を送っていた。まさに定年三昧。ゴルフは週2回、会員になっている近くの河川敷のゴルフ場に行き、プレーを楽しんだ。スコアが少しづつ上がっていくのが楽しみになっていた。
「もうすぐコンスタントに80台が出せる」。旅行は奥さんと一緒にイタリア、ポルトガル、フランスに行った。読書は古典と言われる本を主に読んだ。会社勤めをしている時はビジネス関係の本が多かったが今ではそれも卒業だ。しかしそのような日々は長く続かなかった。
今年3月、奥さんが病気で突然亡くなった。病院で最後を看取った時、奥さんは「お父さんに出会えて、一緒に人生を歩めて良かった。幸せな人生だったわ」と最後に言った。その言葉はその後の岳生の人生の支えとなったが、毎日の生活の淋しさは募るばかりだった。
マンションの窓を開けて、奥さんの名前を夜空に向かって小さく叫んだことが何度あったことか。ゴルフも旅行も読書も楽しめなくなった。岳生は改めて奥さんあっての退職後の生活だったと思わずにはいられなかった。
岳生はホテル会社に勤めていた。40歳を過ぎたころから海外にホテルを出店する業務に携わっていた。日本国内でもある程度知名度のあるホテルだったので、海外からの出店依頼も多かった。そんな訳で日本を長期間空けることがしばしばだった。自宅に帰るのは年間で半分という年もあった。留守宅を奥さんは守ってくれたが、どんな気持ちでいたのだろう。浮気の心配もしていたのではないだろうか。
岳生はショッピングセンターの中に入っているカフェでぼんやりしている。歩いている人々を見るともなしに見ている。段々夕暮れが近づいてきた。マンションの家に帰っても誰もいない。岳生には子供が一人いるが、現在は奥さんと一緒に海外に駐在している。
岳生は暗くなる迄椅子に座っていた。急に夜景が見たくなってショッピングセンターの最上階に上がった。見下ろす町に電灯が灯り始めていた。夜景を見ているうちに岳生は涙を流している自分に気がついた。
ショッピングセンターの地下の食品売り場で今晩のおかずを買った。牛丼風にして一杯やろうということで、牛肉、春雨、豆腐、ホウレンソウを買った。家に帰り、キッチンでフライパンを出し、熱したフライパンにサラダオイルを入れて、ホウレンソウを炒め、頃合いを見て春雨、豆腐を加え、最後に薄切りの牛肉をフライパンに入れた。上から薄口醤油をかけ、ワインを垂らした。暫く蓋をして蒸らしてから食堂に持ってきた。炊飯器のごはんを茶碗によそって、これで完成。「良子、これから夕飯だ」奥さんに声を掛けて岳生は箸をフライパンに入れた。
その晩岳生に電話がかかってきた。ときどき会ってお茶を飲む友人の尾崎だ。尾崎は友達思いの男で時々電話をしてくる。ゴルフ仲間の中で波長があったのだろう、肩の力を抜いて付き合える。
「近い内に神田で一杯やらないか。ちょっと面白い話もある」尾崎は思わせぶりな言葉を加えて電話を切った。
翌日岳生は尾崎に会った。神田駅西口を出て西口商店街を歩き、外堀通りを渡ってすぐのところにあるビルだ。ビルの前で尾崎は待っていた。尾崎の案内でその事務所ビルの屋上に上がると、びっくりすることに屋上菜園が広がっていた。箱状の菜園の中に野菜の苗が植えられている。
尾崎が説明する。「ここに植えてある苗はミニトマト、壁側に植えてあるのはキュウリ。
あそこの区画には小玉スイカの苗が植えてある。葉物、実物、根物全部の野菜ができるんだ。屋上で野菜をつくる団体からアドバイザーが月2回来てくれる。いつもは自分達が野菜の世話をしているんだ。」
岳生が聞く。「世話をしているのはどういう人たちなんだい」
尾崎は嬉しそうに答える。「『楽農オジサン一杯やる会』っていうんだ。全部で5人いる。」
屋上菜園で皆で作業をした後、下の居酒屋で一杯やるんだ。居酒屋の店長もメンバーの一人でさ、「今日はこの野菜を使いましょう」なんて言って店に持って帰って酒の肴にしてくれる」
岳生は尋ねる。「オレみたいなもんでも入れるのかな」
尾崎が言う。「実はルールみたいなものが2つある。一つは会社で何をやっていたか、どんな役職についていたかは話さない、聞かない。もう一つはお互い気がついたことはどんどんほめ合う。この2つだ。知っての通り、日本は会社でも家庭でも「ダメ出し」文化だ。
だから一杯やる会は「ダメ出し」ではなく「ほめ出し」で行く。皆元気になるし、お互いの関係も良くなる」
岳生が聞く。「オレみたいな野菜づくりをしたことのないものでもグループに入れるの。
できたら是非入りたい」
尾崎「一度メンバーに紹介しよう。ちょうど今日の午後3時から屋上で農作業がある。
始まる前に皆さんにキミを紹介するよ。その後の一杯にも出たらどうかな。一次会は大体6時頃には終わる」
それから1週間後、屋上菜園で仲間と一緒に作業をしている岳生の姿があった。岳生は毎週2回、月曜日と木曜日に神田迄出てきて屋上で農作業をして、その後居酒屋で仲間と談笑するようになった。生活にリズムが生まれてきた。ある時農作業の後、居酒屋に降りていくと尾崎からこんな話があった。
「エヘン。さて皆さんは日本のオジサンです。日本のオジサンは世界一孤独、という本が出ているくらい孤独で、寂しい存在です。理由はコミュニケーション能力の決定的不足ですね。そこで今日は孤独から抜け出すために2つに絞ってコミュニケ―ション体操をします。いいですか。まず笑顔の練習。目の前の割りばしを咥えて口角を上げて笑ってみてください。顔全体で笑うというのがポイントです。
次は人の話を聞く体操です。自分が話したい気持ちを抑えて、相手の話を聞く。あくまでも相手が主役です。相手に最大限の関心を持って話を聞く。そして区切りごとに相槌を打ってください。場合によっては相手の言葉を繰り返すといいと思います。そうしますと相手は自分の言葉をちゃんと受けとめて理解してくれているんだと安心しますから。それでは今日は6人の参加者ですから2人づつペアを組んでやってみましょう。」
岳生は尾崎とペアを組んでコミュニケーション体操をやった。
岳生は孤独感からはまだ完全には解放されなかった。解放されることは恐らく一生ないだろうと思うが、最近は孤独感には自分自身の問題も大きく影響していることに気が付き始めた。毎日鏡を見ながら笑顔の練習をしているとなぜか明るい気持ちになってくる。
外食をした時、カフェのママに「コーヒーが香ばしくていい味でした」とお礼の言葉を伝えた時、ママの笑顔になんとも言えない美しさが浮かんだ。褒める、感謝するということがいつの間にかできるようになった。
ある時、尾崎がビルの一室の工房のようなところに連れていってくれた。そこではオジサンたちが工具を使いながら、椅子、テーブル、物置、木製プランター、グリーンカーテン用木枠などを作っていた。屋上菜園で今後使うアウトドアファーニチャーとのことだった。
木製品の加工を指導してくれる先生が定期的に山梨の甲府市から来てくれる。
岳生は尾崎と神田の街を歩きながら、「『楽農オジサン一杯やる会』が神田にドンドン増えるといいな、そのためにも楽しく頑張ろう」との尾崎の言葉に力強く頷いた。頑張っているのは俺たちだけじゃない、屋上の野菜たちも頑張っている。
そして呟いた「本当に孤独を感じるからこそ親密なつながりをつくることができる。私が元気溌剌に生きていくことが家内の最後の言葉に応えることになる。」
岳生は顔を上げ、ビルの屋上に声をかけた。
「屋上菜園さん、ありがとう」
屋上菜園物語(10)野菜嫌いな夫
健康診断で夫に大腸がんが見つかった。幸いステージ2だったので、早速手術をした。それでもこれから5年間毎年2回の診断をしなければならなくなった。富子はこれをキッカケに夫に野菜を食べてもらおうと心に決めた。結婚した時分かったのだが、夫は野菜をあまり食べなかった。夫は「俺は野菜は嫌いなんだ。どうもあの青臭いのが苦手だ」と言って、いろいろ工夫して調理したけれども食べてくれなかった。
しかし、大腸がんになった今度は、何がなんでも食べてもらい、再発を防がなければならない。そして夫には元気で長生きしてほしい。最近テレビでも健康番組が増えている。腸の健康のためには野菜が効果的というのはよく知られている。
富子は区が主催している高齢者向けのプログラムの一つ、有機野菜栽培講習会に参加することにした。希望者が多かったが幸い抽選に当たり、講習会に参加するようになった。
4月から始まり、翌年の2月迄の約1年間の講習会。菜園は区の建物の屋上に作られていた。
1メートル弱の四角い、木枠で作られた箱状の中に土が入っている。教えてくれるのは2人の講師。一人は元農業高校の教員、もう一人は屋上菜園栽培歴10年の専門家。講習会の参加者は全部で25名。箱状の菜園は全部で5つあった。一つの菜園を5人で使うということだった。毎月2回講習会が開催された。
富子は自分のマンションのベランダで野菜を栽培するために講師の紹介で木製のプランターを2つ購入した。また有機野菜の培養土併せて購入して、自宅で野菜づくりを始めた。
最初に栽培を始めたのは小松菜と春ホウレンソウだった。少しづつでいいので毎日夫に野菜を食べてもらいたいというのが富子の気持ちだったのだ。
夫の正治は最初はいつまで続くかな、と思っていたようだが、野菜を世話している富子のまるで我が子を見守るかの様子を見て、ギクリとしたことを覚えている。いつか富子が言ったことがあった。あの子が生きていたら今頃どうしているかしら。
富子は夫の正治と話していると息がつまりそうな気持になることがしばしばあった。富子が何か言うと、それはこういうことだと自分の理解、考えを話すのが常だった。富子は思った。ここは会社ではないの、今夫婦で話をしているんでしょ。私は夫にアドバイス、結論を求めているんじゃないの。「そうだね」「それで?」と興味を持って聞いてほしいの。私はお父さんが好きだけど、理屈っぽいお父さんは好きじゃないわ。嫌いよ。
富子は毎朝、毎夕木製プランターの前にしゃがんで野菜の世話をしていた。ある時野菜と話している声が聞こえてきた。「元気に育つのよ。お母さんがいつもそばにいるんだから。
講習会の先生も会う度に元気に育っていますか、何か心配なことがあったらいつでも連絡してください、と言ってくださるし」
正治は朝食の時、味噌汁に小さな野菜が入っているのに気がついた。可愛い双葉の間引き菜だった。正治は間引き菜を口に入れた。微かに甘い味がした。正治は富子を見た。富子は黙って笑っていた。
暫くは小松菜、春ホウレンソウの間引き菜の味噌汁が続いた。正治は喜んで食べた。それは元気になってほしいという富子の気持ち、そのために富子自身が自分のために野菜を育てて食べさせてくれていることへの感謝の思いが正治の中に湧いてきていたからだ。
正治と富子は結婚して既に40年間になっていた。夫婦の会話の中に、私がいなくなったら、ぼくが死んだら・・・という話題が時々出るようになっている。二人の考えは今住んでいる家をシェアハウスにしていこうという点では一致している。家族の歴史が刻まれているこの家をどちらかが生きているかぎり、守っていこう。
正治は富子と結婚して以来、富子にずっと苦労を掛け通してきたという思いに立ち戻る時がある。正治自身、人生で経験した2つの大きな試練が自分にとってどのような意味があったのか、考え込むことが最近多くなった。そればかりではなく、あの時は自分のことで精一杯で富子がどんな気持ちでいるのかまでは気が回らなかった。
富子はいつも自分の側にいてくれたが、私の混乱に巻き込まれないように適度の距離をとってくれていた。今になってみるとそれが分かる。その時は冷たいと思ったこともあったが、家族を守るためにも賢明な態度だったのだ。
自分の人生をまとめる時期に来ている。自分は一体何を求めてこの人生を歩んできたのか、求めてきたものが見つかったという達成感はまだ持てないでいる。このまま終わってしまうのか。正治にある時、これからの残りの人生を富子の幸せのためにささげていきたいとの思いが与えられた。
今の自分にできることは富子が育ててくれている野菜を喜んで食べることだ。富子は「この野菜はお店で買う野菜と違って有機栽培しているお野菜なの。農薬も化学肥料も使っていない、お野菜の自然な味がするわ。そして私の愛情のこもったお野菜」最後は笑い声になった。
正治はまだ富子には言ってないが、野菜の効果を確認していた。それは「快便」だ。トイレに入ってすぐに便が出るようになった。スッと一本出る。ということでトイレにいる時間が2,3分間になった。快便は快眠につながる。快便、快食、快眠とは昔の人は良くいったものだ。
富子は食事の時に野菜栽培の話をしてくれる。ある時は講習会の講師が「野菜と対話をしてください。現代は情報発信、受信が盛んにおこなわれていますが、本当の意味での対話が少なくなってきています。人との対話、自然との対話を大切にしてください」と言ったことを話題にして、私たちも対話をしましょう。対話よ」と釘を刺した。
正治は定年退職後知り合い、うまのあう仲間と3ケ月に1回旅行をするようになっていた。
今回は新潟県上越市に二泊三日で来ている。仲間の一人がワインに詳しい。上越市には日本のワインの父と言われる川上善兵衛氏のブドウ園がある。そこを訪問して夜は旅館に泊まり、3人でゆっくりといろいろな話をしようというわけだ。着いた晩は12時すぎまで語り明かした。
翌朝、正治は6時頃目を覚ました。2人はまだ寝ている。絵葉書を取り出して正治は富子宛に書いた。
「今、上越市にいます。昨日は美味しいマスカットベリーAのワインを飲みました。このように平凡でも穏やかな日々を過ごせているのは、富子さん、あなたの御蔭です。あなたと結婚してから、自分のことをいつも先に考える自己中心的生き方、何かを求めているのに、求めているものが分からないため、あっちにぶつかり、こっちにぶつかりの無駄の多い人生行路に付き合わせてしまいました。よく我慢してくれたと思います。こんなぼくを見放さないでいてくれたことに感謝しています。
これからは富子さんを幸せにすることを第一に考えます。今迄二人の結婚生活には辛いこと、悲しいことがありましたね。それを乗り越えてこれたのは富子さんが側にいてくれたからです。私のような弱い人間は一人でいたら倒れていたことでしょう。
これからは一日一日を大切にして幸せな毎日にしていきましょう。今迄本当にありがとう!
旅行から帰ってきた日から暫く経った時、ベランダに見慣れない野菜が2本、木製プランターに植わっていた。聞いてみるとえごまとのこと。1本は葉取りの種類、葉を取って食べることができる。もう一本は種用とのことだ。えごまは、特に油は認知症の予防に効果があるとされている。古くから日本で食用にされてきた国産オイルだ。一番大きな特徴は動脈硬化や心筋梗塞、脳卒中などの生活習慣病の予防効果だ。
正治は富子に聞いた。「えごまを選んだ理由は何なの?」
富子の返事。「アルツハイマー病にならないためよ。お互いのことがわかなくなったら悲しいでしょ。」
正治と富子は毎朝ヨーグルトと一緒にえごま油を摂っている。一日4グラムでいい。だから100円もかからない。これで生活習慣病が予防できればありがたい。えごま油は島根県川本町産だ。
富子はえごまに話しかけている。「私たち夫婦にとってこれからがとても大事なの。うれしいことも苦しいことも二人で経験し、分かち合っていきたいの。えごまパワーを私たちにくださいね。お願いします」
屋上菜園物語(11の1) 見直そう、人生を
風祭明彦はたった一人の息子を16歳の時、交通事故で喪っている。自分とは真反対の快活で、ユーモアに富んだ少年だった。少年から青年になりかかる年齢で突然天国に召された。あれからもう26年になる。明彦は現在73歳、自分では80歳までは生きたいと思うが、こればかりは神のみぞ知る、だ。
御巣鷹山に衝突して多くの犠牲者を出した日航ジャンボ事故が発生したのは1985年。あれから33年経った。家族を突然失った遺族が毎年慰霊の登山をする姿をテレビで見て明彦も悲しみ、辛さを新たにする。他人事ではない。
明彦は生涯で二度大きな喪失体験をしている。一つは息子の死。もう一つは経営していた会社を失ったことだ。この2つの大きな喪失体験が明彦を暗い世界に引きずり込んだ。自分が生きているのか死んでいるのか分からないような現実感覚の喪失状態に数年間苦しんでいた。明るく、冷静でしかも気丈な妻が傍にいてくれたので持ちこたえることができた。(今では妻には戦友のような友情を感じている。)
そんな時たまたま明彦の住んでいるS市が市民農園の募集をしたので、応募したところ当たった。幅3m x 長さ5mの区画で早速夏野菜の栽培を始めた。何分初めてやる農作業なので、簡単に栽培できるもの、ということで、ミニトマト、ピーマン、シシトウ、モロヘイヤの苗を植え付けた。家から自転車で10分ぐらいのところに市民農園はあった。週に2回ほど自転車を漕いで、菜園に通った。始めた頃は野菜を育てて収穫するということより、畑で作業しているといつの間にか無心になれる、というのがありがたかった。野菜は日毎に生長していく。明彦はその時、生命の力というものを野菜に見たような気がした。それが明彦の野菜栽培との長い付き合いの始まりだった。
*
明彦は親友の柿本と久しぶりに会った。JR恵比寿駅の近くのビルの6階が飲食店街になっていて、そこにカフェもある。二人ともアイスコーヒーを頼んだ後、明彦が言った。「まずお互い近況報告から始めないか」「そうだね、どっちから?それではボクからしよう」
柿本「ボクは今年で75歳になった。キミも知っての通り、自分は親父が始めた会社を傾かせてしまった。それから必死に立て直しのために頑張ってきたが、この歳だ。いつどうなるか分からない。それで息子に会社を任せることにした。個人商店みたいな会社だから、最初は息子も嫌がっていたが、何とか継ぐということで納得した。一度は会社を整理しようと思ったんだ。しかし、お客さんから止めないでほしいとメールが入ってきた。こんな会社でもそんな風に言ってくださるお客様がいる。自分がやってきた仕事の意味を改めて考えさせられた」
風祭「そうか。でも良かったじゃないか。息子さんにバトンタッチできて」
柿本「そうなんだけど、暫くは後に立って見守ることにしている。できれば1年間で見守りも終わりにしたい。まだまだ気は抜けない。でも息子が継いでくれることになったので、心配と同時に、正直嬉しさもある。・・・ボクの方の近況報告は以上だけど、今度はキミの近況を聞かせてほしいな」
風祭「最近ボクの方は仕事というより人生というものを考えているんだ。自分の人生とは一体何だったんだろうか。そしてこれからの人生をどう生きていったらいいのか。というのは言葉で言うのは難しいんだが、最近は空虚感に苛まれている。それと同時に現実遊離感のような感じもあるんだ。そういう年頃なんだろうか。高齢者になる、というのは初めての経験なので少々戸惑っている。こんなの初めてだ。」
柿本「見た感じは元気そうだが、そうなんだ。そういえば空虚感というのは自分にもあるし、分かるような気がするけど、現実遊離感というのはどんな感じなんだい」
風祭「現実との距離が以前に比べて広がったような感じなんだ。もっと言えば以前は自分は現実の中にいた。今は現実の外で現実を見ているような感じなんだ。まるで観客のように。」
柿本「空虚感は辛いが、現実遊離感も辛い、という感じがするの?」
風祭「辛いという感情はあまり無いけど、自分はなぜここにいるのか、という違和感に似た感情はいつもこみあげてくるね。そしていつこの世から消えてもいいような・・・」
柿本はゆっくりアイスコーヒーを飲んだ後、「違和感かぁ」と言った。「そう言えば自分もどこかで、微妙に自分の人生にずっと違和感のようなものを感じてきたのかもしれない。」
柿本のそんな表情を見ていた明彦がちょっと笑いながら、「いきなり深刻な話になって悪かった。ただ今の自分の感じていることを聞いてほしくて言ったんだ。キミだったら聞いてくれると思ってね」
柿本「大丈夫だよ。これからは時々こんな話もいいね。何をしているかだけでなく、今どんな気持ちでいるかも話そうよ。今迄はそんな話はあまりしてこなかったけど、これからは必要だね」
風祭「そう言ってもらうとうれしいね。実は今ボクは高齢者向けの精神的コーチング、ということを考えている。簡単に言うと、高齢者が自分の人生を互いに語り合って、自分の人生と向き合い、見直し、受け入れていく、という人生見直しプロジェクトなんだ。今から人生をやり直すことは難しいけど、見直すことだったらできる。そして自分のように空虚感、現実遊離感に悩み始めている高齢者が出てきているんじゃないかと思っている」
柿本「さすが風祭さんだね。転んでもただでは起きない。他に近況報告は?」
風祭「最近ハーモニカと水彩絵の具を買った。自分が子供の頃を思い出してね。散歩がてら家の近くを流れる川の土手に行って、ハーモニカを吹いたり、風景画を描いている」
柿本「いいね、ちょっと絵になるな。ハーモニカか。そういえばボクらが子供の頃はハーモニカが流行ったよね。親父がハーモニカは肺に良くないと言って続けさせてくれなかった。
肺門リンパ腺で肺に影があったんだ。ハーモニカと言えば、ボクが中学生の頃だったか、長島愛生園の青い鳥楽団の演奏会に行ったことがある。ライ病で手が不自由で視力を失った人たちがハーモニカで演奏していたっけ。すごく感動したことを覚えている。人間てすごいなと思うと同時に、想像を絶する努力をされたんだなと思った」
風祭「長島愛生園の青い鳥楽団の演奏会のことはボクも知っていたけど、残念ながら実際に聞いたことはなかったね。川の土手で夕焼け空に向かってハーモニカを吹いているといろんなことを思う。自分の73歳迄の人生、そして戦後73年経った日本の辿ってきた道とか。吹ける曲はまだ少ないので、少しづつ練習をしてレパートリーを増やそうと思っている。絵の方は我流だけど、描いているうちに無心になれるのがいい。吹いてくる風を感じながら描いている」
屋上菜園物語(11の2) 見直そう、人生を
そう言ってから明彦は高齢者向けの精神的コーチングの構想を図解したシートを柿本に渡した。「こんなふうに考えているんだ。次回会った時、柿本さんの感想、アドバイスを聞かせてほしい」
柿本は暫くシートを見てから「分かった。ボクも一歩間違えると世界一孤独なオジサンになるね。ところで屋上菜園の仕事は最近どんな感じ?」
明彦「最近老人ホームから屋上に菜園を作ってほしい、という話が来ている。今後老人ホーム向けの仕事が増えてくるんじゃないかと思っている」
柿本「風祭くんの今迄の苦労と努力が報われるといいね。そういう時代になってきているのかもしれない。ところで近い内にどこかキミの関係している屋上菜園を見学させてくれないか。」
風祭「了解。それでは神田の屋上菜園がいいかな」
「少し散歩しないか」柿本が誘った。二人は駅のコンコースを出て駅前広場を抜け、街路を歩き始めた。「若い人が多いね」明彦。「そうなんだ。それでいて隠れ家的な店もある。「次はそんなところで一杯やろう。聞いてほしいこともある」と柿本。「了解」と明彦。
*
ある晴れた日、明彦と柿本は神田のビルの屋上菜園に上がって行った。ドアを開けると屋上菜園。
柿本「へぇ~。こんな風になっているんだ。トマトもナスも元気に育っているね。小玉スイカも出来ている」
風祭「屋上菜園はちょっと箱庭風に見えるかもしれないね。それでもこの90cm角の木枠でできた菜園なら3畝つくることができる。太陽に向かって背丈の低い順に野菜を栽培するんだ。建物に重量的に負担を掛けないように土の深さと重さを制限している。」
柿本「土の深さはどれくらい?」
風祭「約15cm。それも軽いフカフカの土を使っている。果樹の場合は土の深さを30cmにしている。やはり15cmじゃ無理だ。」
各区画の野菜の様子を見ながら、ブドウのところに来た。
柿本「ブドウもやっているんだ。なんていう種類のブドウ?」
風祭「マスカットベリーAっていうんだ。日本で作出された生食もワインもOKのブドウで有機栽培に適している品種だね。最近気が付いたんだけど、欧米、中近東ではブドウは殆どワイン用。だから生食用の場合に必要とされる「房づくり」という作業が無いようなんだ。
房づくりは手間がかかる。でもワイン用のようにそのまままとめて収穫するんじゃなくて、一つ一つのブドウの房を大切に手入れしていく。大きい房、中ぐらいの房、そして小さな房。ぼくらの場合は商品として販売する訳ではないので、全部の房の手入れをして、完熟になった時に皆で収穫する。ブドウ狩りだ。ブドウは野菜栽培に比べてずっと手間がかかるけど、それだけ収穫の喜びは大きい」
柿本「なんか人生を感じさせるね。栽培者は一つ一つのブドウの房を大事に育てる、だね」
柿本は屋上菜園から辺りの風景に目を移した。大手町と比べて神田はまだ高層ビルが少ない。中小のビルが立ちならんでいる。ブドウの木に柿本は声を掛けた。「今度来るときには収穫して完熟の味を楽しませてもらうよ」
ブドウは答えた。「天候にもよりますが、今年は猛暑に日々が多かったので、例年に比べて2週間ほど完熟の時期が早まるのではないかと感じています。私たちを味わう時、この時のために、皆さんに喜んで頂くために、風祭さんたちが1年間私たちを世話してくださったことを頭のどこか片隅でいいので、イメージしながら食べてください。」
柿本は風祭の傍に来て、こう言った。先日の高齢者向け精神的コーチングのシートをじっくり読ませてもらった。それで思ったんだけど、キミが言っていた現実遊離感は狭い現実認識からもっと広い現実認識に転換させるために、天の大いなる存在がキミに与えた一種の試練じゃないかと。われわれはビジネス中心の狭い現実感覚の中でずっと長いこと生きてきた。この現実感覚こそ大事だと思って頑張ってきた。しかし、今は仕事だけじゃなくて、日常生活の中で、そして自然との関係の中で、人としての本来の全体的現実感覚を取り戻す機会が今与えられている、そんな風に考えたらどうか、と思った。・・・そしてこれからは深い関係性が大事だと思う。ブドウの木は自然と人間との深い関係性の中で実を結ぶ。人間もそれを見習う時に来ているんじゃないかと思うよ」
明彦は黙って柿本の言葉を受けとめた後、ちょっと呻くように言った。「これからボクの新しい生き甲斐が始まるのかもしれないね。」
ブドウの葉と房を、流れてきた微風が揺らしている。
屋上菜園物語(12)野菜の花言葉
西谷桃子は毎朝4階の部屋の引き戸を開け、屋上ガーデンに出る。ガーデンの約半分が菜園になっている。桃子は朝一番で菜園に入り、野菜達に声をかける。「おはよう!今日も一日元気でいてね」。一通り野菜の様子を見てから、部屋に戻り、朝のコーヒーを淹れる。
コンクリート製の4階の建物の2階、3階は賃貸で貸し出している。それが桃子夫婦の毎月の生活費の半分ほどを賄っていた。1階は夫の事務所と桃子の花屋だ。5年前、桃子は夫と一緒にこの家を建てた。土地は既にあったので必要なのは建築費だけだったが、それでも8000万円ほどかかった。夫婦で4階に住み、一緒に屋上菜園を楽しんでいる。今では夫婦の会話の大半は野菜づくりに関することだ。子供のいない夫婦にとって共通の話題があるというのは大きい。
桃子は若い頃、一時有名になったガングロ族として原宿の街で遊んだことがあった。父は中小企業の経営者で仕事中心の日々、家庭のことは殆ど顧みることがなかった。桃子は一人っ子だった。そして桃子が20歳の時、短大を卒業した年、母は乳がんで亡くなった。それがキッカケになり桃子は髪を金髪に染め、顔、腕を黒く塗った。今迄の自分とまったく違う人間になりたかった。家にもあまり寄り付かなかったが、父親はそんな桃子を自由にさせていた。桃子は遊ぶお金が無くなると家に戻り、父親にお金を無心した。父はその都度、まとまったお金をくれたが、「身体だけは気をつけるんだよ」と必ず言ったものだ。
ガングロ生活に飽きたころ、桃子の友人のK子が山梨県の牧丘町で夫と一緒に有機農業をやっているので、遊びに来ないかと誘いがあった。桃子は農業の経験もなく、農業にそれほど関心はなかったが、地方での自然に近い生活にはなんとなくあこがれていた。田舎生活が経済的にも、それから近所付き合いも含めてそれほど容易ではないことをそれとなく知っていたが、折角の誘いでもあり、泊りがけで行くことにした。
当日友人のK子が塩山の駅に車で迎えに来てくれた。塩山から北に向かい、牧丘町に入り、千曲川の支流の鼓川沿いに上がっていったところにK子の家があった。平らなところが少ない土地でK子の家は緩やかな斜面を土盛りして整地したところに立っていた。昔風の民家で、2階では以前は蚕を育てていたとのことだった。
K子はこころづくしの夕食を準備してくれていた。ご主人と3人で囲む夕食。
K子「田舎だからたいしたものはないけど、今日の料理の野菜は全部私たちが育てたの」
桃子「美味しい。なんか久しぶりにちゃんとした食事をしているって感じ」
K子の夫はここに来る迄は東京の世田谷の方で豆を中心としたレストランをやっていたが、豆料理で使ういろいろな豆をどうしても自分で育てたい、という気持ちになってここに移住してきたこと、そして古民家に手を入れて豆のカフェ・レストランを開店したいきさつを詳しく話してくれた。「若いからできたことなんだと思うわ」とK子はちょっと夫を睨む。
K子の夫「大自然が自分の心身を癒してくれるんです。仕事の合間に店の外に出て、風に吹かれているといつの間にか幸せな気持ちになれます。生命に溢れた風です。それから夜空一杯の星。最初、星空を見た時は星だらけで、それはそれは仰け反るほどびっくりしました」
桃子は素朴な雰囲気の夫婦と話をしながら、ご主人が作った豆料理を楽しんだ。
桃子「K子、なんかうらやましい生活をしているね。よく田舎の生活は経済的にきびしいって聞くけど生活の方は大丈夫なの?」
K子「大丈夫よ。夫はお店の方で忙しくしているの。SNSの時代でしょ。こんな山奥のカフェ・レストランに結構お客様が来てくださるの。その口コミで新しいお客様がわざわざ来てくださるので、本当にありがたいわ。私は牧丘町の地域起し協力隊として活動しているの。牧丘町の行政や民間事業者、地域住民とやりとりをしながら都会からの移住者の受け入れ体制を整える仕事をしているわ。ブログを使って全国に牧丘町の魅力を発信しています。地域起し協力隊には年間100万円以上が支払われるからとても助かっている。ただこの協力隊の任期は3年間だけだから、4年後には豆カフェ・レストランを軌道に乗せていないと。」
久しぶりで話は尽きなかったが明日の起床が5時と聞いていたので、お風呂に入ってすぐに床についた。お風呂は太陽光で沸かしていた。トイレは洋式トイレ。午後10時が就寝時刻で、朝は5時から活動開始とのこと。以前の自分は夜通し起きて遊んでいた。何をしていたんだろう。
翌朝、5時過ぎに起きて2階の寝室の窓を開けたら濃い霧がかかっていて何も見えなかった。暫くすると霧が流れ視界が晴れてきた。田んぼの向こうに花々が咲いているのが見えた。靴を履いて引き寄せられるように外に出て花が咲いているところまで行ってみた。
桃子は花の種類はあまり知らなかったが思わず口をついて出た言葉は「野のゆり」だった。子供の頃、母に連れられて近くの教会学校に通ったことがあった。本当に山百合が咲いていた。
その姿を見て桃子は思わず立ちすくんだ。
K子の家には二泊三日した。仰け反るほどの星空も見た。家の周りは野原だった。いろいろな花が咲いている。その時、桃子は思った。「私も野の百合のように咲きたい」
桃子は牧丘町から戻ってきてから、完全にガングロ生活を止めてお花屋さんになるための専門学校に通うようになった。フラワーアレンジメント科で一年間のコースに入った。そのころ神田のちよだプラットフォームの屋上で野菜づくりが始まり、ある団体の主催で「ちよだベジカフェ教室」が開催された。そこで4月から9月迄の半年間、月2回ちよだプラットフォームの屋上に通いつづけ、有機野菜づくりの基本を習うことができた。講習会の前半45分間は屋上で実習、後半45分間は1階のカフェで座学という形。肩の凝らない楽しい講習会だった。講師の先生は2人で年配の男性とアシスタントの若い女性だった。
1年が経った頃、桃子の叔母から手紙が来て、今マレーシアのキャメランハイランドの近くで仕事をしているが忙しくなってきている。良かったら手伝いに来てくれないかとの誘いだった。叔母はキャメランハイランドの山間部でイチゴの栽培と生け花用の花の栽培をやっていると手紙に書かれていた。写真も数枚同封されていた。
桃子は思い立ったら実行するタイプだ。叔母さんのことはよく知っている。亡き母の妹でマレーシアの日本人学校の教師として赴任後、現地のインド人と結婚したと聞いていた。
父親に桃子はマレーシア行きを伝えた。父親は「あの叔母さんのところにいくなら大丈夫だろう。ところで何年ぐらいいるつもりなんだ」と聞いたが、桃子は「行ってみないと分からない」と答えた。父親は寂しそうな表情を浮かべていた。
5月の五月晴れの日、桃子はマレーシア航空で成田を出発、約7時間後にクアラルンプール国際空港に到着した。叔母さんは出口のところで待っていた。すぐに国内航空に乗り換えてキャメランハイランド近くのイポーに向かった。叔母さんの家は丘陵地帯の高いところにあった。別荘のような建物だった。
その晩早速インド人のご主人も交え3人で夕食をとった。ご主人の名前はダト・グーンティン。ダトはマレーシアでは社会的功績のあった人に与えられる称号とのことで、グーンティンさんはマレーシアの公共事業省に勤務し、特に農村部の灌漑工事に長く携わってきた技術者だった。5年前役所を辞めて、現在はイチゴ栽培と花の栽培事業を行っていると話してくれた。叔母さんは「マレーシアではマレー人優先政策がとられていて政府のそれぞれの部門のトップにはマレー人がなるのよ。インド人、中国人はトップになれない仕組みになっているの」
夕食はマレー風のカレーだった。ご主人も叔母さんもスプーンを使わないで、右手を使って食べていた。
夕食後桃子がこれから住む部屋に叔母さんが案内してくれた。床が板張りの大きな窓のついた2階の部屋だった。トイレとシャワーはついていたがバスルームはなかった。
叔母さんは言った。「桃子ちゃんにはここにいる間、私がやっているお花の栽培を手伝ってほしいの。農薬を使わないオーガニックフラワーをハウスの中で栽培しているわ。主なお客様はキャメランハイランドに住んでいるヨーロッパ人とペナンにあるオーガニックを売り物にしているホテルなの」
桃子は専門学校で学んだことを実地に活かせる機会と考えていたが、実際に生きた花々に接するうちに花の魅力に取りつかれていった。半年経った頃、叔母さんが言った。「桃子ちゃんはお花が本当に好きなのね。これからは桃子ちゃんにお花の栽培を任せていきたいわ。」
そのような時、日本から電話が叔母さんのところに掛かってきた。父の弟からだった。
「兄さんが急病で倒れた。医者によればここ1週間の生命とのことで、兄さんは桃子に会いたがっている。一時帰国させてほしい」
桃子はその日の晩の夜行便で日本に戻った。父の入院している病院に翌朝空港から直行した。
「お父さん、桃子よ」
父親はうっすら目を開けて、桃子に言った。
「桃子、すまなかった、ほんとうにすまなかった」
言い終えた後、息を引き取った。
桃子は父の葬式に出た後、すぐにマレーシアに戻った。
それから2年半、桃子は無我夢中で働いた。
3年後、叔母さんが言った。「桃子ちゃん、長いことありがとう。桃子ちゃんと一緒にお花の仕事ができて本当に幸せだった。それで最近叔母ちゃんは思ったの。桃子ちゃんは日本に帰ってお花屋さんをやったらいいんじゃないかしら、って。実は最近桃子ちゃんのお母さん、夢に出てきて、そういうの。桃子ちゃんと別れるのは寂しいけど、それが桃子ちゃんにとって一番いいことだと思うわ」
マレーシアから帰国後、桃子は1年間池袋のデパートの中にある花屋に勤めた。そこで販売の基本を身に付けた後、池袋に近い商店街でお花屋を開店した。開店費用は父の遺産を使わせてもらった。
お花のお客様にカフェがあった。そのビルのオーナーが経営しているカフェで、そこのオーナーに気にいってもらえた。
ある日、オーナーから話があった。「私の息子があなたのことをとても気にいっているの。できたら一度会ってくれないかしら」
ちょっと坊ちゃん的だけど優しそうだ。それが桃子の印象だった。半年間付き合った後で結婚することになった。結婚のためお互い健康診断をした時、男性の方に初期のガンが見つかった。男性はこんなボクと結婚しなくてもいいんだよ、と伝えたが、桃子ははっきりと言った。「あなたと結婚します」
夫はガンの後遺症で車椅子生活だが、以前からやってきた行政書士の仕事を続けている。
1階の半分は夫の事務所で、残り半分が桃子のお花屋のお店だ。桃子は今迄のお花の仕事の他に老人ホームの屋上菜園で、野菜を栽培し、ハーブ、季節の花を育てる仕事もしている。
花には花言葉がある。野菜にも色とりどりの花が咲く。桃子は野菜の花言葉集を作っている。「ダイコンは風になる銀の鈴のよう 花言葉は 喜びの中の悲しみ」
桃子の心の中には「野の百合」がいつも咲いている。
屋上菜園の野菜達が夕陽に染まってきた。
屋上菜園物語 第13話 ゆっくり野菜
水田隆志が老人ホームで暮らすようになってから半年が過ぎた。入居者20名の小さな老人ホームだ。毎日のスケジュールが決まっているので、規則正しい生活は送れるが、自由にできることは限られている。テレビで好きな番組を見たり、趣味で色紙に好きな言葉を筆で書いたりしているがそれでも時間を持て余す。そして最近しばしば「このまま生きていても何の意味があるのだろうか」という思いがさざ波のように繰り返し襲ってくる。特に辛いのは真夜中に目が覚めた時だ。部屋には自分独り。
手元に置いてあるラジオでNHKのラジオ深夜便を聞く。今晩は昭和40年代前半の歌謡曲を放送している。隆志は若い時、ムード歌謡が好きで、ロスプリモスの「たそがれの銀座」(昭和43年)、ロスインディオスの「コモエスタ赤坂」(昭和43年)を聞きながらまだ行ったことのない別世界、銀座、赤坂に想いを馳せたものだ。ムード歌謡のグループの中で特に好きだったのが鶴岡雅義と東京ロマンチカだ。「小樽の人よ」(昭和43年)。
聞いているうちになんとも物狂おしい気持ちになってきた。懐かしさと淋しさと取返しのつかない辛さと悔いが一緒になって心の底から湧き上がってくる。昭和という時代が懐かしさと暗さの顔を見せながら手招きしているようでもある。
隆志は天井を見上げ、そこからこの自分を見下ろしているかもしれないもう一人の自分を見据えた。そして言葉を投げつけた。「あんたはこの俺のことをどう思っているんだ」。答えはない。
眠れないまま、隆志はあの日のことを思い出していた。その時の様子がスローモーション映像のように蘇ってくる。いつものように朝の散歩をしていた。
アパートの近くにある小さな丘に上がり、道を降りてくる途中、道端に小さな白い花を見つけた。なぜかその花を摘もうとして屈んだ時、身体の重心を崩し、そのまま道端の法面を転がって下まで落ちてしまった。当たり所が悪く、頭を損傷してしまった。脳内出血のため下半身に障害が出てしまった。
歩くのがやや不自由だ。それまでは自分の足でどこへでも行くことができた。不自由な自分をなかなか受け入れることが出来なかった。できればこのまま死んでしまいたい・・・何度そう思ったことか。
隆志は建設労働者だった。正確に言えば農閑期の出稼ぎ労働者だった。少ない田畑だけでは食べて行けなかった。稲を収穫した後、毎年東京に出てきて土木関係の工事会社で働いていた。土木の工事会社の社長が同じ村の出身でそのコネでその会社で働くようになった。この工事会社は二次下請けでどんな仕事でもやった。
隆志も若い頃は飯場暮しをした。埼玉県南部の高速道路の建設現場に入った時、その飯場の建物の広さに隆志はびっくりした。窓の傍には布団が積み上げられていた。賄いのおばさんたちが作る夕食を食べた後は焼酎を飲みながら、新聞紙の上に積みあげられたニンニクを齧りながら仕事仲間と今日の作業のこと、明日の段取りなど話し合った。
打ち解けてくると故郷の話も出た。気晴らしに休みの日には現場近くのパチンコ屋で遊んだり、女性のいるスナックにも行った。飯場には落ち着いた普通の生活感というようなものはなかった。荒んだ気持ちになる一歩手前でなんとかこらえているという状態だった。隆志の楽しみはトランジスタラジオだった。イヤホンで毎晩のように歌謡曲と野球中継を聞いていた。
飯場では喧嘩も日常茶飯事だった。現場は一歩間違えると怪我をしかねない。当時はリベットを使う工事も多く、受取りそこなった真っ赤に焼けたリベットが落ちてきて火傷する事故もあった。それどころか鋼材など資材の下敷きになって死ぬこともある。最後は酔い潰れてせんべい布団の上に身を横たえた。朝が早いので飯場の消灯は10時だった。隆志は田舎に残してきた子供たちのことを思いながら眠りにつくのが常だった。
「いろんな現場で仕事をした。辛い思い出が殆どだ、嬉しかった思い出はあまりなかったな・・・。」
そして隆志もいつの間にか60歳を超していた。
事故の後、すぐに田舎から妻と息子がやってきた。暫く病院で治療をした後、リハビリ施設に移り、それから施設に移ることになった。施設は東京の西にある社会福祉法人が運営する身体障碍を持った老人を受け入れている施設で毎月の料金は家族で何とか払えるギリギリの金額だった。息子は田舎の市役所に勤めている。息子は農業を継がなかった。田畑に出るのは土日だけだ。その分妻が頑張っている。
隆志は最近老人ホームの2人とよく話すようになった。なんとなくウマがあう。以前ビル管理会社に勤めていた藤崎雅人と洋品店の店主だった大岩正次。二人とも水田より歳上だ。藤崎と大岩は最近この老人ホームの屋上にできた菜園施設で野菜の手入れをしている。
隆志は今更野菜作りなんてと思い、二人の誘いを断っていたが、「気晴らしで屋上に上がってみたら」と声を掛けられ、他にやることもなかったので、一緒に6階の屋上に上がってみた。上がってみてびっくりしたのは見晴らしのいいことだった。360度グルッと街並みが見える。スカイツリーがぼんやり霞んで彼方に聳えている。
藤崎と大岩の二人が車椅子から降りて何か球根を植え付けている。
「こんな浅い土で根物野菜ができるんですか」と言いながら隆志は2人に近づいて行った時、思わず声をあげた。「チョロギ」ですね。
「そうですよ、良く知っていますね」
「私の田舎でもチョロギを作っていたんです。お節料理で梅酢で赤く漬けたチョロギを黒豆に添えたり、茹でたり、天ぷらにして食べたもんです。イヤー、懐かしいなぁ」
藤崎の田舎でも、大岩の田舎でもチョロギを栽培しているという話になって、一挙に3人の関係は深くなった。チョロギが取り持つ縁だった。
それがキッカケになって3人が一緒にいる時間が長くなった。ある時、3人それぞれ好きな歌謡曲を3つ挙げようという話になった。
藤崎は鶴田浩二の「好きだった」三波春夫の「チャンチキおけさ」春日八郎の「山の吊橋」
大岩は井沢八郎の「ああ上野駅」東海林太郎の「名月赤城山」三笠優子の「夫婦橋」
三人の中で一番若い隆志は、岡林信康の「山谷ブルース」桂銀淑の「すずめの涙」、森進一の「新宿みなと町」
大岩「藤崎さんも私も70歳を超えているせいか、懐かしいけど古い歌だね。でも古い歌にはどこか強い真実さが感じられるんだ。それぞれ最初に挙げた歌について自分なりの思い入れをちょっと話しませんか」
藤崎「いいですね~。じゃあ私が一番バッターで。私は鶴田浩二の「好きだった」を最初に挙げました。若い頃、好きな女性がいました。彼女は自分のことが好きだと言ってくれましたが、私には相手の女性を幸せにする自信がなかった。却って不幸にしてしまうような気がして、彼女に「好きだ」と言うことが出来なかった。結局自分から身を引く形で別れました。本当に自信が無かった。人を愛せる自信、幸せにするための生活力、それが自分の中には一かけらも無い。頭でっかちの空想家だったんです。二番の歌詞を私はまだ心のどこかで引きずっています。「笑うつもりが 笑えずに 顔をそむけた 悲しみを 今も捨てずに いるくせに」。・・・・・・次水田さん、いかがですか」
水田「私の場合は岡林信康の「山谷ブルース」です。山谷に住んでいた訳ではなく工事会社の寮で寝泊まりしていましたが、気分的には歌詞に近いものがありましたね。特に4番はその通りだと思っていました。『人は山谷を 悪くいう だけど俺たち いなくなりゃ ビルも 道路もできゃしねえ だれもわかっちゃ くれねえか』。高度成長期の日本はまさに日本列島改造ということで土建国家日本という感じでした。だけど土建の仕事は結局現場で生身の人間がやるわけですよ。労働条件なんてそんなものは実際なかった。私たちは汗水流した、そしてある意味で私たちの犠牲が無ければ、橋もトンネルも道路も港もできはしなかった。でもそんなことはだれもわかっちゃくれねえ、と岡林は歌っています。本当にそうだと思いましたね。」
大岩「藤埼さん、水田さん、ありがとうございました。私の場合は井沢八郎の「ああ上野駅」です。私の実家は農家で、私は4男でしたので、田畑を継ぐというわけにはいきませんでした。それで中学を出てすぐ東京の横山町の繊維問屋で働くことになりました。休日は月2回しかなくて働き詰めの毎日でした。会社の寮はすぐ近くにあって朝昼夕と食事がでましたが、最低限の定食という感じで、食べ盛りの私はいつもお腹を空かしていたんです。よく上の人から怒られました。寮の屋上に上がって故郷の方に向かって叫びました。田舎に帰るわけにはいかない。「おかあちゃん~、おかあちゃん~」三番の歌詞に「お店の仕事は 辛いけど 胸にゃでっかい 夢がある」とありますが、当時の私には夢なんか無かった。」
大岩がある朝、2人と一緒になった時、嬉しそうにこう言った。今朝野菜の手入れをしていた時、こんな言葉を聞きました。「人生、やり直すことはできませんが、『生き直す』ことはいつからでもできます」そのためにはゆっくり生きることです」。ちょっと弱っていたピーマンの内側の枝(内向枝)を整理している時、ピーマンが語りかけてくれました。」
『太陽の光の当たりにくい内側の枝を切ってくださり、残した枝にもっと光が当たるように枝を拡げてくださりありがとうございました。また追肥もちょうど欲しい時だったので助かります。太陽の光を浴びてもう一度大きな実をつけますよ。楽しみにしていてください。そして大岩さんも藤崎さんも水田さんも是非ゆっくりと毎日を生きてくださいな。人間はどうしても急ぎ過ぎてしまいます。今こそ大事なことは「ゆっくり」です。私たち野菜は焦ったり、急いだりしません。生きるリズムを大切にしながら、ゆっくりと着実に生長していきます。たとえ明日収穫されることになっても今日をゆっくり生きていきます。覚悟を持って。』」
隆志は大岩に聞いた。「私たちのような身体が不自由な者でも『生き直す』ことができるんでしょうか」。大岩は答える。「生き直すために一番大事なことは『意識』です。思いを、考え方、つまり意識を変えれば生き直すことができる。ピーマンはそのように言っていると私は受けとめています」
藤崎は微笑して付け加えた。「私が生き直すために心掛けていることはどんなにささやかでも周囲の人に安らぎを与え、希望をもたらすことです。私がやることですから大したことはできませんが、また失敗もありますが、生き直すことがこれからの人生の目標となりました。別の言葉でいうと『一隅を照らす』ですか」
隆志は故郷の妻と息子に久しぶりにはがきを書いた。
12月にチョロギが収穫できたら送る、そして毎日友にも恵まれ元気に生活している、と。
屋上菜園ではチョロギが茎葉をグングン伸ばしてきた。
屋上菜園物語(14)バトンタッチ
ここは神田のビルの屋上菜園。90cm角の木枠が10セット置かれて、培養土が20cm近く入っている。今日はトマトの横のジャガイモ掘り。黒石美奈子は息子の健太と一緒にジャガイモの周りの土を手で掘り始めた。ジャガイモが1個、2個と出てきた。土寄せは1回しかしていない。最初はあんまりないのかなと美奈子は思ったが、深く掘っていくうちに健太が「下の方にたくさんあるみたいだよ」と声をあげる。二人は力を合わせてジャガイモの茎を引っ張りあげた。12個以上の中ぐらいの大きさのジャガイモが姿を見せた。二人は思わず叫んだ。「ジャガイモがたくさん採れたよ~」
「屋上菜園では露地の畑のようにジャガイモの土寄せを2回すれば本当はいいのですが、そのためには新たに土を購入して追加する必要があります。そうもいかない場合は、1回で済ますために敢えてジャガイモの種芋を深植えします。通常の露地栽培の場合、土の深さ5cmのところに種芋を置きますが、屋上菜園の場合15cmぐらいの深さのところに種芋を置くと1回の土寄せで大丈夫ですよ」と栽培指導のYさんがアドバイスしてくれたのだ。それをやってみた。屋上菜園の場合、土の下は耐根シートが張ってあり、水はけはいい。屋上菜園ならではの裏技のようだ。
他の区画でも親子でジャガイモを掘っている。大体7~8個ぐらいは収穫できている。声を聞いて他の区画の家族が美奈子と健太のジャガイモを見に来た。健太はちょっと誇らしげだった。美奈子は健太のその顔を見て嬉しかったが、健太の視線がいつの間にか種芋に注がれているのに気が付いた。健太は黙って腐りかけた種芋を見ていた。
*
健太は昨年の暮れから落ち込んでいた。家で長いこと飼っていたスピッツ犬のマミーが死んだのだ。マミーは健太になついていた。健太はマミーを可愛がっていた。健太の傍にいつもいたマミーが突然いなくなったのが健太には信じられなかった。その時健太は死というものを実感した。そしていのちあるものは必ず死ぬという恐怖に襲われた。死は自分の大切な存在を突然奪っていく。それに対して自分は何もできないという無力感にも打ちのめされた。
ある晩のこと、家族が寝静まった頃、健太は布団から抜け出てリビングルームに行き片隅で祈り始めた。「かみさま、お母さん、お父さん、それに妹の美智子を死なないように守ってください」。健太はかみさまがどんな方なのか知らなかったが思わずそう祈った。祈らずにはいられなかったのだ。そして自分にできることはかみさまに祈ることだけだった。そんなことが毎晩続いた。ある晩のこと、美奈子は健太が夜中にリビングルームに行くのに気がついた。起き上がり戸の隙間から様子を見ていると、健太が泣き声になって祈っていた。その姿を見た。
「かみさま、お母さん、お父さん、それに妹の美智子が死なないように守ってください」。何度も何度も繰り返していた。美奈子は思わず健太に駆け寄って抱きしめたい衝動に駆られたが、こらえて自分の布団に戻った。暫くして健太が戻ってきて布団の中に入った。
美奈子は布団の中で考えた。「健太はかみさま、と祈っていた。かみさまがどんな方か健太は知らないはずだ。だけどかみさまが私たちにいのちを与えてくださっている方だということは本能的に知っている。健太の祈りが本当の祈りなのかもしれない」
健太は子供心に「死」について考えていたのだろう、元気のない日々が続いていた。そしてポツリと言った。「ぼくも死ぬんだね」
*
健太は生まれつき感受性の強い子供だった。他の子供より深く出来事を受け止めてしまうところがある。道端に咲いている小さな花を見つけそこにしゃがみこむことがよくあった。
「おかあさん、この花見て。きれいだよ。香りもするみたい」
健太は自分の考えが相手に受け入れられるかどうか、いつも気にしていた。美奈子は自分ではそう思っていなかったが、口うるさい母親なのかもしれないと思ったことがある。健太が何か言うと「そうじゃないわ」「それではだめよ」「それはこうするの」と言っている自分がいたことにある時気が付いた。それは健太が悲しそうに「おかあさんはぼくが何を言ってもダメっていうんだね。何を言っても、何をやってもダメなぼくなんか生きていてもしょうがない」と言った時だった。
美奈子は慌てて「健太が失敗して辛い思い、悲しい気持ちにならないようにと思って言っているのよ。健太のことをダメだと思って言っているんじゃないの」
健太はちょっと抗議するような表情をして「だったらおかあさん、おかあさんがぼくに3つ言ううち一つは「健太の言う通りよ、やってみたらいいわ」って言ってほしい。失敗しないと前に進めないとぼく最近気が付いたんだ。いつまでも立ち止まってしまって一歩が踏み出せない」
美奈子が中学生の時、親友のM子ちゃんが飛行機事故で突然死んだ。ショックだった。暫くは学校に通う道に、突然M子ちゃんがひょっこり出てきて「美奈子、おはよう」と言うのではないかと思い、あたりを見回すことが度々あった。暫くはM子ちゃんが死んだことを受けとめきれなかった。
M子ちゃんのお葬式はキリスト教の教会であった。牧師先生は、M子ちゃんは教会に通い、洗礼も受けているので、この地上の人生は終わったけれども、今は天国で神様から永遠のいのちを頂いている、と告別式の説教で話していた。しかし今一つピンとこなかった。
美奈子が疑問に思ったことは、「なぜ神様は中学生のM子を天に召したのか、なぜ人生の途中で、これからという時に地上の人生を突然終わらせたのか」ということだった。考えても分からなかった。それから高校入試のための受験勉強が始まり、死について考えることからいつの間にか遠ざかってしまった。
高校、大学、就職そして結婚。夫とは職場結婚だった。そして2人の子供に恵まれた。
美奈子はこの際子供の健太に死についてキチンと教えないといけないと思っていた。子供が理解でき、そして前向きになれるような教え方はないものか。図書館にも行っていろいろな本にあたってみたが、これはというのは無かった。夫にも相談したが、自分にはそんな難しい話はできない、とうまく逃げられた。
今年の5月、近くのショッピングセンターの屋上菜園でイチゴ収穫とトウモロコシの種まきイベントがあった。先着20名ということだったので、美奈子は健太を連れてイベントに参加することにした。開始は午後2時だったが、屋上に上がってみると既に10人ほどの行列ができていた。並んで整理券をもらい、まだ時間があるので屋上でゆっくりした。ここの屋上はとても広く、芝生が張られている。花壇もあり、木も植わっているので公園みたいな雰囲気だ。屋上の一部が菜園になっている。
午後2時。整理券を持った人たちが屋上菜園の前に集まってきた。屋上菜園で栽培管理をしていて、今日のイベントの進行役の人Aさんが説明を始めた。アシスタントのスタッフが2名、整理券と番号札とを交換している。
「これから皆さんにイチゴを収穫して頂きます。イチゴにそれぞれ番号札をつけていますので、その番号のところに行ってイチゴを収穫してください。イチゴは5月上旬から下旬にかけて収穫していきます。真っ赤になっているのが完熟したイチゴです。」
スタッフに誘導されて参加者はイチゴを収穫していった。若い家族も多く、子供が主役だ。「イチゴってこんな風にできるんだね」と子供の声。
美奈子はイチゴ収穫イベントの後のトウモロコシの種まきイベントを健太と一緒に見ることにした。一定の間隔にあけられた小さな穴にトウモロコシの種が参加者の手で播かれていく。
イベントの後、美奈子と健太は屋上菜園にとどまり、他の野菜が育っている区画を見て回った。そんな様子を見て、屋上菜園で栽培管理をしているAさんが美奈子に声をかけた。
「楽しかったですか?イチゴの数に限りがありますので、そんなにたくさんはとれませんが、収穫の体験をご家族でして頂きたいという思いからこのイベントを企画しました」
美奈子は答えた。「こんな経験はめったにないので子供も喜んでくれたと思います」
突然健太がイチゴの区画を指さしてAさんに聞いた。
「収穫した後、イチゴはどうなるんですか。枯れてしまうんですか?」
Aさんは微笑みながら「坊や、どうしてそういうことが気になるの?」
健太「なぜか気になるんです。死んでしまうんですか?」
Aさん「難しい質問だね。坊やは今イチゴの株から粒を収穫したね。その株を親とすると今年実をつけた親からリードというツルが伸びてきていくつも子株ができるんだ。来年はその子株を育てて子株に実をつけさせるんだ。」
Aさんは菜園のイチゴのリードを見せながら「バトンタッチなんだよ。親から子へ。バトンタッチをちゃんとやっていくと毎年良い実がたくさんつくんだ。坊やの名前、教えてくれる。・・・健太くんだね。健太君、イチゴもその一つなんだけど自然の世界もバトンタッチなんだ。人間の世界もバトンタッチだとオジサンは思っている。人はそれぞれ何かをやりとげて次の人にバトンタッチする。難しいことばだけど人にはその人に使命が与えられているんだ。その人だからこそできる、その人にしかできないことがある。それに取り組むことが人間の場合とても大事なんだ。自分の走る道を走り抜く、オジサンも今そうしている。健太君にもすごい使命が与えられているんだよ。そして健太くんのバトンを待っている人がいる。どうせ死ぬんだったら何をやっても意味がない、なんて思っちゃいけないよ」
Aさんが立ち去った後、美奈子と健太はもう一度イチゴの区画に戻った。
健太がイチゴに声をかけた「イチゴさん、ありがとう。これからも頑張ってね」
イチゴが答えた。「健太さんのこれからの人生は長いです。いつも明るいこころを持ち続けてください」
何かに気付いたのだろう。それから健太は夜更かしはきっぱりやめて早寝早起きになった。
*
美奈子はジャガイモの種芋を見詰めている健太に声をかけた。
美奈子「健太、いまどんな気持ちなの?」
健太「種芋が腐っているみたい。だけど種芋は自分のいのちを使って茎を伸ばし、葉をつけて新しい沢山の芋を生みだしたんだね。ぼく今、種芋さんに『頑張ったね』と心の中で声をかけていたんだよ」
美奈子は健太を思わず抱きしめた。「そうだね、種芋さん、頑張ったね。そしてそう思える健太もえらいわ」。
神田のビルの屋上菜園でも夏野菜の収穫が終わり、秋冬野菜の準備が始まった。土の中から夏野菜の残った細かい根を取り除き、ゴミも拾い出し、きれいにしてから堆肥、元肥を入れ、有機石灰を撒いて、2週間ほど待ってから秋冬野菜の苗の植付け、種まきをする。
秋ジャガイモの種芋も準備した。
秋晴れの下、いよいよ秋冬の野菜栽培が始まる。
屋上菜園物語(15)天空果樹園カフェ
市川純一は自分の小さなカフェを開いた時から将来は銀座の真ん中で、それもデパートの屋上にカフェをつくりたいという夢を持っていた。今その夢が実現しつつある。屋上果樹園・菜園の中にあるカフェ。
純一は5年前パリに行った。伝統ある農業祭を視察するためだった。2月末にパリに入り、3月初め迄滞在した。まだ時折みぞれが降る日もあった。ベルサイユの農業祭には3日続けて通った。夜はホテルの近くの小さなレストランで牡蠣料理をツマミにしてワインを飲んだ。日本の牡蠣に比べ随分身が薄い。このレストランは通路にテーブルを出しているが、頭上にはネットが張ってあり、ブドウの枝葉が拡がっている。街中でブドウの木を見るとやはりパリだと思う。
純一は海外に出ると街中を散歩するという習慣を持っていた。地図を見ながら歩き回る。ブダペスト、ベオグラード、アテネ、リスボン、ロンドンと歩き回った。アテネの憲法制定広場ではオレンジの木がたわわに実をつけていた。純一は日本とヨーロッパの都市を果樹で比較してみたことがある。日本の都市には緑が少ない。ビルばかりだ。パリではマビオン通りまで歩いた。ある時銀座でパリ在住の日本人画家の展覧会に行ったことある。作品の一つに「マビオン通り」というのがあった。純一はその絵になぜか強く心惹かれた。マビオン通りのある場所の地下1階には昔、日本人の製本家が住んでいたと何かで読んだことがある。今は道路から階段を下りていったところに庭があり、その奥にレストランがあった。
Aデパートは以前、夏場はビアガーデンとして屋上を使っていたが、夏場以外の季節は特に何もしていなかった。買い物客が買い物した後に一息つけるようにベンチとテーブルを並べていた。ベンチに座っているのは年配の女性だ。それもチラホラだった。飲み物はベンディングマシーンで買うようになっていた。このデパートの屋上はどこか寂しげな場所、という印象だった。
純一は九段でカフェを経営している。オーガニックカフェ、「シャルダン デザンジュ(天使の庭)」という名前だ。開店してから4年、経営も軌道に乗ってきた。純一は以前期間限定でAデパートの地下レストラン街にカフェを出し、主にスイーツを販売した経緯がある。それ以来デパートの担当者とは時々会って話をすることがある。
前回はデパートからの話でそれに乗った形だったが、今回は自分の方から働きかけてみようと思った。屋上である程度のスペースを確保して小さな果樹園をつくり、その中にカフェを開く。屋上の場合、室内と比べ家賃は安くなる。午前10時から午後5時迄はスイーツカフェ、午後5時から午後8時迄はワインも出す、というのが純一の考えだ。果樹園の周りはモリンガの林で囲む。空気の汚れている都心の真ん中できれいな空気を吸いながら、ゆっくりとしたひと時を過ごす。
以前からこのアイデアを温めてきたが、実現するためには具体的段取りとそれを実現してくれる協力者、パートナーが欠かせない。簡単なプロジェクトではない。その協力者たちと出会い、意気投合する迄にはやはり時間がかかった。
純一は京都府宮津市に生まれた。ところが純一が10歳の時、両親は車で外出中に事故に遭い、死亡してしまった。その後は叔母に引き取られて中学生迄世話になったが、高校に進むかどうか迷っていた時、遊びに行った友人の家でおやつにプリンを頂いた。プリンを食べたのは生まれて初めてだった。こんなに美味しいものがあるなんて、純一は心の中で驚嘆した。その時純一は菓子職人になることを決めた。叔母には高校には進学しないで、東京で菓子職人になると伝え、中学卒業後、東京の菓子工房に職を見つけることができた。
経営者のMさんは純一の境遇を理解してくれた。
「菓子職人になるための修行は厳しいぞ。頑張れるか」
「ハイ、頑張ります」
中卒と言うことで店ではもっぱら小間使いの仕事をやらされた。純一は月に1回しか休みを取らなかった。実際に菓子作りにタッチできるようになったのは3年後だった。純一は菓子工房の寮で生活していた。経営者のMさんには子供がいなかった。そんなこともあってか、純一の成長を暖かく見守ってくれた。
ある時Mさんの自宅に呼ばれて一緒に夕食を食べた。Mさんは優しい眼差しで純一を見ながらこう言った。
「市川くんも18歳になったんだね。18歳と言えばもう大人だ。そこで今日は世間を生き抜いていくために大事なことを教える、いいかな。第一は朝の挨拶を元気良くすること。第二はハイとはっきり返事をすること。第三は後始末をキチンとすること。これを続けて行けば地に足の着いた素晴らしい人生を送ることができる。天国のお父さんお母さんも市川くんがそのような人生を送ることを願っておられるのではないかな」
純一は今でもMさんの言葉を実行している。そして三つのことを教えてくれたMさんへの感謝の気持ちを忘れたことはない。
純一は鋭い味覚と嗅覚を持っていた。そしてちょっとした美的センスも。25歳を超した頃には30種類ほどの菓子の製造責任者に抜擢された。
仕事を終えて寮に帰ってきてからも菓子づくりの研究を続けた。そしていつしか菓子づくりの本場であるフランス、イタリアに行って修行してみたいと思うようになったが、それは叶わぬ夢だった。28歳の頃には100種類以上の菓子の製造責任者となった。毎月新しい菓子の発表会があった。純一は食べ物の世界にオーガニックの波が来ていることを感じていた。それで新しい菓子を10品出す中に必ずオーガニックの材料を使ったものを入れていた。ただ問題だったのはオーガニックの材料を使うとコストが上がり、販売価格が高くなることだった。お店に出しても売れ残ることが多かった。それでも純一はオーガニックの菓子の製造を続ける道を選んだ。その結果Mさんの店をやめて独立することになった。自分の信じる道を歩きたいというのが純一の思いだった。純一はMさんの自宅に呼ばれた。純一はまずMさんに詫びた。
「今迄長いことお世話になっていながら、私のわがままでお店を辞めさせて頂くことになりました。誠に申し訳ありません。」純一は頭を上げることができなかった。
Mさんはやさしく受けとめながら、
「市川くんがいなくなるのはとても寂しい。だけど、自分の道を進みたいという市川くんの気持ちもよく分かる。頑張ってほしい」
純一は将来のことを考えて貯金をしてきた。早速不動産屋に依頼して物件を探したところ何件かあたった後、九段の住宅街の元カフェを紹介された。カフェの厨房設備、お店の椅子、テーブルなど少し手を加えれば居抜きで使える。純一は貯金の全額をこの店に使ったが、内装工事関係のための資金がなく、友人にも手伝ってもらって自分達で内装工事をやった。店の看板にはオーガニックカフェと謳った。しかし実際はすべてオーガニックの材料を使うというわけには行かなかった。できるところはオーガニックを心掛けて菓子を作った。最初の頃は物珍しさもあったのだろう、売上は順調だったが、店のスタッフの出入りが多く、人事問題で頭を悩ませることがしばしばあった。
それを救ったのはやはり純一の菓子の美味しさだった。リピーターのお客様が増え、売上が右肩上がりで伸びていった。その手ごたえを確かめてから、純一はスタッフの給与レベルを思い切って引き上げた。それからはスタッフの出入りはめっきり減った。
あれから4年。純一も35歳になった。九段店の他に新しい店を出したい、できれば銀座で勝負してみたいという気持ちがいつしか湧いてきた。
純一は東京に近い山梨県でオーガニックの食材を栽培してくれる農家のパートナー探しを始めた。友人に紹介された山梨県甲府在住のSさんは地元の農家に強い人脈を持っている。
昨年の秋、純一は山梨県の身延町から南部町と回った。Sさんと夕食の後別れて旅館に戻る帰り道、満天の星を見た。その瞬間、自分は孤児の気持ちを心の中に抱えながら生きてきた、ずっと一人で生きてきたんだという思いが突き上げるように湧いてきた。涙が止まらなかった。自分の気持ちを聞いてもらえる友が自分にはいなかった。実際は自分から友を求めたことが無かったのだ。他の人と親しい、深い関係をつくることをいつも避けていた。それが菓子づくりに打ち込む原動力になっていたのかもしれない。しかし、今は違う。
いつの頃からか人々を幸せにするために自分は菓子をつくっているのだという気持ちになった。それはお店で純一の菓子を笑顔で食べているお客様の姿を見てからかもしれない。あるいは子供の頃、プリンを食べた時の喜びを思い出したからかもしれない。とにかくいつの間にかそんな気持ちになったのだ。そして純一はそんな気持ちになれた自分が嬉しかった。
山梨県ではオーガニックの果樹の材料の調達に奔走した。ブドウ、桃、ブルーベリー、リンゴ、クルミ。そして思いがけず果物のような味のする伝統野菜も見つけた。またこれらの果樹をパレット付き木枠セットで栽培し、デパートの屋上に持ってくる。純一は果樹の実際の姿も都市に住んでいる人たちに見てもらいたいと思っている。
天空カフェは夕方5時からはワインも出すことにしている。純一はワインのことを調べているうちに「日本ワインの父」と言われる川上善兵衛氏のことを知った。現在の新潟県上越市に「岩の原ブドウ園」がある。そこでワインも作っている。創業してから130年も経っている。純一は11月のある日、「岩の原ブドウ園」を訪れた。少しゆっくりしたかったので、北陸新幹線で向かった。上越妙高駅で降りてタクシーで「岩の原ブドウ園」についた時は午前11時だった。早速ワインの樽の貯蔵室を見学した。樽はフランスの樫の木製だ。貯蔵室は夏でも室内温度が15℃以上にならないようにあらかじめ冬の間に貯蔵した雪を使っているとのことだった。見学の後は川上善兵衛記念館で川上氏の遺品、記念品を見た。生涯約16,000種のぶどうの人工交配をした川上氏の業績に触れ、純一は創業者精神の神髄に触れたような思いがして心が震えた。ワイン工場の背後に迫っている丘の中腹にブドウ園が、また丘の上にブドウ園があった。丘の上からは遠くアルプスの山々が見え、その前に高田の町の風景が見えた。雲一つない青空の下、何か夢を見ているようだった。天空果樹園カフェには「岩の原ブドウ園」のワイン、特にマスカットベリーAを中心にしてコーナーをつくろうと純一は決めた。
モリンガの林づくりは静岡県の農家が協力してくれることになった。果樹と同じように木枠セットでモリンガを栽培し、それをパレットに載せてデパートの屋上迄運んでくる。
純一は京都府の宮津市の里山で生まれた。10歳で両親と死に別れした。それから叔母のところでの生活。そして菓子職人としての道を歩き、今ではカフェのオーナー、パティシエとなった。そしていよいよこれから銀座のデパートに出店する。これは大きなチャレンジだ。今回銀座のデパートに出店するにあたり純一はクラウドファンディングという仕組みを使った。全部で200万円集まった。
純一は雨の日、打ち合わせの後、黄色くなったイチョウ並木の脇の道を歩きながら天国の両親に呼びかけた。「お父さん、お母さん、ぼくはここまでくることができました。これからも見守り続けてください」
純一の心の中でブドウの木が声をかけてくれた。「一緒にがんばりましょう」
屋上菜園物語(16)寂しさのはてなむ国
本間 寛は路地に面したアパート2階の引き戸を開けてタバコに火をつけた。自分と同じくらいの老年の男性がリックを背負ってうつむき加減に歩いていくのが見える。その後ろ姿を見送ってから寛はガタガタと音をたてる引き戸を閉めて、座布団の上に座り、ぼんやりしていた。いつの間にか夕日がスリガラス越しに部屋に中に差し込んできている。何もすることがないので、近くの公園にぶらっと出かけた。歩いて5分ほどのところにある小さな公園だ。桜の木が数本植わっている。今年の4月、缶ビールを持ってこの公園に来た。一人でビールを飲み、一人で桜の花を愛でた。今は桜の枯葉が足元で風に吹きまわされている。季節の移り変わりがなんと早いものか。寛の頬を夕陽が染めている。
寛は夕暮れの紫がかった空を流れる雲を見ながら、小声で歌い始めた。杉本まさとの「吾亦紅」。昔の母という立場、役割を生き切った母と比べて自分はなんと浮草、流れ草のような人生を送ってしまったものか。今度は自分のわがままでそんな自分を支え続けてくれた妻と別れることになった。いつまでもこんな自分に付き合わせては申し訳ない、妻を自分から自由にしてあげたい。これ以上迷惑はかけられない。そんな気持ちさえ、自分勝手で無責任としか言いようがないのかもしれない。
そんな自責の気持ちが母に対してだけでなく、妻に対しても、この歌には込められているのだろうか。寛はもう一度歌った。
寛の妻、公子は現在特養老人ホームに入っている。今年の春迄一緒に暮らしていたが、認知症が進み、予想もしていなかったことだが、夫である自分に罵詈雑言、暴力をふるうようになった。下の世話もしなければならなかった。暫く様子を見ていたが、自分にはこれ以上世話が難しいと判断して近くの特養老人ホームに入ってもらうことにした。
寛は親の書店業を継いだ。場所は市ヶ谷で、学生もサラリーマンも多く経営は順調だったが、将来のことを考え、建物を建て替え、5階建ての貸事務所ビルにした。その1階でずっと書店業を続けてきたが、3年前に廃業し、1階もコンビニに賃貸で貸している。幸いなことに5フロワー全部にテナントが入っているが、建設資金の銀行返済が毎月かなりの金額になり、それほど余裕があるわけではない。毎月の特養老人ホームへの支払いにメドをつけて、公子を老人ホームに入れた。公子は嫌がったが、今は妻との距離を置く時なのだと自分なりに理由もつけてのことだった。毎週老人ホームに行き、公子と面会するが、「家に帰りたい」と必ず言う。私は「職員の皆さんの言うことを聞いて迷惑をかけないように」とたしなめる。老人ホームからの連絡によれば、ホームの中では公子はおとなしくしているとのことだが実際は手を焼かせているかもしれない。
アパートの2階に戻ってきて寛は夕食を準備した。納豆、豆腐、サバの缶詰。公園からの帰り道、コンビニで買った野菜サラダの詰め合わせ。自分が病気で倒れたらどうしようもなくなる。せめて自分は元気でいなくてはいけない。テレビの健康番組を参考にしながら、寛は健康に良い食べ物をとるように心掛けている。
食事をしながらテレビを見ていると最近特に老人ホームの中の事件、家族の中の事件が増えているように感じる。何かタガが外れた、辛い時代になっているのかもしれない。
以前寛は廃業してやっと二人だけの時間が取れるようになった時、公子に言った。「二人で国内旅行をしよう。どこに行ってみたい?」。公子は友人のいる場所を3ヶ所挙げた。能登半島の輪島、北海道の札幌、そして大阪。「観光だけじゃなくて、そこに知り合いがいるのがいいわ。」公子はそれぞれの場所毎に夫婦共通の友人の名前をあげた。
寛も二人で行きたいところがやはり3ヶ所あった。熊本県の天草、福島県の大内宿、秋田県の八郎潟。ところが公子に認知症が突然出て、一緒に旅行に行くのが難しくなった。
何年か前、二人は伊豆下田に1泊2日の旅行に出たことがあった。下田市街から少し離れたホテルに泊まった。夜は露天風呂から下田港の灯が見えた。夕食にはお約束の金目鯛の煮付けがでた。翌朝はホテルで朝食後、チェックアウトして下田の町をゆっくりのんびり歩いた。道路脇に花を植えたプランターが置いてある。花の多い街だ。由緒のあるお寺に2ヶ所ほど立ち寄った後、ランチは街中を流れる川の傍のレストランで取った。午後はペリー来航の場所迄足を延ばした。その先の岸壁では釣り人が大勢いた。何枚か写真も撮った。・・・そんなことを思い出しているとふぃに涙があふれてくるのを感じた。
寛は下田市の南隣の南伊豆町の下賀茂温泉に行くことにした。気分転換を兼ねた2泊3日の旅行だ。知人がペンションを経営している。知人は下田駅迄車で迎えにきてくれた。彼とは学生時代からの長い付き合いだ。サラリーマン生活を切り上げて10年前に下賀茂にペンションをオープンした。自分のところの農園を持って有機野菜を宿泊客に出している。
昼食後、近くの熱帯植物園に連れていってくれた後で、折角ここまできたのだから石廊崎迄行こう、ということで足を延ばした。海の色が濃い。寛は太平洋の大海原に暫く見とれていた。宿泊客が少なく彼とは積る話をした。ペンションの経営はなんとかうまく行っているが、後やっても10年くらいかな、とのことだった。
翌朝彼の農園を見た。ゆるい傾斜面にある畑だ。まだ朝食迄時間があったので畑迄歩いて行った。今は晩秋なので秋冬野菜だ。寛は野菜の種類については詳しくないが、ブロッコリー、ホウレンソウ、シュンギク、キャベツ、レタスが育っているのは分かる。そして一際目立つのが土の上に白い肌を見せているダイコンだ。朝風の中で葉がさざ波のように揺れている。
寛は秋の野菜を見ながら、自分の人生も春、夏が終わり晩秋に近づいている、そして失敗の多い、寂しい人生だったなと心の中で呟いていた時、思わず若山牧水の「幾山河こえさり行かば寂しさのはてなむ国ぞ今日も旅ゆく」が口をついて出てきた。ダイコンの傍に寄り寛はダイコンに話しかけた、というより呟いた。「自分は今とっても寂しいんだ」
ダイコンは暫く経ってから応じた。「確かに寂しそうな顔をされていますね。でも寂しさって何でしょう。私たちは種を播かれ、芽を出し、葉を伸ばし、根を伸ばし、根を太らせ、花を咲かせ、種をつけていきます。単純と言えば単純な一生です。しかし私たちは人々が、ここに住み着き、畑をつくり、野菜を育ててから何百年間もここで繰り返し、繰り返し生きてきました。私たちを必要とし、育ててきてくれた人々がいたからこそできたことです。寂しさは自分が誰からも必要とされていない、というところか生まれてくるのかもしれませんね。他の人から必要とされるためには、まずご自分がご自分を大切にするという気持ちが大事なのでは・・・。生意気なことを言いました。生意気ついでに私は「寂しさのはてなむ国」は永遠の国と思っています。そしてこの私たちが今いる場所が永遠の国です。」
寛はダイコンに答えた。「そんな風に言ってくれてありがとう。言ってくれたことはよく分かるんだけど人間って複雑なんだ。最近つくづくそう思う。・・・しかし単純に生きる、というのが簡単じゃないけど今の自分には必要なのかもしれない」
ダイコンが励ますように言った。「生きる、真っ白な気持ちでひたすら生きることに徹したらどうでしょうか。余計なことを考えず、他人の人生と比べたりしないで、ただ今を生きる。私たちはそうしています。私たちは背中をまっすぐ伸ばして天と地の間で生きています。一生の辛さ、喜びも感じていますよ。それが私たちの辛さ(からさ)であり、甘味でもあるのです」
ダイコンは微笑むかのように葉を揺らした。
単純に生きる、ただ生きる、まっすぐに生きる・・・自分でもう一度口にした時、なんとも言えない爽やかな気持ちで心が満たされた。こんなことは初めてだった。そして改めて自分の人間としての弱さ、甘さに思い到った。ダイコンのように一人で生きる強さを自分も待たなければならない、と。
寛は旅行から帰ってきてすぐに、区役所に行き、社会福祉協議会にボランティア登録をした。小銭を稼ぐアルバイト的なことより小さくとも社会的価値のある仕事をしたいと思ったからだ。暫くすると社会福祉協議会から連絡があった。近くの大きな特養老人ホームが
屋上菜園の野菜を使った地域交流をするので、そのコーディネーターの手伝いをしてほしいという話だった。当日コーディネーターが地元の親子を10組連れてきた。屋上菜園の野菜の葉と花を入居者と子供が一緒に収穫した。それを使って、一つは押し葉を作る工作、もう一つは葉と花を細かくちぎって手製の万華鏡に入れる工作。日頃子供達と触れ合う機会の少ない高齢者は一緒に作業しながら笑みを浮かべ、笑い声さえ立てている。寛も実際にできた万華鏡の中を見た。「野菜でもいろいろ面白いものができるんだ。」それは寛にとって大きな発見だった。
この屋上菜園を管理し、野菜栽培を指導し、菜園カフェタイムを担当しているAさんをコーディネーターが紹介してくれた。
Aさんは都市の屋上菜園関係の事業を展開しているある一般社団法人の役員の一人だった。
Aさんは屋上菜園がなぜこれからの時代必要なのか、寛の質問に答えながら丁寧に説明してくれた。
Aさん「もしよろしかったら私たちの栽培管理の作業を手伝っていただけませんか。私たちがこの屋上菜園に来るのは月2回です。職員さんにもお世話をお願いしていますが、日頃のお世話をお願いできれば助かります。私たちと一緒に作業する日は別にして、まず週1回ぐらいでどうでしょうか。手入れの仕方は私たちがお教えしますよ。」
その時、寛はそんなことでお役に立てるなら、と即座に快諾した。
「分かりました。是非やらせてください」
寛は屋上で野菜栽培ができるとは思っていなかった。屋上で野菜を栽培するためにはそれに合った土壌と栽培方法があることを教えられた。Aさんがマニュアルを見せてくれた。
「このマニュアルを使って今後現場で現物を見ながら説明していきますね」
絵と写真の多い分かりやすそうなマニュアルだった。
「本間さんですね。これから一緒に作業できるのが楽しみです。本当に助かります。」
Aさんは自分より少し年上のようだ。笑顔が優しい。
別れ際、寛は「よろしくご指導の程お願い致します。」と頭を下げた。
寛は自分が住んでいるアパートの屋上が空いていることに気がついた。いつもは物干し干し場として使っている。大家さんは近所のおばあさんだ。頼まれてこのアパートに住んでいる。かん水の水は水道の蛇口が無いのでジョーロで運ぶことにした。おばあさんのところへアパートの屋上にプランターを置いて野菜づくりをしたい、と使用許可を求めに行ったら、「どうぞ、どうぞ」と言ってくれた。自分の住んでいるところでも、老人ホームでもこれから野菜づくりができる。寛にとって野菜づくりは生甲斐づくりになりそうだ。野菜づくりを通じていろいろな人と出会い、普段着の気持ちでコミュニケーションを持つことができる。そして寛は南伊豆町の下賀茂温泉で出会ったダイコンの姿と会話を折りに触れて思い出すのだ。野菜は育てて食べるだけではない、野菜の一生から教えられ、気付かされることがある。私も野菜と一緒に生きていこう。
ある日、寛は公子の老人ホームに行った時、アパートの屋上で育てて収穫したホウレンソウを持って行った。最初公子は怪訝な顔をしていたが、寛がアパートの屋上で野菜づくりをしていることを話すと「良かったわー、私あなたのことがずっと心配だったの。」と認知症とは思えない真顔で返事をしてくれた。今日は調子がいいようだ。この老人ホームでも屋上菜園を検討していると若い職員が説明してくれた。寛は「是非設置してください」と
伝えた。それを聞いた公子が「その時は私も野菜づくりに参加させてください。」
嬉しそうにほほ笑んだ。
屋上菜園物語(17)パソコンの前から屋上へ
高山美香はデザイナーだ。彼女の特技は写真をデフォルメして超現実的な画像を創り出すことだ。大手も含め広告関係の注文が多い。仕事の方は順調だが、締切に追われることが多く、睡眠不足になりがちだ。また仕事時間中はほぼ椅子に座りっぱなしなので腰に度々痛みが走る。おまけにパソコンの画面を見ているためストレートネックになっているのだろうか、やたらと肩が凝る。忙しい時には昼食もデスクでパソコンの前で仕事をしながら食べることが多い。ただ最近気になっているのは身体的なことよりも神経的、精神的なことだ。言葉では適確に表現できないのだが、パソコンの画面ばかり見ているうちに現実の世界にリアル感を感じられなくなっている自分に気がついた。それに気がついたのは新入社員の女性が花瓶の花をミーティングテーブルに置いた時だった。
花というよりも何かモノが置かれているとしか感じられなかった。花というよりもモノだった。その一方でパソコンの画面に映っている花は花と認識することができる。画面の花は香りもしないし、触れることもできないのに・・・。この逆転現象は何を意味するのだろうか。美香は不安になった。何か人間として、とても大事なことのバランスが崩れ始めているのかもしれない、と。そういえば最近頭痛も時々感じる。
美香は以前仕事をしていた桃川オフィスの桃川氏のことを思い出していた。桃川氏が米国に活動の拠点を移すことになった時、美香は米国迄ついていけないので、今のデザイン事務所に移った。その桃川氏が5年振りで米国より帰国し、現在青山の前の事務所で仕事をしていると聞いた。
午前12時前に桃川事務所に電話を入れたところ桃川氏が出てきた。
「高山です。高山美香です。ご無沙汰しています。桃川さんが帰国されたと聞きましたので久しぶりにお会いしたくて電話をしました」
「お電話ありがとう。久しぶりだね~。お元気ですか?そう、それは良かった。それでは急な話だけど今週土曜日朝7時半私の事務所に来ませんか」
「朝7時半ですか?そんなに早く」
「そう。来てもらえば分かるよ」
翌朝美香はいつもより早く起きて手早く朝食をとってから駅に向かった。降りたのは千駄ヶ谷駅、歩いて3分の、4階建てビルの4階に桃川事務所がある。桃川はこのビルのオーナーでもある。1階はカフェ、2階は美容クリニック、3階はアパレルショップの本店が入っている。桃川の事務所のドアのベルを押すと、小柄な女性が出てきた。桃川氏の奥さんだ。奥さんも一緒に米国に行っていたと聞いていた。
「お久しぶりです。高山さん。今日は朝早くからごめんなさいね」
「お元気そうでなによりです」
屋上に上がる階段から桃川が降りてきた。
「高山さん、おはようございます。ちょっと上にあがりませんか。見てほしいものがあるんです」
美香は階段を上がってびっくりした。ビルの屋上全体が畑になっている。
「すごいですね。いろんな野菜が育っている」
桃川はプランター毎に説明してくれた。「ここのプランターはみんなキャベツ。ぼくはキャベツが好きだからね」「こっちはビーツ。ほらボルシチなんかで使うカブ。色がとってもキレイなんだ。」桃川は次から次へとプランターの野菜について説明してくれた後で、思い出したように、「それでは下に降りてお茶にしましょう」
美香「桃川さんがこんなに野菜好きとは知りませんでした。いつから野菜栽培をするようになったんですか」
桃川「実は米国に行ってパートナーのオフィスでデザインの仕事を始めて間もなく、体調を崩してしまったんだ。パートナーの期待に応えようと思って頑張りすぎたのかもしれない。1日15時間以上もパソコンの前に座っていた。家に帰るのは寝るだけのようになってしまった。家ではちょっと大げさに言えば抜け殻みたいで家内には随分心配をかけた」
美香「奥さんは大変でしたね」
桃川「そんな時、パートナーがちょっと気分転換をしませんか、と彼の別荘に連れて行ってくれた。彼は週末はこの別荘に来て、畑仕事をしているとのことで、私も手伝ったんだ。一泊二日で少し気分が変わったような気がした。それを彼に伝えると『それは良かった。土は人を癒すと言われているが、やはり本当なんだね。そしてミスター・モモカワ、私の期待に早く応えようと頑張りすぎないように。ゆっくり、ゆっくりやってください。その方が結果的にクオリティの高い仕事ができます』
美香「パートナーの方、素晴らしい方ですね」
桃川「それからはパソコンの前に座りっぱなしということの無いように心掛けるようにした。30分パソコンの前で仕事をしたら3分間デスク椅子から立ち上がって歩き、ストレッチをする、ランチタイムはデスクを離れて外の景色を見ながら、ランチテーブルでゆっくり味わいながら食べるようにしたんだ。そして1ヶ月に1回ぐらいだったけどパートナーの別荘に泊まって農作業をするようにした。」
美香「効果はどうでした?」
桃川「3ヶ月経った頃には体調も回復し、元気になった。最近の流行の言葉でいうと自律神経のバランスが回復したということかもしれないね」
美香「良かったですね。ところでニューヨークではブルックリン地区の大きなビルの屋上が菜園になっているというのを何かの記事で読んだことがあったんですが、本当にそんなところがあるんですか」
桃川「あるんだね。ブルックリンなら近いので、実は私もそこに申し込んで会員になったんだ。毎週日曜日は家内と一緒に農作業三昧の生活をすることができた。そして一番うれしかったのは幻覚のようなものが消えたことなんだ。夜寝ている時に幻覚に襲われることがしょうっちゅうあった。そんなこともあって日本に帰ってきてからも屋上で野菜づくりをしている。ナチュラルとアンナチュラルの間でやっとバランスを取ることができるようになったんだ」
美香は桃川の幻覚ということばをゆっくり受けとめてから、思い切って言った。
美香「桃川さん、実は私の場合は幻覚というよりも何か逆転現象があるんです。」
美香は最近感じている違和感について桃川に話した。現実が現実として感じられなくなっているんです。何か現実が遠くなっている、と言ったらいいかしら。」
桃川「美香さんは自分で違和感に気付いたんだね。少し休暇をとって旅行でもしたらどうかな。そしてマンションにベランダがあったら何か野菜でもハーブでもいいからやってみるのもおススメかな」
美香は桃川に旅行に行くことを勧められたが、デザインの注文が詰まっていてなかなか行けなかったが、2ヶ月後、やっと時間が取れて山梨県の南部に2泊3日で出かけた。知人からそこでスーパーフードの野菜の栽培をしている農家を紹介された。川の上流にある温泉に泊まり、翌朝農家のSさんに連絡した。Sさんは旅館迄来てくれた。
Sさん「わざわざ遠いところまでお越しくださりありがとうございます。何も無いところですが、自然だけは一杯あります」
Sさんの農園に着いてびっくりしたのはその広さだった。
美香「いろんなものを栽培しているんですね」
Sさん「主にスーパーフードと言われているものを栽培しています。ちょっとへそまがりなもんで、普通の野菜では面白くない。これからは健康価値の高い野菜、植物の時代だろうと考えてスーパーフード中心の農場で行くことにしました。こっちは今注目されているモリンガの林です。モリンガの原産地は北インドと言われていますが日本でも暖かいところであれば栽培できます。亜熱帯性の植物です。あちらはえごまの畑です。葉っぱも食べられますが、人気のあるのは種から搾った油です。最近テレビでもよくえごま油を取り上げています。その向こうはビーツの畑。ビーツは鉄分が多く「食べる輸血」とも言われています。その向こうは雲南百薬。これから段々種類を増やしてスーパーフード農場として売り出していきたいと思っています。私は以前はサラリーマンをやっていましたが、不摂生で身体を壊してしまいました。薬もたくさん飲みましたが、ある時食生活を変えたらどうだろうと思いついて、それだったら自分で作ろうと思って農家になりました」
美香「随分思い切った決断をしたんですね」
Sさん「紹介してくださる方がいてこの町の地主の方にお会いしたら、是非来てください。
現在耕作放棄地が増えて畑が雑草だらけの荒地なっている。いくらでもお貸ししますよ、ということでこの町に住み、農作業をすることになりました」
そんな話をしているところへ女性が現れ美香に挨拶した。女性はSさんの奥さんで、後で聞いたところによれば地主さんの一人娘とのことだった。
地方の山間部の町に行くととにかく夜が寂しい。道路の街路灯も殆どなくて車はヘッドライトを頼りに暗闇の中を走ることになる。
Sさんの奥さんは地元の若い人たちと一緒に、たまり場風のカフェを運営している。カフェタイムは午後2時から5時迄と午後7時から9時迄。午後は主に車で移動している旅行客、夜は地元の若い人と旅館に宿泊している観光客だ。暗い町に灯が点る。
美香はその日一日Sさんについて農作業を手伝った。実際は足手まといだったかもしれないが、デザインの仕事のことは忘れて身体を動かした。畑で食べた昼食も美味しかった。握り飯、野菜の煮付け、サバの塩焼き、梅干し。初めて飲んだモリンガとエゴマと豆乳のスムージーは独特の美味しさもさることながらなぜかこれで健康になれるという気持ちにしてくれた。
夕方迄畑で作業した後、Sさんは美香を自分の家に招き、夕食をふるまってくれた。
Sさん「また機会がありましたら是非お越しください。」
美香「今日一日畑にいたせいでしょうか、身体は疲れましたが、気持ちのいい疲れです。御蔭様で気分もスッキリしました」
Sさんは美香を旅館迄送ってくれた。美香は身体を動かした後の温泉がこんなにも気持ちがいいことを実感した。「こんなの初めて~」
ぐっすり眠った。
翌日の朝、旅館にNさんが迎えに来てくれた。山の竹を竹炭にするプロジェクトのリーダーのNさん、40代の女性だ。保険会社に勤めていたが、途中退職して現在は山を守るために竹林を伐採して竹炭にして販売する事業を展開している。
山の斜面での作業なので、やはり疲れる。Nさんは無理しないように、見ているだけでもいいですよ、と言ってくれた。さすがに昨日の疲れもあり、Nさん言葉に甘えた。見てみると全部で作業している人達は10名ほどだが、女性はそのうちの半分だった。リーダーのNさんが女性にも積極的に声をかけているのだろう。
その晩は町役場の近くのイタリアンレストランで夕食会があり、美香も誘われて参加した。驚いたことはUターン組、Iターン組が半分くらいいたことだった。
美香は東京に戻ってから早速木製プランターを購入し、モリンガと苗を植えつけた。
「リアルな現実よ、私に戻ってきて」
そう祈り、手を合わせた。
屋上菜園物語(18)銀座屋上葡萄園
冬の日の夕暮れ、南部稔に電話があった。「初めてお電話しますが、私は高居と申します。南部さんの所属されている一般社団法人のホームページを見て、屋上でブドウを栽培していることを知りました。実は私も自分のビルの屋上でブドウを栽培しています。電話では話が長くなりますので、一度来ていただけないでしょうか。詳しいお話はその時させて頂きます。場所は銀座7丁目です」
高居さんはビルの住所とそのビルの7階に住んでいると伝えてくれた。訪問する日時を決めた。1週間後だ。
1週間後の金曜日、南部は高居さんのビルの前に立っていた。鉛筆ビルほどではないが、小ぶりの古いビルだ。1階は店舗が入っている。脇のエレベータで高居さんの住いのある10階迄上がった。ドアのベルを押すと、年配の女性が出てきた。部屋の中に入ると車椅子に座っている高居さんがいた。
「今日はよく来てくださいました。どうぞそちらにお座りください。家内です」
「南部です。お声をかけてくださりありがとうございました」
「今日来て頂いたのはブドウのことなんです。実は急に足腰が立たなくなってしまい昨年 まで自分で世話していたのですが、来年はどうも自分でブドウの世話をすることがで きそうもありません。このブドウは私にとってはとても大切なブドウなので、来年もなんとか続けられないものかと思っていたところ、そちらのホームページを見て、屋上でブドウ栽培をしていることを知り、そこでお願いできないかと思った次第です」
「高居さんのブドウの木を拝見させていただけますか」
10階の半分は住居になっていて、住居スペースの前にはウッドデッキが張ってあり、その先に庭が広がっている。陽当たりの良い庭の真ん中にブドウに木が一本植わっている。高居さんは奥さんに車椅子を押してもらい、ブドウの木の傍らに来た。
「このブドウの木はここに植えてから5年目になります。あることを記念して植えました。種類はマスカットベリーAです。友人の山梨県塩山市のブドウ農家に頼んで植えてもらいました。植えた翌年から房が付き始め、今年は40房ほど収穫できました。嬉しかったですね」
「ブドウ栽培の仕方はどのようにして覚えられたのですか。都市の中での栽培ですから農薬は使えないですよね」
「そうなんです。有機的栽培ということになりますか。塩山市の農家に栽培のことを相談しましたら、農薬なしにブドウ栽培はできませんよ。もしできたとしても3年目頃からうまくいかなくなる、と言われました。農薬を使わないのなら栽培指導はできないと言われて、後は自分なりにブドウの有機的栽培の仕方について本を読んで、失敗をしながら何とかある程度できるようになりました。ビルの屋上という場所は案外ブドウの有機的栽培に向いているのかもしれませんね」
「私もそう思います。私たちの屋上ブドウ園でも病気は殆ど出ていません。出たとしても葉に出るべと病、幹に出るうどん粉病です。問題なのはコガネムシです。完熟期になるとやってきます。うどん粉病には竹炭を根元に撒いておけばほぼ防げます。コガネムシ対策は袋掛けですね。私たちが栽培しているブドウは高居さんと同じようにマスカットベリーAです。ブラックビートも少しやっています。ブドウは芽かき、菓舗の整理、房づくり、摘心、摘房、摘粒と細かい作業がありますが、お身体が不自由なのによくおやりになりましたね」
「今年はなんとかできましたが、来年はもう無理だと思っています。それで助けてくださる方を探しているうちに、南部さんの団体に行き着きました」
あくる年の1月から月2回、高居さんのお宅を訪問し、一緒にブドウ栽培をすることになった。高居さんは午後から病院に行くとのことで、作業時間は朝9時から11時迄とした。
実際の作業は1時間ほどで終えて、その後は高居さんの希望で懇談の時とした。
帰り際、南部は高居さんに言った。
「銀座7丁目といえば、昔シャンソン喫茶の銀巴里がありましたね。私は若い頃、時々、銀巴里に行き、シャンソンを聞いていました。小海智子、大木康子、津軽弁の工藤勉が好きでしたね」
「嬉しい話ですね~。銀巴里をご存知なんて。私も時々ですが、行ってましたよ。当時はメケメケの丸山明宏も出ていましたね。今度銀巴里の話もしましょう」
1月下旬、南部は高居さんのお宅に伺い、ブドウを栽培している木枠の中の土に竹炭を撒いた。この竹炭はポーラス竹炭で千葉県いすみ市の竹炭研究会でつくっている。竹炭散布の後、枝の剪定作業をした。高居さんは傍で見ていた。作業の後、部屋に戻った。奥さんがお茶と菓子を持ってきた。「どうぞごゆっくりなさってください。私はちょっと買い物に行きますので」
高居さんはブドウの木を見ながら、ポツンと言った。
「私は大腸ガンなんです。ステージ4で転移が進んでいるのでそう長くは生きられません。でも二度とない人生ということで自分なりにやりたいことをやってきましたので、特に悔いはありません。勿論、私も人並みに自分の人生の意味とか生きがいが分からなくて悩んだ時期もありましたが、ある時、凡人である自分などそんな哲学的問題に関わる必要はないと割り切ってとにかく目の前の問題だけに取り組んでいくという、良く言えば一日一日を大切にする、悪く言えばその日暮しの生活をしてきました。あのブドウの木は私の一人息子を偲んで植えたものです。息子は学生時代、フランスに行ってワイン農家に民泊させて頂いたことがキッカケになって、日本に帰ってきてから山梨県勝沼市のワイン会社に就職し、将来は自分で日本産ワインの会社を起こしたいと考えていました。そして7年前縁あって結婚しました。結婚式はハワイであげました。・・・あのころが私たち家族にとって一番幸せでした。その息子が奥さんの実家がある宮崎に飛行機で行った時、飛行機が墜落し、二人とも天国に行ってしまいました。妊娠の報告のための帰省だったんです。それから半年間、どうやって毎日を過ごしていたか、思い出せません。・・・いやいやすっかり暗い話になりました。話題を変えましょう」
「大変な経験をされたんですね。その大変さは私にはとても想像もつきません」
「その後私は父の時代からやってきたお酒の販売店ですが、品揃えにワインを加えるようにしました。私の齢ですから今からワイナリーを立ち上げるのは無理ですが、販売ならできます。息子が果たせなかった夢を少しでも叶えてあげたい、そんな気持ちでした。今では店の売上の三分の二がワインになっています」
「天国の息子さんもお父さんのお店を応援されているのではないでしょうか」
「そうだと思います」
それから二人は話題を変えて、銀巴里の思い出を語り合った。高居さんは遠くを見るようにして言った。
「私は金子由香利が好きでした。彼女のレコードを買って何度も何度も聞きました。彼女が銀巴里の舞台に出る時は、できるだけ都合をつけて行ったものです。特に好きだったのは「再会」でした。話すような、歌うような彼女の歌い方がなんとも言えなかった。南部さんは小海智子、大木康子、そして工藤勉がお好きだったとか」
「そうなんです。シャンソン歌手には大人の女性というイメージを抱いていました。ちょっと手の届かない女性、ということでしょうか。最初に行ったのがなにしろ浪人時代。現役で大学に入った連中は女子学生と腕を組んで歩いている。それに引き換え、こちらは2浪。ほぼ毎日予備校通い。母からは来年こそ志望校に入ってよ。隣近所から息子さんはどうしていますかと聞かれて肩身の狭い思いをしているんだから、と言われていました。小海智子さんの明るさに救われたような気持ちになったことがありましたね。工藤勉さんの津軽弁のシャンソンには地方に生きる人の深い悲しさ、逞しさを感じました。大木康子さんには自分もそれなりの大人になったら大木さんのような女性と付き合いたいと思わせる雰囲気がありましたね。浪人時代でしたので、使える小遣いも少なく、そんなには行けませんでしたが、大学に入ってからは家庭教師のバイトもやっていたので、1ヶ月に1回くらいは行ってました。私は工藤勉のレコードを買いました」
2月にはもう一度剪定作業をした。3月中旬に入るとやっとブドウの芽が出てきた。萌芽だ。ただ3月は天候不順の日が続き、展葉迄時間がかかった。4月上旬になると一斉に展葉が始まった。展葉の芽かきは3回に分けて行った。新しい枝、梢についた花穂を2つ残すか、1つだけにするか。判断しながらの作業となる。
高居さんは南部の作業をじっと見守っていた。病状は明らかに進行していた。車椅子に座っているのが辛い時には簡易ベッドを庭に置いて、寝ながら作業の様子を見ていた。
そして4月も下旬になると新しい枝が伸び葉を拡げ、アッという間に沢山の花穂がついた。6月にはいよいよ房づくりだ。種あり栽培と種なし栽培とでは房づくりのやり方が違ってくる。高居さんのブドウは種ありなので副穂を切り、先端も詰めて主穂の長さを10cm、支梗は15段ぐらいにする。
房づくりが終わったら袋掛け作業だ。雨に濡れないように、またコガネムシ対策も兼ねてやるこの袋掛け作業は重要だ。
南部は高居さんに報告した。
「ブドウの袋掛け作業が完了しました。7月、8月と見守って行きます。9月初旬には予定通り収穫できそうです。ご一緒に収穫しましょう」
「南部さん、ありがとうございます。私が世話していた時よりブドウが生きいきしている感じがします。収穫が楽しみです」
暑い、雨の降らない夏の日々が続いた。南部は乾いたブドウの土に水やりしながら、袋掛けの中のブドウを覗いた。以前他の屋上菜園で夏場の水不足でブドウが萎んだことがあった。
8月下旬、高居さんから久しぶりに話がしたいとのことだったので、作業は早々に切り上げて高居さんの居間に向かった。今日は元気そうだ。なぜか高居さんは座布団に正座して待っていた。私が座る座布団も用意されていた。高居さんと向き合うように座り、目の前のお茶をお互い一服飲んだ後、高居さんが言った。
「南部さん、一つ頼みがあります。私のいなくなった後のブドウのことなんです。誠にご迷惑なお願いになりますが、私のブドウを引き取ってもらえないでしょうか。屋上でも露地でも南部さんがご都合の良いところでお世話していただければ有難いのですが、いかがでしょうか」
南部は以前から漠然とだったが、高居さんのブドウの身の振り方について考えていた。大切な息子さんの形見のようなブドウの木だ。おろそかに扱うことはできない。屋上で育てることもできるが、もっと落ち着いたところで育てられないかと考え、友人が山梨県の南部で最近ワイン用のブドウ園を始めたので、相談したところ、もしそうなった場合は喜んで引き受けさせてもらいます、という返事を受け取った。
南部はその話を高居さんに伝えた。高居さんは涙を流しながら、何度も何度も頷いていた。「南部さんに出会えて良かった。本当に良かった・・・・」
9月上旬、高居さんの屋上葡萄園のブドウを初収穫した。高居さんはもう起き上がることもできない状態だったが、南部が高居さんのブドウの木から収穫し、持ってきた3房のブドウを渡すと、胸に抱きしめるようにして、息子さんの名前を呼んでいた。
南部は高居さんの耳元に寄って声をかけた。
「息子さんのブドウの世話は私の友人と一緒にやっていきますよ」
それから二人は声を合わせて金子由香利の「再会」を小声で歌った。
・・・息子さんに天国で再会できますように。
屋上菜園物語(19)わが家の灯り
大空明美は専業主婦だ。小さな子供が3人いる。最近夫の様子が少し変だ、仕事で何か大きな問題を抱えているのだろうか。帰宅した時、アルコールの臭いがする。どこかの居酒屋で一杯飲んできているようだ。遅い夕食も殆ど会話もなくただ食べているという感じだ。明美はたまらずに夫の義雄に話かける。
明美「どうしたの?仕事でなんかあったの?」
義雄「・・・。ちょっとね。でも心配しなくていいよ」
そんな会話がそれから1週間ほど続いた。義雄の表情が段々暗くなっていった。
事態は悪くなっているようだった。
ある晩、夕食後明美はたまらずに聞いた。
「ほんとにどうしたのよ。毎晩そんなあなたの顔を見ているととにかく心配よ。こっちまでおかしくなるわ。一体何があったの?」
義雄は絞り出すような声で答えた。
「自分は商売には向いていないのかもしれない。頭の回転が遅いんだ。そしていつも何かした後で後悔する」
明美「何か失敗したの?」
義雄「実はそうなんだ。注文したある原料に問題が見つかった。仕入れ業者からは99%大丈夫ですと言われて、注文したんだけど、問題が見つかって、販売先のお客さんが引き取りを拒否するという事態になったんだ。仕入れ業者は「残りの1%が出たんですね。ただ注文は注文ですからキャンセルはできませんよ」と言われた。」
明美「それでどうなるの?」
義雄「結局うちの部の部長が販売先の部長と交渉して大幅な値引きをすることで引き取ってもらうことになった。100万円ぐらいの損害が出る。」
義雄は明美に申し訳なさそうに言った。
「今度のボーナスに影響が出るかもしれない。それと課長から「何か心配な時は自分で決めないでオレに相談してくれ。オレも部長から注意されたよ。それも厳しくな」叱られた。」
義雄は中堅商社に勤めていた。就職してから商社の仕事はどうも自分には合わないなと思いつつ早くも3年が経っていた。最近以前から付き合いのあった人材育成会社の社長から誘われたが、転職するまでには到らなかった。義雄は人材育成会社に転職する気持ちにかなり傾いたが、明美の反対で商社を辞めないことにした。明美は義雄の弱さを知っていた。義雄は組織によって守られないと仕事ができないタイプだ、ということを見抜いていた。それもあり、会社の中で出世できる可能性は低いのではないかとも見ていた。
妻の明美は義雄のサラリーマン人生に、つまり出世を期待しないと半分諦めの気持ちで自分の考えを整理した。そして決めた。子育てが一段落したら私も仕事を持とう。
義雄はこの問題が発生してから、職場の同僚、上司が自分のことを馬鹿にしているのではないかと思うようになった。自分のか弱さがつくづく厭になったが、そのうち、ノイローゼ気味になった。家族のいる自分は引きこもりになることはできないが、もしそうできたら一時的には楽だろうとさえ思ったりした。
上司の課長は「一人で決めるな。商談を決める時は必ずオレに相談しろ」と釘を刺してきた。「二度と同じことはやらないように」
ある日、部長から呼ばれた。転勤の辞令だった。子会社への出向だった。観葉植物を事務所にレンタルする会社で営業を担当することになった。部長からは「新規事業だ、頑張ってほしい。大空くんに合った仕事ではないかな」と言われたが、実際はこの手の営業マンは部においておくと将来のリスク要因になると見たのだろう。
この観葉植物を扱うという仕事が義雄に一つの転機をもたらした。観葉植物を事務所に届け、設置すると事務所で仕事をしている人が喜んでくれる。観葉植物にも人工と自然と2種類ある。採光条件を見ながら、種類と植物を決めていく。
義雄は今迄植物と触れる機会を人生の中で持つことが無かった。観葉植物を扱いながら義雄は段々自分が元気を取り戻していくのを感じていた。毎月の給料は親会社の時より減ったが、何よりも元気に働けるのがうれしい。明美には苦労をかけるが・・・。
仕事が休みの、ある土曜日の朝、明美は夫に声をかけた。
「この団地の中に住んでいる竹山さんのところで昼食会があるの。予約をしておけばこの団地の住民なら誰でも参加できて、昼食会の後はオープンカフェよ。私も1回行ってみたけど楽しかった。今日子供も連れて一緒に行ってみない?」
義雄は休みの土曜日の午前中は団地の近くの図書館で本を読んで時間を潰していた。
昼時間に竹山さんご夫妻の家に家族全員で行った。3階建ての団地の3階に竹山さんの家はあった。竹山さんの奥さんと団地の奥さん達が親睦を深めるために開いた昼食会に最近は夫婦同伴で、また家族連れで参加する団地住民が増えてきた。
義雄は竹山さんのご主人とは面識はあったが、話をしたことは無かった。昼食代は大人1人200円、子供は半額の100円だった。皆で食事をしながら自己紹介をした。世間話に花を咲かせた。竹山さんのご主人から、今この団地の中で小さな菜園をつくり、野菜を栽培しているとの話があった。
竹山さんのご主人「約10平方メートル(㎡)ぐらいの畑で季節の野菜を無農薬、無化学肥料で栽培しています。今は私一人でなんとかできますが、できたらどなたかにお手伝いして頂ければ助かります。今日の昼食会のサラダで出たレタスは実は畑でとれたものです」
竹山さんのご主人がそれとなく義雄に顔を向けた。
義雄は思わず言った。「レタス、美味しかったです」
1週間後の土曜日の午前9時、菜園で竹山さんと一緒に農作業をしている義雄の姿があった。作業が一段落した休憩の時、竹山さんのご主人が義雄に打ち明けるように言った。
「大空さんを見ていると私はなぜか自分の若い頃を思い出します。私は今年で75才になります。そんな私ですが、何か大空さんの助けになりたい、そんな気持ちなんです。もし
ご迷惑でなかったらいろいろとお話を聞かせて頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。」
義雄は少し声を詰まらせながら答えた。
「ありがとうございます。こんな私ですが、いいのでしょうか。」
竹山「どんなお仕事をしているんですか?」
義雄「今は観葉植物を事務所関係に設置する仕事をしています。以前は貿易の仕事をしていました。今の仕事について何か等身大の仕事が出来ているように感じます。以前の仕事は何か背伸びしてやっていたような気がします。」
竹山「それは良かったですね。植物の緑には人を元気にする力がありますね。植物を見ているとすべての生き物は「生かされて生きている」という言葉が実感として分かります。自分だけの力で生きようと思うとついつい肩に力が入って空回りします。大きな力によって生かされていると信じて肩の力を抜けば、本来の力が出てくるのではないでしょうか。大変お恥ずかしい話ですが、私もこの歳になってやっとそうしたことが分かってきました。」
義雄「竹山さんはどんなお仕事をされてきたんですか。」
竹山「私は大学を出た後、地元の会社に就職し、そこで定年迄ずっと勤めました。土木工事用の資材を販売する小さな商事会社でした。日本の高度成長期、インフラの整備が国の重要な政策になっていました。現場事務所に行くために山奥迄行ったこともあります。65歳で定年を迎えた後、思うところがあって便利屋になりました。その便利屋も体力的に限界が来て、2年前にやめました。今は特に仕事はしていません。平凡といえば平凡な人生です。」
義雄「竹山さんは私を見ていると自分の若い頃を思い出しますと仰ってくださいましたが、どんなふうに思い出されるのでしょうか」
竹山「そうですね。一言で言えば、自分の本当の生きる意味、自分が活かされる場所を探し続けている、ということでしょうか。もう一方で自分の人間としての器の大きさがまだ見えていない。失礼なことを申し上げるようですが、若い時の私はまさにそのようでした。しかし、私が若い時にはそのような思いを聞いてもらえる人は周囲にはいませんでした。一人で悶々としていました。」
義雄「竹山さんの言われる通りです。今の私はそのような状態にあります。どうして私の今の状態が分かったんですか。竹山さんが私のようなものの人生の同伴者になってくだされば、私は独りよがりの狭い部屋から出ることができます。」
竹山「不思議なというか、齢を取ってくるとそうしたことが直感的に分かるようになるんですね。齢をとるというのは悪いことばかりではないようです。それではこれから大空さん、お互い心の中のことについて折に触れて話合うようにしましょう」
義雄が団地の菜園で農作業に加わり始めてから竹山さん宅での昼食会ではサラダの量も、また料理で野菜のメニューも増えた。竹山さんは食事が始まる前、いつも言う。
「これからの時代は薬で病気を治すだけでなく、安心安全な食べ物を賢く食べて病気を予防する時代です。特に生活習慣病は正しい食生活で予防することが基本です。」
ある日、2人は菜園の雑草を抜いていた。梅雨時には雑草の生え方が凄い。早く抜かないとアッという間に繁ってしまう。雑草を抜きながら竹山は考えていた。雑草は誰からも期待されていないのにドンドン生えてくる。この生命力は一体どこからくるのだろうか。竹山は40歳の頃、仕事で行き詰まったことがあった。一つは自分のサラリーマンとしての限界が見えたことだ。それと裏腹だが、自分と同年代の同僚が出世していく。自分の居場所のようなものが無くなっていくような気がした。
竹山は義雄に声をかけた。
竹山「雑草を抜きながら大空さんはどんなことを思っていますか」
義雄「最初は面倒だなと思いながら抜いていましたが、途中からそんなことも思わずに無心になって抜いています。すごい生命力ですね。私も見習わなくてはと思いました。畑作業を始めてからお蔭様で気持ちが変わってきました。土に触っているとなぜか気持ちが落ち着いてきます。野菜って不思議ですね。自然は「自ずから然り」とも読みますが、野菜を見ていると「自ずから然り」という感じがします。」
竹山「大空さん、凄いですね。私も最近野菜を育てていてそういう感じがします。」
義雄は観葉植物のレンタル会社で元気に働いている。お客さんの声を聞きながら義雄なりに新商品の開発にも力を入れている。近い内に2つの試作品モデルを製作してお客さんに使ってもらう予定だ。「開発に協力するよ」とお客さんに言って頂いた。
明美は子供達を保育園に預けた後、近くのカフェでアルバイトを始めた。もともと接客は好きな方だ。義雄の給与が減った分はカフェのアルバイト料で穴埋めできる。これから子供たちが大きくなったら養育費もかかる。
義雄は残業を終えて帰路についた。駅を降りて団地迄15分だ。団地の前は以前は畑だったが、今は整地されて分譲地になっている。わが家は2階だ。義雄は足をとめて2階のわが家の灯りを見た。あの灯りの下に妻と子供がいる。自分の帰りを待っている。義雄はそこに暫く佇んでわが家の光を見つめていた。
幸せの光。
屋上菜園物語(20)今、ここを生きる
緑川研志は甲府駅から身延線に乗り換え、山梨県南部町に向かっていた。平日の午後のためだろうか、乗客はまばらだ。南部町の駅迄、各駅で約2時間かかる。甲府盆地を過ぎると両側に山が迫ってくる。あれから何年になるだろうか。窓の外の流れる風景をぼんやり見ながら、振り返る。歳月の流れのなんと早いことか・・・。
緑川は現在都会の屋上に菜園を設置するという仕事をしている。そして屋上菜園には屋上菜園独特の栽培方法があり、その技術開発も進めている。緑川はこの仕事を始める時、一つ考えたことがある。それは屋上菜園で使用する資材はできるだけ自然のものを使うということだった。できれば日本の山を守るために間伐材を使いたい。最初は緑川の会社のある埼玉県の県産材を障害施設で加工してもらっていたが、先方の事情で加工が難しくなり、新たな安定的な加工先を探している時に、山梨県南部町のS商会のI会長に出会った。縁とは不思議なものだ。あれからもう数年になる。
S商会は製材と木工製品加工を専門的に行っている協同組合と近い関係にあり、屋上菜園で使う木枠と木工製品はすべてS商会にお願いしている。メインの木枠の材料は南部町の山林から出るヒノキの間伐材だ。
右側の窓の下に富士川の大きな流れが見えてきた。内船駅で電車は停まった。降りた乗客は研志と若い男性の2人だった。この駅は無人駅だ。
S商会の会長の息子さんで専務のKさんが迎えに来てくれた。まず車で協同組合の作業場に寄った。Sさんが現在試作中の木工製品を見る。間伐材、端材を使ったベンチ、簡易式屋台。作業場の後S商会の事務所に寄って皆さんに挨拶した後、今晩泊る民宿に向かった。山の麓にある。
民宿の客は研志一人だった。大きな食堂で夕食を食べた後、部屋に戻り、窓を開けた。夥しい星がきらめいている。研志は星を見ながら一緒に屋上菜園事業を始めた仲間の島崎健三のことを思い出していた。島崎は5年前、肺がんになりこの世を去った。亡くなる直前病院にお見舞いに行った。島崎は言った。「大変だと思うが、日本の都市に屋上菜園を一つ一つ増やしていってほしい。オレにとっても夢の扉だ。たのんだぞ。緑川ならできる」さらにこうも言った。「今日は仕事の帰りだろ。疲れているんだろうから、オレのことはこれでいいので、早く家に帰れ。」島崎はその1週間後息を引き取った。
研志は風呂を使った後、部屋から林田に電話した。今回は林田にも一緒に来てもらう予定だったが、林田は急に病院で検査を受けることになり、入院となった。心臓に入れたカテーテルの具合がどうも良くないらしい。林田は明日入院するとのことだった。林田には実際に民宿に泊まってもらい、これからの民宿のあり方、経営について相談にのってもらうつもりだった。
思い起せば島崎も林田も緑川も全共闘世代だ。3人が一緒にいると学生時代に戻る。大学では同じ社会思想史のゼミの仲間だった。疎外論とか理念型、エートスなどという哲学的問題で議論に明け暮れた思い出がある。当時は自分がその難しい問題をどこまで理解しているかということを相手に分かってもらうために延々と話したものだ。3人とも社会に出てそれぞれの職業について社会の荒波に揉まれてきた。お互いの意見、考えを柔らかく受けとめることができるようになっているが、それでも議論が始まるといつの間にか熱を帯びていた。
島崎は屋上緑化事業を手広く手掛けていた。これから都市の環境問題が大きなビジネスチャンスになると見ていた。島崎は起業家精神に溢れた、まさに経営者だった。40歳過ぎ迄大手の重工業会社でエンジニアとして仕事をしていたが、脱サラして環境関係の事業を起こした。環境機器と屋上緑化を事業の2本柱にしていた。樹木、芝生、花を中心にした屋上緑化が今後都市部で拡大していくと読んでいたのだ。
緑川は父親の後を継いで土木建築資材を建設会社に販売する会社を、10年間ほど経営していた。いろいろな新規事業を立ち上げたがことごとく失敗。売上が一時は50億円迄いった会社に見切りをつけ自主廃業を決断し、約1年間かけて完了した。一歩間違えると倒産という崖の上の細い道を歩き続けるという極度の緊張を強いられた。自主廃業を完了後、暫くの間虚脱状態に陥っていた。その後声を掛けて頂いて2つの会社の営業顧問的仕事をしていたが、時間もあるので気分転換も兼ねて野菜作りを農家から畑を借りて始めた。もし農作業をしていなかったらウツ病になっていたかもしれない。自分の人生には一体どのような意味があるのか、まさに実存的空虚感の底に落ち込んでいった。
自分で栽培して自分で食べる。販売するために農作業をするわけではないので、無農薬、無化学肥料の有機的栽培に取り組んだ。野菜作りをしているといつの間にか無心になれる。何も考えずに無意識で作業している自分がいた。それだけでも救われた。
それから2年後、緑川は久しぶりに島崎と会い、島崎の屋上緑化事業に関わることになった。島崎の会社は屋上用の軽量土壌を開発していた。この土壌の主な用途は芝生と樹木、花用だった。緑川は島崎に勧められて、この軽量土壌を使った野菜栽培に取り組んだ。芝生と違って薄い土で野菜を育てるというのは簡単ではなかった。試行錯誤、失敗の連続だった。
当時は屋上で野菜をつくるというのが珍しかったせいか、メディアにも取り上げられたが、小さなブームはアッという間に去っていった。
屋上菜園は事業として取り組むにはいろいろな問題があった。環境対策として屋上に芝生を張ったり、樹木を入れたりするケースは増えていた。一方屋上菜園は手間がかかる。特に都市部の屋上になぜ屋上菜園を設置するのか、その積極的意味が求められるが、当時は説得力のある意味付けがなかなかできなかった。屋上菜園を設置することは設備投資を伴い、また野菜を栽培するのだからそれなりの栽培費もかかる。それだけおカネをかけてどんな見返りが期待できるというのか。企業の本来の事業にとっての経済的貢献が期待できないのであれば、屋上菜園の意味はなくなる。この問題が緑川を苦しめ続けた。
緑川は夜空を見ながら呟いた。「あの時は・・・ずっと屋上菜園事業では食べていけない。しかしなぜか都会の屋上での野菜栽培を自分は諦めることができない。自分をウツ的状態、さらには深い空虚感から救ってくれた野菜達が何かを自分に託しているのかもしれない。自分がこれからの人生を生き続けていくためには野菜達と離れてはいけない。そんな声もどこからか聞こえてきた。これしかないのかもしれない。もし諦めたらこれからの人生、一生後悔するかもしれない。」
幸いある大きな商業ビルの屋上菜園での栽培作業を緑川が参加していたNPOが仕事として受注することができた。この屋上菜園での仕事がもし無かったら、緑川の屋上菜園事業は全くどうなっていたか。・・・途中で緑川が属している団体がNPOから一般社団法人に変わったが、栽培管理契約は継続した。
その商業ビルの屋上菜園の栽培管理を2008年からはじめたので既に10年以上続けてきたことになる。「あれからもう11年か。いろいろあったが、アッという間のような気もする。屋上菜園で忘れがたい人々との出会いもあった。一期一会的出会い、ご縁だったがそれらの人々との出会いも研志に屋上菜園事業を続けさせる力となった・・・。この仕事は文字通り社会の片隅の仕事だ。顧みてくれる人は限られている。まさに小さな一隅を照らす仕事だ。それでも屋上菜園を愛してくださる人々がいる」
緑川は60歳の時から年金受給者になった。贅沢をしなければやりたい仕事ができる。
林田は大学卒業後経営コンサルティングの会社に入った。会社では問題解決手法と経営計画づくりの専門家として活躍してきた。60歳の定年退職後は自営で10年以上コンサルティングの仕事を続けてきた。現在は小さな会社の事業計画案作成を手伝い、伴走者として相談に乗っている。ただ林田は心臓に持病を抱えていて無理はできない身体だ。
翌朝、緑川は午前7時頃に起きて民宿の近辺に散歩に出かけた。住宅の間の坂道を下りていくと川の水音が聞こえてきた。川の上流の方に歩いていくと大きな滝が見える。人工的に作られた滝だ。暫く滝を見た後、踝を返して川の下流に沿ったゆるい坂道を歩いていった。農家の婦人が畑でしゃがんで青紫蘇を収穫している。ひとしきり歩いた後、民宿に戻った。食事迄の間、読み続けている本を30分ほど読んでから食堂に降りた。朝食をとるのは研志だけだ。
8時半にS商会のSさんが迎えに来てくれた。S商会の皆さんに会うのは半年ぶりになる。
何か親戚の人々と会っているような気さえする。
S商会は家族経営の会社だ。早速専務と打ち合わせに入る。打ち合わせは昼前迄続いた。S商会も会長から長男Kさんへ経営のバトンタッチを進めている。専務になったKさんが頼もしくなってきている。彼の、さらにはS商会の皆さんの期待に応えるためにも研志は自分にカツを入れた。「頑張らなくては・・・自分に残された時間も少なくなってきている。」
内船駅までKさんに送って頂き、甲府行きの各駅の電車に乗った。遥かに聳える山々を見ながら研志はこれからのことに想いを馳せていた。
自分は11年間、屋上菜園の仕事をやってきた。続けてこれたのは何よりも妻の理解と協力だった。儲かりもしない割に手間がかり苦労の多い仕事、と思ったこともあったことだろう。研志はのめり込むタイプだ。「やめて」といっても聞かないだろうと諦めていた部分もあったのではないか。
人にはそれぞれ持ち場というものがある。研志は自分の居場所、さらには持ち場を探し求めていたが、なかなか見つからなかった。ある時、一つの詩に出会った。
あなたの持ち場は小さいか
心してそれを守りなさい
あなたの持ち場は大きいか
心してそれを守りなさい
あなたの持ち場が何であれ
それはあなただけのものではない
あなたをそこに置かれたかたのものである
研志は「今、ここ」、屋上菜園こそ自分の持ち場であると思い定めた。野菜の神様が自分を屋上菜園に置いてくださったのだ。その方は「私はあなたと共にいる」と言ってくださっている。そんな風に信じることができた。
11年間やってきてやっと屋上菜園への根本的問い、「屋上菜園は企業の本来の事業にとってどんな経済的貢献が期待できるのか」が見え始めてきている。研志は業務用として、商業ビル、マンション、事務所ビル、老人ホームと4つの分野に分類した。分野ごとに貢献内容が違う。それぞれの分野ごとに実績、事例が増えてきているので、いずれビジネスモデル化しようと準備に入っている。
11年間、屋上菜園に仕事として取り組んできて研志の中で大きく変化したことがある。
ちょっと大げさに言えばコペルニクス的転回だ。齢をとり、残された人生が少なくなってきた高齢者特有の思いかもしれない。
一つ目はこれからの人生で、人生から何を期待できるか、という思いが消えて、私と私の大切な人々の人生に対して自分はこれから何ができるか。
二つ目は今迄明日のために、未来のために今日自分は何をすべきか、何をしなければならないか。さらに言えば現在を未来のための踏み台、通過点と考えていたが、現在は「今、ここを生きる」。未来は「今、ここを生きる」の積み重ねの結果としてある。「今、ここを生きる」が一番大事。
三つ目は本から現実へ。本を読むことは大切だが、本の世界にとどまるのではなく、現実に向き合い、現実の中で生きること。研志はある日、電車の中から郊外に広がる町の風景を見ていた時、瞬間的に自分の生きてきた文字の世界の殻が破れて現実の世界に置かれたように感じた。生きているという実感がした。そして現実世界が愛おしく思えた。
野菜栽培が研志に生きることのリアリティを回復させてくれた。そして居場所、持ち場を与えてくれた。これからの残された人生、野菜の神と共に歩いていくことだろう。
そして最後に願うことは研志のバトンを受け取って次の走路を走ってくれるランナーが出てきてくれることだ。
一隅を照らし続け、幸せな社会を拓くために。
右手方向に雨ヶ岳の高い頂が見える。これから甲府盆地に入っていく。雲間から太陽の光が地上に降り注いでいる。
「生きること、生き抜くこと、それがどんなに平凡な人生に見えても。野菜の生き方に見習いながら生きること」。研志は車窓の外の流れる光景を見ながら、そう自分に言い聞かせていた。いつの間か微笑みが浮かんでいた。
(完)
あとがきに代えて 「菜楽」のススメ
人は何かを始めても続けていくことがなかなかできません。たとえば健康のために運動しましょうと言われたとしたら、早速始める人は何人かいることでしょうが、続ける人はガクンと減るはずです。「今日は疲れたから、時間がないから、その気にならないから…」理由はいろいろでしょう。
私自身がそうです。健康のために毎日3種類の運動(スクワット、腕立て伏せ、腹筋運動)
をすることにしていますが、全部できたという日は殆どありません。スクワットだけでもするようにしていますが、10回3セットの目標を実現することはめったにありません。途中で止めたりしています。いい加減ですね。
運動学の先生が楽しく身体を動かす「動楽」をススメていますが、どのようにしたら運動が楽しくなるのか、具体的なことは残念ながらあまり書いていません。楽しみ方は読者が自分で工夫して考えるように、ということでしょうか。
さて最近はマンションのベランダで、自宅の庭で野菜を栽培する人が増えてきました。ホームセンターに行きますと、野菜栽培のための土壌、肥料、資材、苗、種が大量に並べて置いてあります。野菜栽培愛好人口は確実に増えています。
野菜栽培を愛好する人達に、私が是非おススメしたいことは「野菜づくりを楽しむ」ということです。野菜栽培に遊び心を加える。私たち日本人はどうしても真剣に物事に取り組んでしまいます。それがあったからこそ、現在の豊かな日本があるのでしょうが、これからは経済的な繁栄だけでなく、人生を楽しむ気持ちと時間をもっと多く持ちたいものです。
私は都会の皆さんにあらゆるシーンで野菜生活を楽しんでほしいと願っています。音楽を楽しむように「菜楽」を日常生活の中に、さらには仕事の中に取り込んでいって頂きたいのです。そうしますと毎日の生活が少しずつ変わっていきます。またパソコンの前に座って仕事をすることが多いビジネスパースンの皆さんにもまたとない気分転換、リフレッシュの時となります。
音楽、動楽、そして菜楽。もっともっと人生を、仕事を楽しみましょう!特に菜楽はそれほどおカネもかかりません。野菜との対話も楽しんでください。
皆さんが野菜生活を楽しむ中で、皆さんご自身の「菜園物語」が生まれることを願っています。
(全完)読みいただき有難うございました!