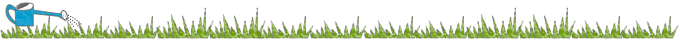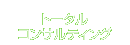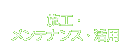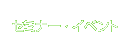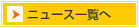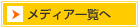欅風-江戸詰侍青物栽培帖
時代小説「欅風」の読者の皆様へ
いつも欅風をお読みくださり、ありがとうございます。
途中何回が中断し、皆様にはご迷惑をお掛けしました。
最初は30話で執筆をスタートしましたが、結局70話迄
書くこととなりました。
63話は6月20日にアップされ、これから毎週金曜日に1話づつ
アップされていきます。最後の70話は8月15日にアップ予定です。
既に69話迄書いています。
最後迄お楽しみ頂けたら幸いです。
作者 阿部 義通
第62話 千恵とおしの
千恵は波江にとって娘であるばかりか歳の離れた妹のようでさえあった。千恵は波江の農作業と寺子屋のために独特の働きをするようになった。農作業では子供達のまとめ役になって手順を子供達に話すのだった。
「今日は土の耕転よ。こんな風に土を掘ってひっくり返す。その前に一昨年の冬準備した 腐葉土を土の上に撒いておきましょう。本当は一尺ほど深く掘って耕転すればいいんだけど子供の私達には無理だから、半尺でもいいわ」
子供達は今日耕転する予定の場所にそれぞれ散らばり、袋に入れた腐葉土を撒いていく。
「腐葉土は土をフカフカにするのよ。それにミミズも腐葉土の中で増えて、畑に入ると畑の土をどんどん良くしてくれるの」
「千恵ちゃんは何でそんなことを知っているの」
「お母さんが教えてくれたの。晩御飯を食べている時にお母さんが教えてくれるのよ。お母さんは母屋の叔父さん、叔母さんから教えて貰っているって」
寺子屋が始まる時は千恵が皆に声をかける。
チリン、チリンと口で言いながら「寺子屋が始まりま~す。皆集まって」
千恵は波江が教材を準備し、筆、墨、紙を準備するのを手伝った。
慈光和尚の朝のお勤めも波江と一緒だった。ある日お勤めの後、千恵は慈光和尚にこんなことを尋ねた。
「私のお母さんは食べ物がなくて、最後は食べる力が無くなって死んでいきました。私を連れて江戸に出てきてから辛いことばかりでした。私はお母さんを大川の水辺から川に流しました。それがこの世での別れでした。でもお母さんは見えませんがいつも私の傍に居てくれるような気がします。この世とあの世はどこかでつながっているように思うのですが、和尚様はどのように思われますか」
慈光和尚は微笑みながら言った。
「拙僧も千恵ちゃんと同じ思いだ。私達は自分達だけが生きているように思うが、そうではない。死んだ人達は、姿は見えないがその思いが私達と共に生きていて、守ってくれていますのじゃ。」
千恵は嬉しそうに言った。
「おばちゃんと私はいつもお母さんと一緒に食事をしているの。おばちゃんと私とお母さんの3人分の食事を準備して食べているんです。」
「それは賑やかでいい」
波江は和尚に顔を向けながら、
「和尚様、ありがとうございます。和尚様にそう言って頂いて、さぞ嬉しかったことと思います」
さて狭野藩領内の叡基の寺に文が届いた。郷助が息子孝吉を連れて大阪、堺に行くのでその際、叡基の寺を訪ねたいとのことだった。郷助の旅行の目的は大阪、堺に義手、義足そして車椅子の作り方について説明したポルトガルとオランダの本があると聞いてのことだった。大阪、堺には外国語が分かる通詞もいる。その人達が生きているうちに本を手に入れ、話を聞いておきたい、郷助はそう思った。準備には1年の歳月が必要だった。本を購入するための費用、旅にかかる費用、通詞への謝礼。全部を合わせると郷助にとっては大変な金額になった。次郎太は兄のために特別の講をつくり、仲間から金を集めてくれた。
郷助は将来のことを考えて孝吉を連れていくことにした。タケも次郎太も才蔵も賛成してくれた。
大阪、堺と回って郷助親子が叡基の寺にやってきた。叡基が朝明川の普請から一時戻ってきた時だった。
「叡基様、お久振りでございます。大川の普請では大変お世話になりました。こちらは倅の孝吉でございます」
孝吉が挨拶する。
「叡基様、孝吉でございます。父が大変お世話になっております」
叡基は言った。
「郷助さん、お元気そうで何よりです。この度は義手、義足そして車椅子の件で大阪、堺に来られたとか。求めていた書物は手に入りましたか。」
郷助が嬉しそうに答えた。
「首尾よく手に入りました。つくり方については絵が沢山載っておりますので、ポルトガル語、オランダ語が分からない私にもおおよその見当がつきます。やはり南蛮ではこの方面の研究が進んでいます。学ぶことが山ほどあります」
「そうですか、それは良かった。むさくるしいところですが、とうぞゆっくりしていってください」
そこにおしのが茶を運んできた。叡基が紹介する。
「おしのと言います。元は江戸の近くに住んでいましたが、私が大川の普請をした際、縁あっておしのを知ることとなりました。おしのには兄同然の元吉というものがいましたが、郷助さんもご存知のように地震があった時、普請現場に落ち、命を落としてしまいました。普請が終ってからは私が引き取って、狭野につれてきて私の娘のようにして、一緒に暮らしています。」
おしのは郷助と孝吉に頭を下げて、挨拶した。
「おしのといいます。こちらにご滞在中は私がお世話をさせて頂きますので、何なりとお申しつけください」
その夜はおしのの心のこもった料理の数々が食卓に並んだ。
孝吉が聞く。
「これ全部おしのさんがつくったのかい。すごいなあ」
叡基が言う。
「料理だけじゃないんだ。材料の野菜も全部おしのが畑でつくった。おしのは本当に働きものだ。私も随分と助かっている」
叡基と郷助は酒を酌み交わしながら話している。大川の普請の話だ。
「叡基様。狭野藩が普請したところはこの間の台風の時もビクともしませんでした。ところが隣の工区の堤は他の藩が普請したところですが、一部が波で抉り取られ大変な問題になっています。さすが狭野藩の敷葉工法はすごい、と評判です。」
「いやいや郷助さんが送ってくれた村の衆が本当に良い仕事をしてくれました。そのお陰ですよ」
大人達二人の話を聞いていた孝吉がおしのに聞く。
「どこの生まれなんだい」
「深谷よ」
「どうして江戸に」
「別れ別れになった兄さんが江戸の普請場で働いていると風の便りに聞いたの」
「それで江戸に」
「でも兄さんには会えなかった。どこかで生きていると思うけど。探しているうちに元吉さんに会ったの。元吉さんは厠掃除の仕事をしていた。私も手伝って一緒にやったわ。
そして叡基様の普請現場でも厠掃除の仕事をした。元吉さんは叡基様のお役にもっと立ちたい。それで現場と普請小屋との連絡の仕事を頂いて、始めた矢先に地震で足を滑らしてなくなってしまったの。元吉さんのお墓が、あそこに小さな石が立っているでしょ。あそこに叡基様がつくってくださった」
孝吉は元吉のこと、おしの兄のことを思いながら雲が流れる空を見上げた。
第61話 氏安 幕閣に入る
朝の評定では家老が進行役を勤める。お役目の者が一人一人報告、説明をする。その際、氏安は丁寧に話を聞くよう心がけている。
「塾について準備作業が進んでいることを嬉しく思う。ところで塾で使う教材はどのようにして準備するのか」
役目の者が答える。
「教材は師範として選ばれた者にそれぞれ準備させる所存です。それぞれの師範が本分に基づいて考え抜いたものをそれぞれ作成すれば良いと思います。まだ始めの段階ですし、いろいろと試していくなかで、自ずから相応しいものが出来上がってくると存じます」
氏安は評定に出ているものに、必ず一言言わせるようにしていた。そして全員の意見を聞いた上で結論を出すようにした。見解が別れた時は再度評定する、ということで評定に出ている者に考えさせた。
氏安は言う。
「見解が別れるということは、まだ全体が見えておらぬということだ。またわれわれの考えがまだまだ浅いということではないかな」
氏安は側室であった母の教えをいつも胸の奥底に抱いていた。母は自分が言うことに対し、「それは違います。正しいのは・・・」とは言わなかった。自分が考えたことは幼かったり、明らかに間違っているようなことでも、「そうですか。なるほどそう考えたんですね。その理由はなんですか」。自分の考えを聞いた後で、考え込む母がいた。母はある時、このように言ったことがある。
「人は自分の言ったことを頭から否定されるとまるで自分自身が否定されたように思うものです。そのようなことが続くといつの間にか、人は自分で自分のことを信じられなくなります。そしてあなたを遠ざけたり、更には憎んだりするようになります。ですからあなたも心してください。人を柔らかに受け止める。言葉は刃にもなり、温かい気持で差し伸べる手にもなりますよ」
氏安は忠誠、奉公という精神的姿勢を否定しているわけではなかった。しかし「殿様、殿様」と朝夕藩主をあたかも神のように唱え、崇める行き方の中に危険な匂い、さらに言えば狂気を感じていた。藩主は神のような存在ではないのだ。
評定が進む中で、塾のそれぞれの名前が決まっていった。武士の塾名は「護民塾」農民の塾名は「国柱塾」工人の塾名は「国富塾」そして商人の塾名は「流通塾」。師範の中から互選で塾長を選らんだ。塾が目指すことは一つだった。「新田開発よりも人材開発、人材興国」
師範が決まり、塾長が決まり、塾名が決まった後、直ちに受講生の募集が始まった。
1.老若男女別なく受講できる事
2.途中で入塾し、途中で退塾できる事
3.男女については仕切りを設ける事
4、受講料は無料とする事
5.期間は1年間とする事
氏安が期待した通り、直ぐに塾は定員を満たした。
これは塾であった。師範は自分がつくった教材に基づき講話をし、講話の後は必ず質疑応答を行なった。そして師範から必ず宿題が出た。宿題は領民の生活、仕事に根差した「たとえ話」が多かった。それぞれの師範が物語づくりに知恵を絞った。
「ある村に戦で怪我をした者がおった。左腕を刀で切られ、右手一本になってしもうた。 畑に出ても両腕があるものには敵わん。そのうちこの者は、俺は役に立たん。皆の足手まといになる。それにゴクつぶしだ。いっそ死んでしまおうか、と考えた。さて皆さんがこの者の兄者だったら、また母親だったらどうするか」
一番受講生の多い「国柱塾」で師範から以上のような宿題が出された。師範は言う。「これが正解というものはない。皆さんがそれぞれ考えたことが正解なのだ。次回はその正解をお互いに披露し合うことにする」
「護民塾」でも「国富塾」でも「流通塾」でも同じように、自分の問題として考えられるような宿題が出された。狭野藩の領民の間で塾のことが皆の口に上るようになった。
「俺も塾に行きてえ」
塾は日中の仕事が終ってから開かれた。労働の疲れのためだろうか、居眠りしているものもいる。中には鼾をかいているものも。あまり鼾がひどいときはつついて起こすが、そうでもない時はそのままだ。また塾に遅れてくるものもいる。そのような時、師範は言う。「よく来てくれた。仕事は片付いたか」
仕事の後、勉学に励むということは容易なことではない。日中の労働で農民、工人、商人は疲れている。塾の学びは楽しく、また実際に役立つものでなければならない。そうでなければ続けていくことは難しくなる。
武士達は日中それほど忙しくないので、農民、工人、商人の仕事の大変さが分からないということもあろう。狭野藩では武士も月に1回、それぞれの希望で農民、工人、商人のそれぞれの職場に行って働くことが奨励された。
それぞれの塾が軌道に乗る迄は時間がかかることだろう。狭野藩百年の計なのだからじっくり取り組んでいけば良い。願うことは学びの裾野を拡げることにあった。裾野が広がり、大きくなれば、自ずから頂きも高くなっていく。領民に支えられて、優れた者が輩出し、狭野藩の将来を担っていく人材が現れることを氏安は期待していた。
時期を見て、大阪、京都、堺から優れた先生に来て頂いて、講話をしてもらうことにしよう。師範にとっても、受講生にとっても啓発されるまたとない機会になるであろう。
日々の報告も因果関係をはっきりさせて行なうようにしてから、短時間で済むようになった。評定は一刻迄として、それ以上時間をかけないようにした。
ある日江戸城の土井利勝より書状が届いた。直ぐに登城するように、と書かれていた。氏安は旅装に着替え、直ちに江戸表に向った。江戸屋敷の徳田家老を伴い、江戸城の内桜田門に出頭した。
「こちらにどうぞ」と促されて城内に入った。案内されたところは黒書院の控えの間だった。待つともなく土井利勝が出てきた。土井は柔和な顔に笑顔を浮かべ、氏安に声をかけた。
「変りないか。桑名44村の建て直しの儀、しっかり頼むぞ」
その後で、これは殿からのご下命であると前置きして、
「貴公に御料地担当の役目を命じる。」
氏安は幕閣の一人に加えられた。
黒書院の中に人の気配があった。
第60話 狭野藩改革
狭野藩は1万石余のまことに小さな藩だ。領地も狭く、当然石高も少ない。氏安は考えた。小さな藩はどのように生きていったら良いのか。日夜考えつづけた。そこで得た結論は小さな藩だからこそできることを見つける、小さな藩しかできないことを実行する、ということだった。氏安は、藩は地産地消、自分達の力だけで藩の経済を守り、廻していかなければならないことをいつも自分に言い聞かせていた。誰も助けてはくれないのだ。それどころか幕府は一方的に藩に普請を冥加金を言いつけてくる。藩が疲弊するギリギリ迄追い詰めてくる。それを凌がなければならない。
そして考えたことを先頃叡基の寺を訪ねた時、氏安は叡基と一緒に散策した折、話を切り出した。
「叡基殿、貴殿はこの徳川の世をどのようにお考えでしょうか。信長様は才あるものを身分にかかわりなく取り立てられました。秀吉様は農民から信長様に取り立てられて出世され太閤殿下にまで昇りつめられましたが、徳川の世ではもはや農民が武士の頂点に立つことなど叶わぬ夢、ということになりました」
叡基は周囲を見渡した後、低い声で言った。
「能力があれば身分にかかわりなく出世できるという自由な時代は終りました。士農工商という新しい身分制度は、武士は武士らしく、農民は農民らしく、工人は工人らしく、そして商人は商人らしく、それぞれ身分を弁えて身を処することを眼目としております。要するに幕府のご法度、思し召しの下で四民がそれぞれ役目を持って世の中を支え、守っていく、武士は政事を持って社会の秩序を守る。農民は必要な食糧を生産する。工人は生産と生活に必要な道具とか品物をつくる。商人は品物を動かす。そこには極めて厳しい身分の別、主従関係がございます。武士以下の三民は皆武士に従わなければなりません。武士と三民の間には超えることのできない深い淵があるのです」
「日ノ本という国全体をまとめ、二度と戦乱の無い世にするためにはそれが良いのでしょうが、三民は皆武士に申し立てることは出来ず、また将軍は思いのままに政事を進める、ということになりますが、本当にそれで世が治まるものでしょうか。民が安心して暮らせる世の中になるのでしょうか」
叡基は暫く考え込んでいたが、氏安の問いには答えず思いもかけない話を切り出した。
「『大般涅槃経』の中に阿闍世王子の話が出てきます。王子は父王を殺し、母親を獄に幽閉して王位を継いだ人物です。王子は自分の罪におののき6人の大臣を訪問して意見を聞きます。6人の大臣の最後の吉徳は、武士(王種)は国土を守るために政治を行なうので、そのために父王を殺しても罪に落ちることはない、と答えます。6人の大臣は結局、殺人を仕事とする武士階級にはもともと殺人罪はありえない、という結論では同じでした。従い武家の法と世の中一般の法とは全く別のものということになります」
「ここ日ノ本でも武家の行なう政事は常に殺人を正当化する、ということなのでしょうか」
「そのようにお考えになってよろしいかと存じます。武家が行なう政事ではいつもそのことを覚悟しておかれることが肝要です。氏安様は阿闍世王子とは違いますが、今の世の政事はそのような闇と牙をその奥底に持っていることを片時もお忘れなきように。徳川の御世にあって主従関係はかつてのように戦場であったものとは異なります。武家が支配する権力は、いつも戦場でなくとも最後は権謀術策の果て、暴力的な力で決着をつけるという本性を現すことになります」
氏安はうめくように言った。
「私が目指している政事はそのようなものではありませぬ。身分を弁えつつも狭野藩の領内で生きる者が、四民がそれぞれ人として自分の道を歩き、互いの道を尊び、力を合わせ、それぞれの務めを果たし、幸せになることなのです。そのような政事はできぬものなのでしょうか」
叡基は雰囲気を和らげるように言った。
「氏安様。お気持は私にも痛いほど分かります。さて日ノ本を治めるのと狭野藩とでは事情は異なります。殿の思いはこの狭野藩であれば叶うことかもしれません。幕府の身分制度の枠組みの形はそのままにして、中身を変える、というのはいかがでしょうか。確かに一万石の狭野藩は、領民それぞれに力を大いに発揮して貰わねば、いずれ頭打ちとなり、更には立ち行かなくなるやもしれません」
氏安は言った。
「私は理想を追い求めている訳ではありません。確かに身の丈と言う考え方がありますが、領民が本分を尽くし、互いに協力し合えば、少なくとも狭野藩の実力を今の2倍、2万石にできると信じているからです。そうすれば凶作、飢饉などの波風に耐えられる藩にする、それが藩主である私の本分、務めと考えているのです」
「殿は本分を尽くし、互いに協力し合えば、と言われました。私もその通りであると思います。是非狭野藩をそのようにして頂きとう存じます」
叡基は思った。氏安様はまだ若いけれど、心が円満で考え方も成熟しつつあると。理想を求める思いも確かなものだ。しかしながら考えと思いが過激に走ることがないよう、お支えしなければならない。
叡基は3つのことを氏安に進言した。
・狭野藩の領民のためにそれぞれ塾を開設すること。武士のため、農民のため、工人のため、商人のため
・人材を能力だけではなく人柄も含めて総合的に評価し、起用すること
・物事の報告に当っては因果関係をはっきりさせて話をさせる、また文書を書かせるようにすること
叡基は一つ一つ説明した。
「四民にはそれぞれの道があります。何のために自分は武士なのか、何のための自分は農民なのか、何のために自分は工人なのか、何のために自分は商人なのか・・・その本分を学ぶことが大切です。四民には四用があります。どれ一つ欠かすことはできません。
塾の師範は、それぞれ武士は武士の中から、農民は農民の中から、工人は工人の中から、商人は商人の中からこれはと思うものを数人選び、師範のお役目に付かせるのが良いかと思います。大事なことは人格的陶冶であり、実学実用です。
人を見る時には能力だけではなく人望も見なければなりません。どんなに能力があっても人がついていかなければ何事もできない、ということになります。勿論無能では、人はついてはいきません。ただ私は無能の人間はこの世にいないと信じております。領民一人ひとり、機会を与え、その得意なところ、美点を引き出し、それに確かな人格が加われば半円ではなく円満な人となります。
最後に因果関係です。すべて原因があって、結果があります。この考え方は重要です。報告する者もされる者も正確に事態を掴み、適切な手、解決策を講じることができるからです。但し落ち度があった時、誰に責任があるか敢えて問い詰める必要はありません。それは当の本人が一番良く分かっていることでしょうから。
氏安は叡基が自分の思いを確かに受け止めていることに内心感激し、言った。
「叡基殿。進言の一つひとつ、頷くことばかりです。私の中で十分に反芻して、自分のものにした後、狭野藩の政事に活かしていきたいと思います」
叡基は頭を下げて言った。
「大変差し出がましいことを申し上げました。どうぞ殿がお考えをまとめる際のご参考になれば幸いです」
氏安は叡基との話合いを日々自分の中で反芻していた。
氏安は夢を見た。まだ部屋住みであった頃、狭野藩領内の領民と世間話をしている夢だった。どんな世間話をしていたか、残念ながら思い出せないが、何かとても楽しかった。早朝の床の中で、暫し余韻に浸っていたが、直ぐに寝間から出て野良着に着替え、藩邸の中の畑に出た。農作業をすることが氏安の日々の勤めになっていた。「今日も天気が良い。畑日和だ」。文字通り朝飯前の農作業を終えて、氏安は朝餉をとった。茶を一服してから毎日の朝の評定がある。
第59話 桑名村の天岡組と朝明川の叡基組
天岡は桑名村の大庄屋と話し合いを重ねていた。米の生産を安定させることと、良質の米を増産することが話し合いの中心であった。天岡は桑名村44村に米作りの名人を一人推薦するように手紙を書いた。2ヵ月後霜月の晦日に、桑名の大庄屋の屋敷に集まるようにと認めた。それぞれの村では寄り合いが始まり、自分達の村で誰が米つくりの名人か、選ぶための話合いが続いた。最初は内輪で揉めていたが、そのうち対抗意識が生まれ、「他の村には負けられねえ」と言う気持が高まり、村の代表、米つくり名人が次々と決まっていった。
44村の米つくり名人が集まった日、天岡は大庄屋の大屋敷で、皆を前にしてこのように言った。
「今日はわざわざ起こし頂き、こころからありがたく思っております。皆さんの力でこの桑名村を米づくりで日の本一にしようではありませんか。私どもは幕府から御下命を受けてこの桑名村のために粉骨砕身取り組む所存でございます。皆さんが一同に顔を合わせるのは今日が初めてですから、まずは固い話はこれまでにしてお互いを知るため、夕餉を一緒にしながら、歓談の時を持つことにしましょう。今晩はこの大庄屋さんと周りの農家にお宿を提供して頂くことになっています。夕餉までまだ時間がありますので、庭に狭野藩で開発した農機具などを並べておりますので、ゆるりとご覧ください」
各地の米つくりの名人はぞろぞろと庭に出て、農機具を見た。庭には稲の苗を一定の間隔に植えるための竹と紐でつくった田植え縄、この縄は苗を一定の間隔で植える(正條植え)ために役に立つ。しろかき用の馬鍬、回転式の刃のついた除草機、脱穀用千歯、籾すり用の臼、唐箕くり、千石どおし、米穀検査用の刺し。
「正條植えができるこの道具は、ウチの田圃でも使いたいね。これはいい。今迄草取りが大変だったんだ。正條植えをして、この除草機を使えば四つんばいになって草取りをしないで済む」
「この唐箕くりは右手でここを掴んで回して風を起こすのか。風の力で米と籾と籾殻を分けるのか」
「狭野藩では農民と工人が互いに助け合っているようだ。農民がこんなことで困っている、こんなものが欲しいと頼みごとを持ち込んでくると、工人が知恵を絞って創意工夫し、新しいものをつくっているのだろう」
名人達は熱心に狭野藩の農民と工人が合作した農機具を見て回っていた。中には動かすものもいた。
夕餉は贅沢なものはなかったが、地元で取れた野菜に、桑名の港から上がった魚を料理したものが出された。地元の女将さんたちが腕を振るってつくった料理だった。酒も出された。
夕餉が終った時を見計らって、天岡は名人達を前にして言った。
「まことに宴たけなわですが、遅くなりましたので、そろそろお開きにしたいと思いますがいかがでしょうか。最後に私の方から皆さんにお話があります。2つです。
一つは皆さん、それぞれの地区の米作りの名人です。いかがでしょうか、互いに切磋琢磨するために、桑名44村、米つくりで競い合ったらどうでしょうか。そして年1回米づくりの品評会を開いて1番、2番、3番、努力賞という順番で表彰します。
もう一つは農機具の改良です。使いやすく、安全で、しかも能率の良い農機具を皆で開発していきませんか。桑名村の工人の皆さんにも相談相手になって頂いて、もっと沢山の米をつくろうではありませんか。勿論、狭野藩の工人もお手伝いさせて頂きます」
名人達は暫く黙っていたが、次々に手が上がり、「いい考えだ。やりましょう」声が相次いだ。
天岡は頭を下げてから言った。「それでは皆さん、米づくりの品評会、農機具の改良の件、ご賛同頂きありがとうございます。詳しいことはこれから詰めていきますが、進めることに致します」
夕餉の後、名人達は組に分かれて、周りの農家に散っていった。それぞれの農家で話の続きがあることだろう。みんなで一同に集まる、そして小さな組に分かれて一晩語り合って親睦を深める。こうして桑名44村の農民が力を合わせることができれば、桑名村の再建は軌道に乗るはずだ。明日名人達が帰った後、天岡は農家一軒一軒を訪ねて一夜の宿代を払うことにしている。そして大庄屋の屋敷で開いた夕餉の食事代も、関ってくれた人達に払う約束になっている。天岡は自分の宿に戻ってから帳簿を開き、費用を書き込んだ。どうしても米の増産は必要なのだ。まだ桑名44村の者は知らないが、交通の要所桑名の宿場を守るために助郷制度が更に強化される。村々の負担はそれだけ大きくなるのだ。そしてふと思った。昔の自分であれば、このように平たい心で、農民に接することはできなかっただろう。天岡は出世を鼻にかけ、人を人とも思わなかった時の自分を思い出していた。あのことがなかったら、自分は変ることができなかった。またあの人で出遭うことがなかったら。
手もとに寄せた蝋燭の炎がどこからか吹いてきた風に激しく揺れた。
朝明川の洗掘個所に叡基は立っていた。河床の地盤の弱さが問題だった。その上に堤を築いても沈下したり、あるいはヒビ割れたり、ひどい時には傾いたりすることだろう。どこに松杭を打ち込むか決めなければならない。暫く川面を見ていた叡基が呟き始めた。
「あの線に松杭を2尺間隔に30間打ち込むとすると・・・一列で90本。3列打ち込むと270本。それにしても長さ3間の松杭を船の上に立って打ち込むわけにもいくまい。30間、3列の松杭を打ち込むために足場を川の中に2間毎に設けることになる。仮設足場にためなら松の間伐材を使えばいい。松杭を打ち込んだ後、杭と杭の間の横板を隙間無く乗せ、まず砂利を播き出し、それから敷き葉工法で土と葉を重ねいく・・・。叡基は地元の古老、農民数人を作業班の中に入れ、話を聞いていた。叡基の頭の片隅には武田信玄の千曲川普請のことがいつも規範のようにしてあった。
「ここがひどく洗掘されるのは少し上流の方で川がひどく曲がっているためですだ。曲がりの角度を少しゆるやかにしたら、ここにドーンと当る衝撃も少しは軽くなるはずです」
ある日叡基は作業班の古老、農民と一緒に、上流の川も傍らに立っていた。
「なるほど、そういうことか」
川の流れを付け替えることは簡単なことではない。農民には代替地を世話しなければならないし、また自然の力が造った従来の堤を崩し、新しい堤をつくり、川底を掘り上げるには当然膨大な費用がかかる。
叡基は思案した。その場所は堤が決壊して氾濫する場所ではないので、必要が出てきたら第二期工事とする。当面はそこに大石を投げ込み、大石に川の流れを受け止めさせ、堤を守ると同時に流れの角度を少し変えて緩やかにする、ということにした。
叡基は作業班の者達を集め、工事の進め方について説明した。作業方針は安全第一。正確工事。作業の段取りを決め、資材の調達時期、費用などを決めた。
叡基は自分に言い聞かせた。「さあこれからいよいよ始まる。川のこころになって堤を築こう」
第58話 狭野藩の殖産事業の発展
米の藩内価格を設定してから農民は安心して米づくりに励むようになった。自分たちがやるべきことは病虫害から稲を守り、天候不順から守ることであった。増産すればそれが自分達の実入りになり、また藩の方では年貢米と買い上げた余剰米を藩の運営、藩士への支給さらには不作の折の備蓄にまわしていた。米は藩の収入の土台となっている。狭野藩だけではなくどこの藩も事情は同じであった。農民の側もそれぞれ農事講をつくり、品種改良に努めている。以前はその積立金もままならなかったが、今はそれができるようになった。講の時の農民同士の話だ。白髪混じりに年配の農民が言う。
「この間やってきた堺の薬売りがこんなことを言っておったわ。・・・米の藩内価格制で、狭野藩の藩民は高い米を食べはっている、と聞いてますが、ほんまでっしゃろか。」
年若い農民が聞く。
「それで何んと答えた?」
年配の農民が言う。
「一概には高いとは言えませんがな。米は相場もんや。高い時もあれば安い時もある。けど藩内の米はいつも価格が決まっている。だから高い時もあれば、安い時もある。例えば加賀藩が米の津留めをすれば大阪の米価格は吊り上る。その時狭野藩では安い米を食べているということになりますな」
もう一人の中年の農民が聞いた話だが、と前置きをして話したことはとんでもないことだった。
「米が豊作の時、京都では米の食べ残しが道端に雪のように捨てられる。ところが凶作の時は餓えで死んだ者が枯れ木のように道端に捨てられる」
年配の農民は講の皆に向かって言った。
「ワシらの藩は農民も工人もそして商人も大切にしてくれる。病気の時も、山崩れ、川の氾濫の時も、そしてワシらの日々の暮らしも護ってくれる。殿様もその御家来も、我らは藩民の友になる、と言われている。藩がこの度打ち出した政策もすべて藩を豊かで、生き甲斐のある国にするためだ。殿は我らの声を磨きの砂にするとも言われた」
藩内の米の価格を維持するためには商人の協力も欠かせない。天岡たちは藩内の商人を集めて、この度の藩の政策を説明した後で、こう付け加えた。
「藩経済の土台は米であり、藩の経済を発展させるものは主要農産物と特産品である。藩内で流通する米は藩が買い上げる。一方主要農産物についても藩内で販売する場合はすべて最低価格以上で販売することになるが、他所、他藩に売る場合は藩の物産総会所を通して販売することとする。値段は商いで相手もあることだから商人が決めた価格で販売して貰って結構だ。なお藩の良品証明書を発行して添付するので、その手数料を別途決めることとする。最後に藩札だが、今後とも何かとご公儀の普請など出費が続く。藩札の発行は必ず米の裏付けに基づいて行なう。最後に商人にも冥加金ではなく、農民と同じように年貢に相当するものを藩に納めて貰うことになる」
最後のところで商人たちがざわついた。
年配の商人が聞く。
「天岡様、年貢に相当するものとはどんなもんでしゃろか」
天岡は答える。
「当世は士農工商と言われている。しかし我藩は士も農も工も商も藩を護り、支え、守り立て、また互いの立場・役割を尊重し、協力し合っていくということでは皆同じだ。今迄商人のための税がはっきり決まっていなかった。そこに賄賂など腐敗の温床も生まれた。商人は屏風ではない。藩内のモノの流れを潤滑にし、必要としている人に必要なモノを届けるために、なくてはならない藩民なのだ」
また他の主要生産物について設定した最低価格制も効果を上げている。これらも藩が買い付けて他藩、江戸、大阪で販売を開始した。まず以前から続いている松前藩向けの稲藁で編んだ草履は順調に販売を伸ばしている。泥炭の鉱脈の調査が終った。狭山藩の幾つかの場所で試掘した結果、狭山池周辺地域の多くの泥炭層があることが分かった。米ぬかと一緒にしたボカシをまず藩内の農地で使っているが、特に畑地では効果が大きく、葉物が良く育つ。しかし、採掘すれば無くなっていく資源なので、計画的な生産が必要となる。
生糸については以前外国に輸出していたが、それが難しくなるので今後は生糸の原糸ではなく、反物にして大阪、江戸向けに販売することにした。今まで狭野藩にとって大きな収入源であったが、今後は国内向けとなる。どのようなものが売れるか、現在日本橋の荻屋にいる戸部新之助が調べているところだ。戸部からの報告では、絹織物は大名、豪商など販路が限られているので、狭野藩としては江戸の町人が好む柄の木綿の反物の生産に力を入れるべき、とあった。
今迄生糸中心の生産であったので、木綿の生産には特に力を入れていなかったが、藩内で以前から木綿を生産して、自分達で着物を作っている農家が多かった。幸いなことに木綿を増産するための素地はあった。そこで生糸を生産している農家には反物迄つくるように指導した。京都から反物職人を呼んできて、指導にあたってもらっている。木綿は作付け面積を増やすと同時に、こちらも反物にするために伊勢から職人に来てもらい指導を受けている。これからは原糸ではなく、反物に加工して販売する、というのが基本方針となった。さて新しく始めた特産品の目玉になるのが、薬草の栽培と販売であった。薬草については奈良の薬師寺に縁のある薬種店から職人を招き、山間部の傾斜地帯を視察してもらい、栽培できる薬草につき指導を受けた。氏安の願いは、薬草を使い、藩民の健康を守ることであった。将来藩内を巡り歩く薬売りが藩民の家を定期的に訪れ、薬箱を置いてその都度必要な分だけ使ってもらう。薬売りが訪れた時に支払い、また使った薬種の効果を薬売りに話してもらう。そんな仕組を考えていた。そればかりではなく、薬種を使った薬湯の温浴施設の開設も計画している。農民は一日の農作業の後、薬湯に漬かって疲れを癒す。山の泉の近くに施設をつくり、使った湯は一度ため池に集め、冷ましてから川に流すこととした。勿論農民だけではなく、工人も商人も、侍も使うことができる。竈で一斉に湯を沸かし、いくつもの泉水を湛えたヒノキの風呂に湯を注ぐ。竈の薪は山の枝落としで集めたものを使う。薬湯は藩民の憩いと交流の場にもなろう。
狭野藩の藩庁には、泥炭小組、生糸・木綿反物小組と薬湯小組が置かれた。
第57話 新之助 商売に励む
新之助が店でいつも考えているのは「売れる商品」をどうやって早く見極めるか。もう一つは売れている商品の在庫切れをどのようにして防ぐか、だった。お客様が買いたいと言うのに商品がないのでは話にならない。それではお客様に申し訳ない。かと言って必要以上に仕入れて売残りを出すわけにはいかないので、ことはそう簡単ではない。そこで新之助はまず2つのことを考え、実行していた。
まず第一は毎日の品物を項目毎に分けて、売れた数字とどんな人が買っていったかの記録をつける。それを1週間毎に表にした。売上が伸びている品物もあれば、減っていく品物もある。購入客については、絵文字を考え、売り場では懐に入れた紙にその都度項目別に絵文字を書き、記録した。目的は品物の売れ行きの傾向をつかむことであり、お客様の客層の増減の把握であった。
もう一つはお客様について良く知ることだった。お客様の名前、家族構成、体型、年頃、住んでいるところ、店との付き合い、品物の好み、その他気がついたことを「知客帖」と名付けた帳面に書き付けていった。目的はお客様の購買傾向を知ることであった。
新之助のこの考えは誰から教わったものでもなく、彼自身の下屋敷での青物栽培の経験から着想したものであった。
青物の栽培について当時世話になっていた郷助から次のように教えられたことがあった。
「新之助様。青物は種を播いてから収穫し、そしてまた種を採る迄には随分かかります。子供の成長と同じでドンドン変っていきますだ。そこでその都度その様子を月日と合わせて書き付けておくと役に立ちます。例えば種播きです。いつ種を播いた、いつ芽が出てきた、芽はどの程度出たか。種を播いたからと言って全部が全部芽を出すわけではありません。発芽率と言いますが、良い場合と悪い場合があります。また去年採った種の方が一昨年採った種より良く芽が出ます。」
郷助の家に呼ばれて夕餉を一緒にとった時、郷助が奥の部屋から紙をとじ合わせたものを持ってきて、新之助に見せた。
「私はこんな風にして毎回、毎年青物の栽培を書付けてきました」
分厚い大福帖のようなものだった。
「中を見せてもらってもよろしいですか」
「どうぞご覧になってください。何しろ忙しい中書き付けていますので、字とか数字が汚なくて読みにくいでしょうが・・・まあ自分が分かればいいということで書いていますのでご容赦ください」
新之助は紙を繰っていった。ところどころ絵を描き添えたものもあった。新之助は顔をあげて郷助に言った。
「それにしてもこと細かく記録しているもんですな。ヒバリが鳴いたとか、蜘蛛が巣を張ったとか・・・」
郷助は良く気がついてくれたと言わんばかりに、
「新之助様。お侍さん方にとってはヒバリとか蜘蛛は日々のお勤めには何の関係もないでしょうが、百姓にとっては大有りなんです。私らは大きくは山の姿、桜、ヒバリなど木とか草とか、蛙などの小さな生き物、そして鳥の様子などを農作業の、それぞれ大切な印にしています。蜘蛛は野菜をたべる害虫を食べてくれる益虫です。皆さんにとって蜘蛛はちょっと陰気な生き物でしょうが、私らにとっては大切な味方です」
「そうなのか。百姓は自然と共に生き、仕事をしていると聞いたことがあったが、本当にそうなんだな」
「それはそうとして、新之助様。記録をつけることです。天気も季節も毎年少しづつ違います。10年間農作業をすれば殆どの変化が分かるようになると言われていますが、その変化をすべて会得すれば、一人前です。そしてもう一つ大切なことは青物、根物のそれぞれの特徴を知り、どうしたらうまく育ち、沢山収穫できるかを学ぶことです。水を沢山欲しがるもの、水を枯らし気味にした方が良いもの、それぞれ違います」
新之助は狭野藩の江戸下屋敷で青物組の一人として日々のお勤めの前と後、前栽畑で農作業をしていた。郷助の家で夕餉の後、話を聞いてから、早速青物の栽培記録をつけるようになった。「この青物は殿が下屋敷に来た時食べるのを楽しみにしておられる」。青物組頭の高田修理からは度々そのように言われていた。失敗は許されない、ということでもあった。新之助は栽培記録をつけるようになってから、青物栽培にやりがいを感じるようになった。日々の青物の生長を観察する目付きも変っていった。二人一組の相手は木賀才蔵だった。当時の木賀は気をやんでいたが、新之助には「記録を取ることはいいことだ。問題はそれを続けられるかだ、頑張れよ」と言ってくれたことを思い出す。新之助は記録をとりながら自分なりにいろいろと創意工夫をした。農業には素人の侍がやる青物栽培だ。表をつくったり、絵文字をつくったりした。幸いなことには新之助には絵心があった。作業の段取り、流れを絵巻物のようにつくり、そこに書き込みをしていた。
新之助は日本橋の呉服商「萩屋」2階の自分の居室で当時のことを懐かしく思い出し、呟いた。「あの時は農作業の後に記録をつける、というのは辛い仕事だったが、今こうして役にたっている。人生はなにがどこで役にたつか、分からないものだ」
新之助は番頭の繁蔵付きで店の仕事をしていた。一日の商いが終った後、繁蔵は新之助と短い時間だったが、毎晩話し合った。これは繁蔵の方から言い出したものだ。最近の新之助の仕事振りを見てのことだ。何をどのくらい仕入れるか、そして何を新しく仕入れるか、この2点について繁蔵は新之助の意見を聞いた。新之助の記録がモノをいいはじめていたのだ。繁蔵が言う。
「新吉さんの見通しは良く当ります。売上は増えるし、在庫は減るし、今迄無かった新しい品物も加わりお店の帳尻も大分良くなってきました。」
繁蔵は新之助の「知客帖」を見て、びっくりして言った。
「このようなものは今まで見たことはありません。新吉さんはどこでこのようなやり方を学んだのでしょうか」
新之助は答えた。青空の下の畑で学んだことです。そして百姓の皆さんからも実に多くのことを教えてもらったのです。それがこの呉服のお店で商いに役に立とうとは思ってもみませんでした。」
繁蔵が新之助に言った。
「新吉さん、私にも表の作り方と読み方を教えて貰いたいのだが」
新之助は即座に答えた。
「喜んで。まだまだ改良していかなければと思っています。こちらこそいろいろご指導をお願いします。」
隣の部屋で主人の徳兵衛が二人のやりとりを聞いていた。
「新之助さんは侍にしておくのは勿体無いないお方だ・・・さてさて」
第56話 才蔵と波江の出会い
才蔵は少しずつ生きる自信を持ち始めていた。「自分も人の役に立つことができる」この思いをやっと実感として持つことができるようになった。しかし、一方で才蔵は自分自身のこころの弱さを抱えたままでいた。それは人には言えないことでもあった。以前次郎太には話したことがあった。確かに頭ではどうしたら良いか、わかるのだが、生来の弱さを克服するのはなかなか出来ないことだった。強くならなければならない、そう自分に言い聞かせるのだが、すぐ崩れていく自分がいた。
ある雨の日、町に出かけた。和算の関係の本を買うためだった。古本屋で本を探していると、坊さんも和算の本を探していた。
「子供向けの和算の本がないかと思って探しているのですが、なかなか見つかりません。大人用はあるのですが、子供向けというのはありませんな」
坊さん、実は慈光和尚だが、呟くともなく、話しかけるともなく、言った。
才蔵は答えるともなく言った。
「そうですな、和算道場向けの虎の巻のような本はありますが、子供向けとなると少ないでしょうな」
才蔵は言葉を継いだ。
「ところでお見受けしたところ、僧籍の方のようですが、何か心が落ち着くような教えの本があれば読みたいのですが・・・、何かありませんか」
慈光和尚は才蔵の顔を見ながら、こう言った。
「袖摺り合うも何かの縁、いや仏様が結んでくださった縁でしょう。私の寺はここから歩いてもそんなにありません。ちょっと寄っていかれませんかな。寺でお話を伺いたいと思いますのじゃが、いかがですかな」
「突然伺ってよろしいのですか」戸惑う才蔵に慈光和尚は笑顔で答える。
「寺は人々のためのものです。いつでもどなたでも遠慮は無用です」
町を出ると周りには田畑が広がっている。一本道を慈光和尚と歩きながら、才蔵は不思議な感じに包まれていた。傘をさして小雨の中を一緒に歩く和尚との会話はまことに少ないのだが、なぜか気持がほどけていくようだ。才蔵はその時、京都の寺の門に書いてあるとか聞いた句をふいに思い出した。「仏とは解けることなり まんじゅしゃげ」
ほどなくして寺に着いた。子供達が和尚を迎える。ちょうど波江の寺子屋が終ったところだった。波江も急いで髪に手をやりながら出てきた。才蔵に頭を下げてから、波江は急いで水屋に行き、薬缶で湯を沸かし、香のものと一緒に茶を運んできた。
和尚が波江を紹介する。
「波江さんといいましてな、私の寺で子供達のために読み書きの寺子屋をやっていますのじゃ。最近和算を子供達に教えたいと言われるので、それで何か良い本は無いかと思い、古本屋に探しに行った・・・という訳でしてな」
「そうですか、寺子屋をされているのですか」
「波江さんが読み書きを教え、簡単な和算を教え、そして農作業も教えていますのじゃ」
傍に座っていた波江は急須から二人に茶を注ぎながら、
「子供達から言われましたの。自分たちにも読み書きを教えてほしい、と。それが寺子屋を始めるキッカケでした。ここにいる子供達は皆それぞれ訳があってここにきました。私は少しでも子供達のためになればと思い、お恥ずかしいくらいの知識しかないのですが、子供達に読み書きを教えるようになりました」
和尚は寺の前に広がる畑に目をやりながら、言う。
「波江さんはこの寺の畑の手入れも子供達と一緒にやってくださっている。ご自分の畑だけでも、ほれ、あちらの畑ですが、忙しいのに、本当にありがたいことです」
波江は口に手を当てて、下を向いたまま言う。
「和尚様が子供達を本当に大事になさっているんですよ。素直で働き者の子供達です。子供達の助けが無かったら、私一人ではとてもできません」
才蔵が恐る恐る聞く。
「お見受けしたところ武家の方のようですが・・・・」
波江は答える。
「それも昔のことでございます。子供の頃学んだ読み書きが、今役に立っています」
和尚が波江に語りかける。
「このお方とは古本屋でお会いしました。私が子供向けの和算の本を探していたら、ちょうど隣でこの方も和算の本を探しておいでだったのだ。何かこころの力になるような本がないかとのお話だったので、わざわざ来ていただいたのじゃ」
才蔵は和尚と波江に頭を下げた。
「お恥ずかしい限りです」
「いやいや皆そうですじゃ。こころに安心と力づけを求めています。こんな時代ですからのう」
「それでは私はこれで」と言って波江は子供達と一緒に畑に出ていった。
才蔵は波江の後姿をいつの間にか追っていた。
「ところで、何かこころが落ち着くような本と言われていましたが、もしよろしかったら、今の気持を伺わせていただけますか」
和尚の言葉に才蔵は促されるようにして、自分をどのように考えているか、話し始めた。和尚は相槌を打ちながら、聞いている。
寺の前の畑では波江と子供達の姿が見え隠れしている。
「私の一番の問題は、リンゴに例えるなら中心の芯が腐っている、ということなのです。ですから何をやっても、途中で興が醒めてしまうといいますか、もうあとはどうでもいい、という気持になってしまうのです。ですから何をやってもモノになりません。そうこうしている内に自分が信用できない、というか、どうしようも無い人間に見えてしまうのです。つまりどこまで行ってもニセモノの人間でしかない。」
和尚は言う。
「とてもそんな風には見えませんが、さてさて人というものは難しいものですな」
才蔵は次郎太のことを話した。
「そんな私でも次郎太さんと話しているとなぜか生きる力が湧いてくるのです」
和尚は才蔵に聞いた。
「そのような方が傍にいるのですか。ありがたいことです。ところで、何か心休まる本ということですが、もしよろしかったら、時々拙僧と話をしていただけませんか。才蔵さんは今、本を読むことより、顔と顔を合わせて人と話をすることの方が大事かなと思いますのじゃ」
才蔵は月に1回ぐらいなら、郷助と次郎太に相談すれば大丈夫かと思ったが、念のためを考えた上で、答えた。
「ありがたいお話です。仕事のこともありますので、また後日ご返事させて頂きます」
和尚は優しい笑顔で才蔵を見つめた。
「才蔵さん、人生は楽しく、ですぞ」
波江と子供達が収穫した野菜を籠に入れて戻ってきた。和尚は一人一人の子供を抱いて声をかけている。
波江は才蔵に頭を下げた後、和尚に声をかけた。
「それでは私はこれで失礼します」
和尚は波江の後姿を見ながら、才蔵に聞かせるともなく言った。
「あの人はこれから自分の畑での農作業をした後、娘さんと一緒に野菜の行商に出てそれからまた寺に来て、私と子供達のために夕餉を作ってくださるのじゃ」
第55話 郷助の作業場
郷助は次郎太と孝吉そして才蔵に田畑を任せ、自分は作業場で車椅子、義手、義足の製作に追われていた。注文が日ごとに増えていった。郷助は作業を手伝う弟子の育成にも努めていた。そして今迄全部の部品を一人でつくっていたが、作業を幾つかの部分に分けて、それぞれの部分を助手に担当させた。最後の仕上げは郷助が見た。まだまだやり直しをさせることが多い。この幾つかの部分に分けて、助手に担当させ、全体を郷助がまとめる、というやり方は才蔵の助言によるものだった。その結果、仕事が捗り、増えていく注文を納期どおりこなすことができるようになってきた。そして最近この作業場に助手として入った大船渡出身の源次は手先が器用で、仕事をドンドン覚えていった。
作業場の片隅に木の机と椅子が置いてあり、そこで郷助は相談に来た客に応対していた。
客が言っている。
「義足の方は今のところ困ってはいないだよ。ただつないだとこを固く縛るせいか、日によっては痛い時もあるけど、我慢すれば大丈夫だ。ただ手の方はもう少し使えるようになればいいだ。使える左手でこうやって右手の指を曲げて木の匙で飯を食っているだが、少しゆるいせいか、匙が落ちてしまうだ」
郷助は一つ一つ話を丁寧に聞いている。
「足が痛いというのはつらかんべ。当るところには内側に何か柔らかいものを貼ってみべ。それから指だが、今指の一番目の関節と2番目、3番目の関節のところが義指でも曲がられるように考えているだ。暫くかかるが、待っててくれ」
相談に来た客にタケが茶を運んできてもてなす。郷助は話を聞いている。そして助手は客の足と指を摩り、揉んでいる。
「おらあ、ここに来るとホッとするだ。こんな片輪になった者でも郷助さんたちのお陰でこの人生、生きて生き抜いてみよう、そんな気持になるだよ」
休憩時間に茶を飲みながら、郷助は助手の一人一人に声をかけた。郷助は一切叱らない。褒めるのだ。どんなに小さなことでも褒める。その上で必ず言う。「この仕事は事故で手足を無くした人が少しでも人並みに仕事をし、生活できるように、そして生きていて良かったと思えるように手助けするためだ。」
郷助は少し離れたところに座って茶を飲んでいる才蔵にも声をかける。
「才吉さん。皆で分担して仕事をして、それをまとめる、というやり方はとてもいいだ。随分捗るようになったし、皆の技量も上がってきた」
「それは良かった。それぞれが自分の仕事をまずきっちりやり遂げながら、あわせて前後の仕事をしている仲間の仕事とのつながりのことも考えていけば、更に良くなっていくでしょう。一日一回そのための打ち合わせの時間をとったらどうでしょうか。」
「たしかにそうだ。全部をうまく組み合わせるためには過不足があってはいけない。それでは昼飯の後、暫くの時間、すり合わせのための打ち合わせを持とう。皆どうだ?」
助手達は全員賛成だ。
郷助は2つのことをいつも考えている。一つは助手たちには長時間作業を強いないようにする。そのためにはより短い時間で、より良いものをつくる仕組みが大事だ。もう一つは助手達はいずれ故郷に帰る、ということだ。故郷で車椅子、義手、義足の作業場を持つことになるだろう。なぜなら皆一人一人の様子に合わせて製作する、注文生産だからだ。また使っているうちに手直しも度々ある。遠くの人が旅費をかけてわざわざこの郷助の作業場迄来る、というのは無理な話だ。弟子を育て上げ、その弟子たちがそれぞれの場所で作業場を開けるようにしたい、というのが郷助の願いだった。
それで郷助は助手達が仕事を終えて、夕食を取った後、助手のために塾を開いていた。塾長は郷助、副長は才蔵だ。郷助は車椅子、義手、義足の作り方について、また作る場合の心構えについて分かりやすく説明する。そして問いを出して考えさせる。
「俺の弟、次郎太が戦さで足に大怪我をして、両足なくしてしまった。その時次郎太は何を考えたと思うだ。」
「義足をつけて歩くと痛みが出やすいところが必ずある。それはどこだと思う」
「義手をつけても何にもできない、恰好だけだと言うものがいる。手はそれだけ複雑な動きをするところだ。人が義手をつけていの一番にしたいことは何だろうか」
そして副長の才蔵。
才蔵は、材料の仕入れ、保管、帳簿付け、収支の計算を、事例を使って説明する。また農民、職人が車椅子、義手、義足を購入するための「講」制度づくりについても解説する。
塾が終った後、それぞれ風呂に入って消灯、となる。タケは郷助家族だけではなく、助手の世話もあり、毎日忙しくしていた。
フトンの中から郷助はタケに声をかける。
「タケ、夜明けから夜遅くまで、苦労をかけるな。」
「父ちゃん。父ちゃんこそ身体に気をつけるだ。おらは大丈夫だよ。次郎太さんも 元気に野良作業をしているし、孝吉もしっかりしてきたし・・・おら何だかこういっちゃ父ちゃんには申し訳ねえが毎日が楽しい。そして才蔵さんが見違えるように元気になったのも嬉しいだよ。」
「そうだな、本当にそうだ」
才蔵は床に入る前に作業場の見回りをした。以前作業場に盗みが入ったことがあった。金が置いてあると思ったのだろう。物音がしたので、才蔵が最初に作業場にかけつけたが、侵入者は逃げた後で捕まらなかった。しかし、逃げる時、ニカワの入った鍋に足をひっかけ、土間にはニカワが流れていた。
才蔵は丑三つ時、もう一度起きて、作業場の見回りをするようになった。郷助さんの作業場は何が何でも護らなければならない。
作業場に金がないと分かればいつ何時母屋の方に侵入してくるとも限らない。才蔵は作業場と母屋、両方に注意を払っていた。以前侵入してきた者は一人だったが、今度は仲間を一緒に連れてくるかもしれない。このことについては郷助だけに話した。タケを心配させたくなかったからだ。
才蔵は枕元にいつも木刀を置いて床についた。
第54話 氏安 天領桑名村立て直し その二
氏安は床下に人の気配を感じた。天岡と叡基に声をかけた。「今日は日和も良い。どうだ、外に出て、歩きながら話の続きをすることにしょう」3人は外に連れ立って出た。藩庁の横に大きな池がある。狭山池の水を引き込んで作った約2反分ほどの大きさで、瓢箪のような形をしていて真ん中に赤い橋が架かっている。橋の中央部迄来た時、氏安は足を止めた。そして小さな赤い橋の上に腰を下ろした。
「腰を下ろしたら良い」
二人は促されて座った。
「ワシは御料地の経営に命がけで当る。それが今戦乱のない平和を築き挙げている徳川幕府へのワシのご奉公の道なのだ。天岡と叡基殿には苦労をかけるが、知恵を絞り、力を尽くしてほしい」
氏安は大きな声で自分の決意を二人に伝えた。二人は言った。
「畏まりました。私達も命がけで働く所存でございます。何なりと仰せください」
氏安は藩庁に隣接している木立に隠れている何者かに、微笑むように目を向けた。
「梢の上を鳥が飛んでいる。新緑が美しい季節になった」
翌日から天岡と叡基は打ち合わせを開始した。これからの段取りについて話合った。
1.これからどのようにして桑名44村の米の生産力を上げていくか。これを大目標にする。米の量だけでなく質の向上もはかる。
2.堤防の工事は朝明川の右岸から始めるが、そのための土は近くの山から持ってくる。
そのための道作りと土の運搬のための荷車と人足の手配
3.桑名村の米づくりの名人達を集めて表彰する
4.44村の村請制の検基準を見直し、公平な基準をつくる
5.段取りがまとまったら、庄屋、大庄屋、代官の順で説明し、意見を聞く
特に御料地では大庄屋の存在が大きい。大庄屋の協力が得られなければ、改革は進まない。天岡と叡基は庄屋、大庄屋が納得し、協力してくれる案をまとめなければならなかった。少しでも御料地の桑名村で騒ぎが起きれば、幕府のお咎めを招くことになり、それはどうしても避けなければならない。しかも朝明川の普請は全部狭野藩の負担であった。小さな藩にとっては厳しい負担である。それでも叡基には考えがあった。普請はできるだけ地元の農民にやってもらう、このことであった。朝明川の普請は川の水嵩が低くなる冬場に行ない、農閑期に野良仕事の少ない地元の百姓に人足として働いてもらう。江戸の大川と違い、川幅も狭く水量もずっと少ないので、3ヶ月もあれば完成する
と叡基は見積もったが、問題は堤の地盤だった。海の近くの河口付近ということもあり、
地盤はゆるかった。現在の堤はあちらこちらで沈下しているところがあり、その上に嵩上げの土を載せると更に沈下に拍車をかけることになりかねない。
叡基は朝明川の堤の上を歩き、行ったり来たりしながら、調べていた。堤のあちらこちらにヒビが入っている。
「これでは遅かれ早かれ堤は決壊する。早く普請にとりかからねば。堤全体に松杭を打ち込まねばなるまい」
叡基は堺から土木測量に長けたものを呼び寄せることにしていた。そして朝明川右岸の百姓に堤の決壊個所と程度、それに水田の冠水被害状況を聞いて回った。
宿舎としてあてがわれた庄屋の離れで叡基は普請にかかる費えの見積作業に入った。狭野藩への負担をなるべく減らさなければならないが、あとあとのことを考えると、手を抜いた普請はできない。3日3晩、叡基は見積作業に没頭した。見積が出来上がった後、氏安に手紙をしたため、見積書に図面を添付して送った。
2日後、叡基からの文書を受け取った氏安は見積金額を見て、表情を引き締め、心中で呟いた。
「叡基殿がつくった見積だ。無駄も足らずもあるまい。御料地で手抜き普請をやったとなれば大事となる。普請の期間は半年だ。今迄の蓄えを使えば何とかなるが、それをそのまま使えば、幕府からどのように思われるか、しれたものではない。ここは思案のしどころだ。」
氏安は藩庁の勘定方から朝明川堤普請の勘定を担当する、松本岳之進を呼び、見積書の内容を詳細に把握しておくように命じた。
「松本。明後日迄の桑名に向けて出立せよ。これから1年間叡基殿の下で普請の勘定方を務めるのだ。堺から測量を担当するものも近々桑名に向かうであろう。そのものも我狭野藩の出身の者で、叡基殿が堺に測量の勉学に行かせた者だ。これから1年間、叡基殿を中心に3人で力を合わせて、御料地での普請を立派にやり遂げるのじゃ」
氏安にとって一番神経を使わなければならない問題は「村請制」の石高だった。最終的な目標は44村の村請制の検基準を見直し、公平な基準をつくる、であったが、それを公にする訳には行かなかった。徳川幕府の石高制の根幹に触れる問題なのだ。太閤検地以降、何度か検地があったが、石高は常に過分に評価されていた。実質石高が例えば200石でも、250石と高めに見積もられ、それが基準となった。御料地は四公六民であったが、250石とした場合、農民は実質100石を年貢とし納めなければならない。従い農民に残るのは100石だった。四公六民という割合については不満はないが、過分に評価されている石高には根強い不満が燻っていた。幕府は一旦決めた石高については、変更はありえなかった。ある御料地で農民の窮状を目の当たりにした代官が何度も幕府の石高替えを上申したが、受け入れられず上申に出かけた江戸の屋敷で切腹するという事件も起きた。氏安に残された道は一つしかなかった。幕府によって定められた石高にできるだけ近づくように増産活動を奨励する。増産することによって農民の実質収入を増やし、同時に年貢も増やす。その一つの方法として氏安は狭野藩の特産物である腐植質を沢山含んだ泥炭と米ぬかを独自の方法で混ぜてボカシた肥料を桑名44村の田圃で使うことにした。それも勿論、狭野藩の持ち出し、負担となった。早急に成果を上げて桑名村民の意気込みを上がる必要があった。物事を成功させるためには勢いというものが大きな意味を持っていることを氏安はわきまえていた。また増産をするためには稲の優良品種選抜も欠かせない。病虫害に強く、味の良い米だ。年貢は1村の村請制だから農民にとっては連帯責任なので、1村の中での優良品種を農民の間に広げていくのは左程大きな問題はないだろう。しかしその優良品種の稲を栽培した者には何らかの褒賞を準備しておかなければなるまい。
氏安は頭の中でさまざまに思い巡らしていた。ひとしきり思案をした後、氏安は考えたことを紙に書付けてから天岡を呼んだ。
「天岡、これを読んでくれ」
天岡は黙って読んだ後、一言で返事した。
「よろしいかと存じます」
「しかと内容を覚えたな」
「しかと」
それを聞いた氏安は湯を沸かしていた火鉢に書付けをひねってからくべた。書付けはめらめらと燃えて灰になった。
氏安は天岡に目配せし、天岡は黙って頷いた。
« Older Entries Newer Entries »